よい新年を
 皆の衆、どんな大晦日をお過ごしですか。粗忽天皇は今年も自家製アップルパイを食べてご機嫌じゃ。よい新年を迎えるのだぞ。来年も大いに遊んでくれたまえ。
皆の衆、どんな大晦日をお過ごしですか。粗忽天皇は今年も自家製アップルパイを食べてご機嫌じゃ。よい新年を迎えるのだぞ。来年も大いに遊んでくれたまえ。
2015年12月31日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十七回
赤枯れした草木を踏みしめて走り去る銭形を見送った赤垣は納屋に向かった。騒ぎが収まってほっとした筒井は赤狩衣から顔を出した。
「おまえさん、筒井というのか」
「はい。筒井康隆と申します。小説家です」
「文学者か。で、警察に追われとるのか」
「これにはわけがありまして……」
「いやいや、何も言わんでええ。筒井を名乗るのは世を忍ぶ仮の姿だろ? おまえさんは神様だ」
「いいえ、ただの人間です」
「人間が天から降ってくるはずがない」
「いえ、ですからわたしは……」
「つべこべ言わんで、神様は神様らしい格好しろ」
主人は赤狩衣を剥ぎ取り、頭陀袋も脱がせて筒井を丸裸にし、赤革を何枚も繋いでこしらえたロングコートのような服を着せた。革と革は鎧の赤革縅のような紐で結ばれている。主人は着替えさせ終わると筒井の前におずおずと小さな壺を置いて正坐した。中には香りのよい水が入っている。
「これをわしの頭にそそいでくれ」
「この水を、ですか」
「そうだ。わしは長年密教の修行をしてきた。修行が完成すると頭に香水をそそいで修行が完全に終わったことを証明するんだ。閼伽灌頂という儀式だ」
「修行、終わったんですか」
「ああ」
「おめでとうございます」
「ありがとう。さあ、早くそそいでくれ」
「でも……密教って仏教の一派ですよね? 仏教には神の概念はないはずでは……」
「細けえことはええ! わしの眼の前に神様が現れた。神様が現れたということはわしの修行は完成したんだ。さあ、早く」
筒井は腑に落ちなかったが言われるがままに壺の水を手にすくって主人の頭にそそいだ。厳粛な儀式だから何か唱えたほうがよさそうだと思い、とりあえず「アーメン」と呟いて十字を切った。主人は皮をけずった赤木の柵をくぐってひらりと馬に乗った。
「どこかへお出かけですか」
「赤城に行く」
「アカギ?」
馬が前脚で足掻きを始めた。
「赤城湖だ」
「赤城湖……? ひょっとして群馬県の?」
「そうだ。赤城山の麓だ。密教の修行を終えた者はみんな赤城へ報告に行く」
「群馬に密教の聖地があるんですか? 初耳だなあ」
「わしが嘘をついてるというのか? 本当の話だ。わしはおまえさんに隠しだてはせん。万葉集にもあるだろう、『隠さはぬ明き心を神様に極めつくして――』」
「聞いたことありません」
「とにかく、わしは出かける」
主人は赤木の材で作った刀の赤木柄を握りしめ馬の横腹を蹴ると馬はたちまち納屋を飛び出して駆け出した。あとにひらひらと一枚の赤い紙が落ちた。筒井が拾い上げてみると赤切符である。汽車の三等乗車券ではないか!
妙だぞ。主人はたしか、いまは元禄十五年だと言った。鉄道が開通するのは明治だ。時代が合わないじゃないか。しかしよく考えてみると主人の名は赤垣源蔵で忠臣蔵狂言の登場人物だから、あくまでもフィクションの世界の住人だ。ということはつまり俺はフィクションの世界にいるのだろうか? 赤衣をまとった筒井は呆然と立ちつくした。頭が混乱してきた――ちくしょう、俺はいったいどこにいるのだ? それもこれも作者のせいだ。諺にも言う通り、赤きは酒のとが、顔が赤いのは酒のせいで自分の罪ではない、悪いのは他人すなわち作者だ。作者のやつめ、どこかで見かけたら首をへし折ってやる――
「ああら吾が君、ああら吾が君」
赤城山へ向かって去った赤垣の女房が筒井を呼んだ。相変わらず両手をなでさすっているところをみると皹がよっぽど痛むらしい。
「なんですか」
「赤色を帯びた金と銅の合金を俗になんと申しましたっけ」
「藪から棒ですね。ひょっとして赤金のことですか」
「そうでした。ありがとう」
「どういたしまして」
納屋の壁の向こうにケロケロとカエルの鳴く声が聞こえる。蛙楽を耳にするのは久しぶりだ。筒井が戸口から出て家の裏に回ると水田があり、カエルが畦道に出ようと足掻いている。屋内に戻ると女房はあかぎれの特効薬か、人参と辰砂を混ぜて作った赤薬をごくんと飲んだ。壁には赤具足と呼ぶのだろう、主人の甲冑が揃えて置いてあり、隣には女房のものらしき赤朽葉の襲がかけてある。
突然ドドドドッと地響きがしたかと思うと巨大な獣が戸を蹴破って闖入した。
「ひい! 赤熊じゃ!」
女房が叫んだ。ヒグマだ。熊はひとりしきり暴れ回ると女房を見つけてがぶりと頭からかじりつき、あっという間に食い殺した。肝を潰した筒井が手探りで床を這いずる。舟底にたまった水を汲み取る淦汲みという柄杓が手に触れたので迷わず握って応戦し、闇雲に振り回すと熊の頭に命中し、当たり所が悪かったとみえて熊は脳震盪を起こしたのか、ばたりとくずおれた。筒井は命からがら外に出た。折よく辻駕籠が通りかかった。
「おい、乗せてくれ」
「へい。どちらまで?」
「赤倉温泉」
「赤倉温泉と申しますと、新潟県南西部と山形県北東部にありますが、どちらへ……」
「どっちでも構わない。早く出してくれ」
「へい!」
駕籠は伊勢を発して北へ向かった。
2015年12月31日 Part 1
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十六回
赤垣は土間と地続きの納屋に行き馬の赤鹿毛を撫でた。
「かわいそうに。赤瘡を患っとる」
「アカガサ?」
「麻疹だ」
「馬も麻疹に罹るんですか」
「馬も人間と変わらん。ただし馬の麻疹はブナ科の常緑高木赤樫の葉を煎じて飲ませれば治る」
農夫は赤烏帽子を脱ぎ、頭髪の赤茶けた赤頭をぼりぼり掻いた。「赤柏が炊けましたよ」夫人が柏の葉に盛った赤飯を筒井の膝元に置いた。
「お赤飯……何かお祝い事があるんですか」
「もとは十一月一日に炊くんだ。冬至の祝いだ」
「冬至は十二月二十二日頃ではありませんか」
筒井は相手の返事を待たずにはっと気がついた。十一月一日が冬至ということは陰暦だ。ではやっぱりいまは江戸時代なのか? しかし冬至にはまだ早いはずだ。さっき主人は赤とんぼが飛んでいるのを見て「もうこんな季節か」と呟いた。だからいまは夏の終わりか秋の初めのはずだ。赤垣は馬の腹の赤みがかった灰色に白い差し毛がある赤糟毛をやさしく撫でながら答えた。
「冬至はむかしから十一月一日に決まっとる」
「でもまだ先の話ですよね」
「そうだよ」
「ではなぜお赤飯を……?」
「めでたいからだ」
「何がです?」
「そりゃあ、おまえさんが空から降ってきたからだ。おまえさん、神様だろ?」
赤垣は赤い桐油紙でこしらえた赤合羽をふわりと羽織った。一張羅をまとってすっかり垢が抜けて見える。
「神様をもてなすのにこんな服しか持っとらんで、お恥ずかしい」
「どうかお構いなく。それにわたしは神様では……」
「銅をお供えしたいが、なにしろ浪人になって以来水呑み百姓だもんで」
「ですから、わたしは神様では……」
「何か銅色のものはなかったかのう」
主人は赤銅月代を撫でながら女房に「赤蕪はないか、おい、赤蕪を持ってこい」と命じた。すると戸口をトントン叩く音がする。女房が応対に出ると役人らしき男が紙切れを渡した。
「おまえさん! 赤紙だよ」
「なに?」
「召集令状」
赤垣は土間に降りて役人を睨みつけた。
「赤紙いうたら昭和十年代だろうが」
「そうですよ」
「いまは元禄十五年だ。時代が違うぞ」
「あ!」
「この粗忽者め。帰れ」
「失礼しました!」
主人はぴしゃりと戸を閉じた。女房は水仕事で皹すなわちあかぎれが痛むらしく手をさすっている。再び戸をドンドンと叩く音がした。主人が戸を開けるとスーツを着た人相の悪い男が二人立っている。
「赤垣はいるか」
「わしだ。何の用だね」
「こういう者だが」
男が手帳を見せた。「特別高等警察」と書いてある。
「共産主義にかぶれているそうだな。ネタは上がってるんだ」
「キョーサンシュギ?」
「とぼけても無駄だ」
「さては赤狩りだな」
「そうだ」
「馬鹿者!」
赤垣はどやしつけた。
「いまは元禄十五年だ。ロシア革命は二百年以上先の話だぞ」
「え!」
「顔を洗って出直してこい!」
「うーむ……迂闊だった……今回は見逃してやる」
「おととい来やがれ」
特高は不承々々退散した。まったく近頃の役人はどいつもこいつも時代を間違えおってけしからん――主人がぼそぼそ呟くと、またしても戸を激しく叩く音がする。
「誰だ!」主人は戸を開けずに怒鳴った。
「インターポールの銭形という者だ」
その声を聞いた筒井はギョッとした。咄嗟に家の中を見回すと壁に検非違使の下級役人が身につけていた赤狩衣が一枚かかっているのを見つけて迷わず奪い取り、頭からすっぽりかぶって納屋の片隅に縮こまった。主人は戸を開けた。銭形を名乗る強面の警部が部下を三人従えて立っている。
「何の用だ」
「この家に筒井という男はおらんか」
「ツツイ? さあ、知らんな」
「この家に隠れているという情報をつかんだのだが」
「そういえば――つい今しがた、知らない男が訪ねてきよった」
「こんな顔か?」
銭形警部は人相書きを示した。
「顔はよく覚えとらんが、スーツを着とったよ」
「その男なら私も見ましたよ」部下の一人が口を挟んだ。
「なに? どんな風体だった?」
「特高のようなスーツを着て、あっちに走って行きましたけど」
「ばっかもーん! そいつがルパンだ!――いや筒井だ! 追えー!」
銭形警部は部下を引き連れて走り去った。
2015年12月30日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十五回
農夫は九谷焼の赤絵だろうか、赤を主調に緑や青や紫の色鮮やかな陶磁器に焼き魚を二匹載せて筒井に「ほら、食え」と勧めた。
「これは……?」
「こっちが赤鱝。南日本沿岸で獲れる軟骨魚だ。そっちは赤狗魚。かまぼこの原料に使う硬骨魚だよ」
筒井は空腹のあまり手を伸ばしたが、すぐ手を引っこめた。いまが本当に西暦二〇一五年なのか、どうしても確かめたい。
「ご主人、いまどんな本が流行ってますか」
「本? 本ならこれだな」
農夫は本棚から二巻本を取りだして見せた。
「工藤平助著、『赤蝦夷風説考』……?」
「知らんのか」
「聞いたことありません」
「ロシア人が南下するのを見て、これからの日本はロシアと貿易したほうがいい、蝦夷地を開拓して国家の富を増やしたほうがいいって説いた本だ」
「いつ出版されたんですか」
「天明三年」
「天明三年って……西暦一七八三年じゃないですか!」
「そうだよ」
「じゃあ、いまは十八世紀末……」
「アホ! 古本に決まっとる」
「古本の話なんかどうでもいいんです!」
「ブックオフで買ったんだ。一冊百円。読んでみたら面白いの面白くないの、独り占めするのはもったいないから村中で回し読みしとる」
農夫の妻が茹でた赤海老を三匹持ってきた。筒井は焼き魚と茹で海老を食いながら考えた。ブックオフがありスマホがありツイッターもある――ということは間違いなく二十一世紀だ。なのに農夫は赤烏帽子をかぶっており、首から上はどう見ても平安時代の公家である。妻も妻で赤襟なんかかけている姿はまるで年若い芸者だ。
「おお、もう赤卒が飛んどる」
農夫が土間から外を眺めて言った。
「アカエンバ?」
「赤とんぼのことだよ」
土間からあがった農夫は鎧を脱いで赤い色の大口の袴、赤大口を穿き、仏に供える水を汲んで閼伽桶に入れ、赤縅が目に鮮やかな鎧を壁際に置いて袴の上から赤帯を締めた。服装になんの統一性も認められないところがじつに不気味だ。しかし身の回りの世話をしてくれた恩義があるから褒めておいたほうが無難であろうと筒井は思った。
「立派な帯ですね」
「こう見えても柔道十段だ。――おい、赤御魚を持ってこい。おーい、吾が御許」
「はーい」
妻が答えた。筒井はにはなんのことやらさっぱりわからない。
「いまのは……名前ですか」
「まさか。宮仕えをしている女を親しんで呼ぶ言いかただ。『吾が御許にこそおはしけれ』って源氏物語にもあるだろ」
「そうなんですか。よくご存じですね」
「田舎者を馬鹿にするもんでねえぞ」
女房が鮭の塩焼を持ってきた。
「アカオマナって鮭のことなんですね」
「そうだ。赤貝の刺身もあるぞ。食うか」
「いえいえ、もうじゅうぶんです」
「赤蛙はどうだ」
「カエルを食べるんですか」
「うまいぞ。鶏肉みたいな味でな。――おーい、赤酸漿をくれ」
「はーい」
女房はホオズキの枝を一本持ってきた。
「わしはこれから風呂に入るが、おまえさんも入るか」
「あ、はい。えーと、ではお言葉に甘えて。でも、あとでいただきます。お先にどうぞ」
「女房は垢掻をやっとったから、ゴシゴシ洗ってもらえ」
「アカカキ?」
「風呂で客の垢を落とす女だ。湯女とも呼ぶ。遊女も兼ねたもんだ。江戸の常識だぞ」
「江戸? そういえば、まだお名前を伺っておりませんでした」
「赤垣だ」
「アカガキさん……」
「赤垣源蔵だ」
「え!」
筒井は目を丸くした。いくら無知な俺でも赤垣源蔵の名は知っている。忠臣蔵を題材にした歌舞伎や講談、浪曲に出てくる人物だ。赤穂浪士の一人、赤埴源蔵をフィクションに取り入れた名で、講談の義士銘々伝「赤垣源蔵徳利の別れ」で有名だし、河竹黙阿弥の「仮名手本硯高島にも登場する。てっきりフィクションの世界の人だと思ったが、実在するとは……。
2015年12月29日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十四回
「お二人はご夫婦ですか」筒井は女に訊ねた。
「兄妹だよ」男が答えた。
「こいつは赤い信女だ」
「アカイシンニョ?」
「後家だ。三年前に夫に先立たれた」
男はなぜか鎧を身につけている。札を結わえた赤糸縅が目に鮮やかだ。
「見事な鎧ですね」
「これか? どうだ、似合っとるか」
「ええ。仮装行列か何かですか」
「落ち武者からくすねた」
「落ち武者?」
「ほれ、あそこの畦道でくたばっとったから、くすねたんだ」
筒井は胸騒ぎを覚えた。
「つかぬ事を伺いますが……いまは西暦二〇一五年ですよね」
「セーレキ?」
「平成二十七年、ですよね」
「ヘーセー? 何の話かわからんが、関ヶ原の戦いの真っ最中だ」
筒井は耳を疑った。
「関ヶ原の戦いなんて四百年以上もむかしの話ですよ」
「おまえさん、寝ぼけとるのか」
「えーと、えーと……赤い鳥はご存じですか」
「赤い鳥……? ヤマガラのことか?」
「いいえ、鈴木三重吉の児童雑誌です。大正七年に創刊されました」
「タイショー? 知らん」
「じゃあ……赤い羽根は?」
「ヤマガラの羽根か?」
「違います。共同募金ですよ。ほら、寄付した人が胸につけるでしょう」
「おまえさんの話はチンプンカンプンだ。天下分け目の戦いの最中だと言うに。どっちが勝つか賭けをしとるんだ。こいつは大権現様が勝つと言う」
「大権現様というと……」
「家康に決まっとる。わしは石田三成を応援しとる。あそこに赤色と青色の旗があるだろ。大権現様が勝ったら赤の旗、三成様が勝ったら青の旗があがるんだ。わしは青の旗がいつあがるか、いつあがるか、楽しみにしとる」
筒井は腰を抜かした。エジプトから日本に帰れてやれ安心と思ったら時代が四百年も遡ってしまった。
「おまえさん、そんな頭陀袋みたいな服着て畑をウロウロしたらイノシシと間違えられて鉄砲でズドンと撃たれるぞ。うちへ来なさい。息子の野良着がある」
筒井は農夫の家でブルカを脱いで着替えた。野良着にしては赤い模様が目立つ。
「ずいぶん派手ですね」
「赤色の袍だ。天皇や摂政、関白が着る上衣だ」
「え! あなたは皇族のかたですか?」
「アホ! 偽物に決まっとる」
「ですよね……」
「それを着とればイノシシと間違えられることはない。天皇だと思ってみんな土下座するよ。ははは」
農夫は糠をまぶして塩漬けにした赤鰯を振る舞った。腹ぺこだった筒井はむさぼり食った。
「うまい!」
「鳥羽の港で贖ひたんだよ」
「お代わりください!」
「よく食うなあ。赤鰯はないが、赤魚の焼いたのでよければ」
「ありがとう! むしゃむしゃ」
「赤浮草のおひたしもあるよ」
「ください! パクパク」
「よっぽど腹が空いとるようだな」
「ええ、なにしろエジプトで豆を食って以来飲まず食わずで……しかも気がついたら関ヶ原の戦い……」
「関ヶ原? あっはっは」
農夫はカラカラと笑った。
「あの話は赤嘘だ」
「え?」
「真っ赤な嘘だ」
男は納屋に繋いである赤馬の背を撫でながら笑い続けた。
「嘘? どうして嘘なんかつくんです!」
「だっておまえさん、空から降ってきよっただろうが。どう見ても怪しいよ。畑に大の字になって、わしはてっきり赤海亀の死体かと思った」
「これには訳があるんです」
「どういう訳か知らんが、妹はすっかり興奮して『天から人が降ってきたなう』ってツイッターで呟いたよ」
「ツイッター?」
「ああ。これ見てみい」
農夫は野良着の懐からスマホを取りだして見せた。
「妹さん、ツイッターやってるんですか!」
「やっとるよ。アカウント持っとる。田舎者だと思って馬鹿にするなよ」
筒井は目を白黒させた。じゃあ俺は現代の日本に戻ってきたのか……?
2015年12月28日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十三回
「あなたは……モーフィアス?」筒井は恐る恐る訊ねた。
「ローレンス・フィッシュバーンだ」
「それは本名でしょ? ここはマトリックスの世界だね?」
「マトリックス? 何の話だかわからない」
「でも映画で観ましたよ。あなたは救世主ネオを案内したでしょう。コンピューターによって管理された世界に」
「君はいったい何の話をしてるんだ」
「だから映画『マトリックス』ですよ。人々が現実だと思っている世界はじつはバーチャル・リアリティーで、本当の世界はコンピューターが管理している」
「バーチャル・リアリティーって、仮想現実のことか?」
「ええ」
「では君は、いま仮想現実にいるとでも思っているのか」
「そうです」
「バカバカしい。あれを見ろ」
フィッシュバーンが指さしたほうに赤赤と窓の灯がともっている。
「君はあの家を仮想現実だと言うのか」
「そうに違いない」
「じゃあ、これを見ろ」
フィッシュバーンは黒いズボンの裾をまくった。膝に大きな赤痣があり血が滲んでいる。
「さっき転んですりむいた」
「痛そうですね」
「痛いよ。ものすごく痛い。君はこれも仮想現実だと思うのか」
「うーん……バーチャル・リアリティーなら痛みなんか感じないはずですよね……」
「当たり前だ。その証拠に、君はいまアリを踏んづけただろ」
「え?」
「足下をよく見ろ」
筒井が右足を上げると、いつの間に踏んだのか、赤蟻が潰れてどす黒い体液が飛び散っている。
「仮想現実でアリが死ぬか?」
「なんだか頭が混乱してきた……」
筒井はわけがわからなくなった。すると平安絵巻から飛び出したようないかにもやんごとない男が現れて筒井に言った。
「アリを殺したのはそなたか?」
「え? あ、はい。あなたは?」
「亜槐だ」
「アカイ?」
「大納言の唐名だ」
「大納言?」
「太政官の次官だ。そんなことも知らないのか」
「まるで平安時代ですね」
「なにを寝ぼけたことを申す。いまは鎌倉時代である。先ほど『新古今和歌集』を撰定し終えたばかりだ。嘘だと思ったらひとつ歌って進ぜよう。『朝ごとの閼伽井の水に年くれて――』」
「アカイって何ですか」
「閼伽の水を汲む井戸に決まっておる。そなたは本当に日本人か」
筒井は正気を失いつつあった。俺はいまどこにいるのだ。俺は誰なのだ。わからない、わからない……。
突然あたりが真っ赤になった。白一色だった世界が赤い光に包まれたかと思うと、それまで立っていた地面が抜けて筒井は奈落の底へ落ち、また気を失った。
「あがいもこがいもない。ほれ、見てみい。空から落ちてきよった」
筒井が目を覚ますと畑の畦道のようなところに大の字になって寝そべっており、中年の男と女が顔を覗きこんでいる。
「ここは、どこですか」
「伊勢だ」女が答えた。
「伊勢? 伊勢って、伊勢神宮がある?」
「あたりまえだ」
筒井の眼のまわりを赤家蚊がブンブン飛び回り血を吸おうとする。手で追い払うと女が「これでも食え」と赤烏賊の丸干しをくれた。
「おまえさん、神様だね」
「神様……? いえ、わたしは筒井という者です」
「嘘つけ。天から降ってきたじゃないか。神様に決まっとる」
女は赤い気炎をあげて踊り始めた。
「あの……」
「なんだ」
「何か勘違いなさってると思うんですが。わたしは人間です。売れない小説家です」
「いいや、神様に違いない。引田部赤猪子だね」
「アカイコ?」
「古事記に書いてある。雄略天皇の目にとまり、空しく召しを待つこと八十年。天皇がこれを憐れみ歌と禄を賜った女だ」
「わたしは男です」
「じゃあ、なんで女の格好しとるん」
筒井は半身を起こして両手で体を触ってみた。頭にすっぽりブルカをかぶり、眼と手以外の全身を一枚の布で覆い隠してある。エジプトにいた時と同じだ! 俺はエジプトから伊勢にやって来たのか! 筒井は女に訊ねた。
「向こうに見える山は何ですか」
「赤石山脈だ」
「え! 長野と山梨の県境の?」
「そうだ。長野と山梨、静岡の三県にまたがって南アルプス国立公園に指定されとる」
「じゃあ、あの高い峰は……?」
「赤石岳だ。静岡と長野にまたがっとる。標高は全国七位だ」
筒井は興奮した。故郷長野は目と鼻の先だ。俺はついに帰ってきたんだ!
2015年12月27日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十二回
突然ものすごい上昇気流が発生し、筒井の体が天高く舞い上がった。右に左に激しく揺さぶられて天に昇りながら筒井は気を失った。
――我に返ってあたりを見ると真っ白である。雪ではない。ひたすら真っ白の空間。真っ暗闇の正反対としか言いようがない。前後左右の方向がまったくわからない。恐怖を覚えて身をすくめる。遠くに人影が見えた。だんだん近づいてくる。男の子だ。年若い、まるで「まんが日本昔ばなし」から抜け出たような青童だった。
「おじさん、遊ぼう」
「ここはどこだ? 君は誰だ?」
「遊ぼう」
「さっきの嵐は何だ?」
「嵐じゃないよ。亜音速流れの気流だよ」
「アオンソク?」
「高速の流体で、流れの速さがその流体中を伝わる音速より遅い流れのことだよ」
「ずいぶん難しいことを知ってるんだな」
「子どもだと思って馬鹿にすると痛い目に遭うよ」
筒井の体を稲妻が貫いた。いや、稲妻かどうかはわからないが、とにかく激しい電流が走って体がビリビリしびれる。いったい何者だ、この小僧は。
「ごめんね。馬鹿にするつもりはなかったんだ」
筒井は謝った。白一色だった世界にぼんやりと緑色の平面が見えてきた。
「あれは何だろう」
「あかだよ」
「アカ?」
「うん。おじさん、あかも知らないの? 千葉や茨城では田んぼのことを『あか』って言うんだ」
「へえ。初耳だなあ」
するとここは関東なのか? 今度は別の色が見えた。赤だ。赤い点が明滅している。
「あそこでチカチカ光ってるのは?」
「信号機に決まってるじゃないか。おじさん、信号も知らないの?」
「いや、知ってるけど……」
筒井は腕をまくってぼりぼり掻いた。垢がぼろぼろ出る。そういえば長いこと風呂に入っていない。
「体を洗いたいんだけど、このへんに風呂はない?」
「あそこに舟があるでしょ?」
「舟?」
言われたほうを目を凝らして見ると、たしかに舟のような物体の影が見える。
「あそこの淦で洗えばいいよ」
「アカって何?」
「舟底にたまった水のことだよ。おじさん、何にも知らないんだね」
「どうやらそうみたいだ」
舟のような物体のほうへ向かって歩き出した途端、固いものが足に当たった。見下ろすと満々と水をたたえた盥である。とりあえず手を洗おうとしゃがんで盥の水に手を入れようとすると「あ、ダメ!」と子どもが大声を上げた。
「それは閼伽だよ! 触っちゃダメ」
「これもアカっていうのか? 何なの?」
「貴賓や仏前に供える水だよ。罰が当たるよ」
またしても強烈な電流が身を貫いた。ここがどこだかまるで見当もつかないが、身勝手に振る舞うとお仕置きされるルールがあるらしい。
「閼伽も知らないなんて、おじさん、いったいどこから来たの?」
「どこからって……説明しにくいんだけど、エジプトのね、カイロっていう町の近くに大きな河があるんだ。そこから……」
「エジプト人なの?」
「いや、日本人だよ」
「日本人のくせに閼伽を知らないなんて変だ」
返す言葉もない。今度は足下でぴょんびょん何かが跳ねる。
「真っ白でよくわからないけど……これは何だろう」
「ウサギじゃないか! ウサギも知らないの?」
「知ってるけど見えないんだよ。真っ白だから」
「ウサギ科は二種類あるんだよ。ムカシウサギ亜科とノウサギ亜科」
「君は物知り博士だね」
「馬鹿にすると承知しないよ!」
またしても電撃に打たれて体がビリビリした。
「お願いがあるんだが……」
「なあに?」
「ビリビリはやめてくれないか」
「いやだよ」
筒井はびくびくしてあたりをキョロキョロ見回すと赤赤とした木の実のようなものが見える。
「あれは……ちょっと待て! 当ててみせる! あれは……あれは、えーと……わかった! 柿だ!」
「当たり」
「でもおかしいぞ。田んぼに水があるのに柿がなってるなんて、季節がバラバラじゃないか」
「季節? ここには季節なんてないよ」
子どもがニヤニヤ笑う。薄気味悪い。いったいこの坊主は何者なんだ?――筒井がしげしげと顔を見ると青童は急に体が大きくなり、黒いロングコートを着た黒人の大男になった。黒いサングラスをかけている。見覚えのある顔だ。
「Welcome to the real world...」
黒人男はニヤリと笑って言った。ローレンス・フィッシュバーンだ! 待てよ。真っ白い空間にローレンス・フィッシュバーン、そして今の台詞……映画『マトリックス』だ! キアヌ・リーブス扮するネオがフィッシュバーン演じるモーフィアスに案内された現実空間――ここはマトリックスだったのか!
2015年12月26日
It Came Upon a Midnight Clear
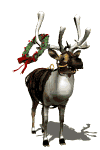 三十数年前からクリスマスに必ず聴くアルバムはフィル・スペクターが制作した『クリスマス・ギフト・フォー・ユー・フロム・フィル・スペクター』、そしてシンガーズ・アンリミテッドの『クリスマス』です。前者はアメリカン・ポップス黄金時代の傑作。後者はア・カペラ多重録音コーラスの金字塔。この二枚があればほかには何も要りません。
三十数年前からクリスマスに必ず聴くアルバムはフィル・スペクターが制作した『クリスマス・ギフト・フォー・ユー・フロム・フィル・スペクター』、そしてシンガーズ・アンリミテッドの『クリスマス』です。前者はアメリカン・ポップス黄金時代の傑作。後者はア・カペラ多重録音コーラスの金字塔。この二枚があればほかには何も要りません。
2015年12月25日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十一回
青ナイルの河口で売子と雑談するうちに筒井は日本がたまらなく恋しくなった。俺は今まで日本のことなら何でも知っていると思っていたが、とんだ思い違いだった。まだまだ知らないことがいっぱいある。思いがけずエジプト人が蒙を啓いてくれた。
外国に来ると自分が日本人であるのをつくづく思い知らされる。いわば祖国の再発見だ。帰国したら――いつになるかわからないが――日本のことをもっと勉強しよう。青山御所を訪ねてみるか。いや待てよ、あそこは赤坂御用地の中だ、一般人はきっと立入り禁止だぞ。芝居を観ようか。最近全然観てないからなあ。青山杉作が創立に加わった俳優座に行こうか。江戸初期の譜代大名青山忠俊の伝記も読みたい。青山胤通とは何者か、恥ずかしながら俺は何にも知らない。うろ覚えだが、伝染病の研究をした人だった気がする。江戸後期の儒学者青山延于ってどんな人だったんですかと人に訊かれたら返答のしようがない。何も知らないんだ。ああ俺は無知だ。無知だということに、いま気づいた。「自分は無知である」ということだけは知っている。――ん? これってソクラテスの「無知の知」ではないか。そうか、ソクラテスも同じ悩みを抱えていたのだ。俺はソクラテスの境地に達したぞ。ソクラテスは偉大なり!
裾の長い青山吹色の民族衣装を来た女が馬を引いて通りかかった。顔はベールで覆い、口に細い枝一本をくわえている。枝の先には青柚というのだろうか、小粒で濃緑色のユズのような実がなっている。川風の煽りに裾がぱたぱたと揺れる。女は横腹を泥よけの障泥で覆った馬を止め、服を脱ぎ捨てて河にじゃぶじゃぶ入り、ざんぶと身を躍らせて煽り足すなわち横泳ぎで対岸に向かって泳ぎだした。すいすいと泳ぐ姿は障泥烏賊を思わせるほど優美だ。ちょうど神明造りの屋根の大棟左右にしつらえた障泥板を流れる雨水のようななめらかさである。オリンピックの競泳に出場したら優勝間違いなしだ。なんなら俺がスカウトしてやろうか。スポンサーも見つけてやる。複数の会社に打診して煽り買いさせてギャラを高騰させよう。女は驚くだろうな。無名だったのに一夜にして世界的な競泳選手になるのだ。まるで劇場の大きな舞台装置が煽り返しでぐるっと回って別の場面に変わるような気分だろう。「オリンピックを目指してトレーニングだ! オーストラリアで最高の訓練を受けさせてやる!」。女を煽り立ててやろう。女は言うだろう。「オーストラリアになんか行けません。うちには病気の両親がいて面倒をみなくてはならないのです。それに我が家は安普請で、強い風が吹くとドアがバタバタうるさいんです。風が吹いても窓や扉が音を立てないように煽り止めの金具を壁につけたい、それだけが夢なんです」。――ちっぽけな夢だなあ。金具なんかホームセンターで買えばいいじゃないか。いっそのこと窓枠とガラスを蝶番で連結させて煽り窓にすれば開け閉めが楽だし風に煽られる心配もなくなる。
女を追いかけよう――筒井は思ったが、岸辺に立ったまま足が動かない。前回の連載で触れた通り筒井は金槌なのだ。女ははるか沖の黒い小さな点になってしまった。悄然として頭を垂れた筒井があらためて顔をもたげると、小さな点がだんだん大きくなった。女は途中から引き返してこちらの岸に戻ってきた。河から上がり服を着た女に声をかけようと筒井がそばに寄ると女は「じろじろ見ないでよ! この変態!」と叫び、そそくさと馬に乗って障泥を打ち、来た道を引き返した。女を出しにして巨万の利益を得ようと目論んでいた筒井は思いも寄らぬ展開の煽りを食ってへなへなとくずおれた。「ちくしょう、一攫千金と思ったのに」。筒井はやけ酒を呷りたい気分だった。川風がジャケットの裾を煽る。
2015年12月25日 Part 1
Have yourself a merry little Christmas
 山下達郎の『クリスマス・イブ』が三十年連続でオリコン週間シングルランキング百位以内に入りました。もちろん前人未踏の偉業です。流行を追わず「いつ作られたのかわからない曲を作るのが理想」とおっしゃる山下さんならでは。クリスマスの曲ばかりを集めたアルバム『Season's Greetings』もお勧めですよ。
山下達郎の『クリスマス・イブ』が三十年連続でオリコン週間シングルランキング百位以内に入りました。もちろん前人未踏の偉業です。流行を追わず「いつ作られたのかわからない曲を作るのが理想」とおっしゃる山下さんならでは。クリスマスの曲ばかりを集めたアルバム『Season's Greetings』もお勧めですよ。
2015年12月24日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三十回
青瓢のような木っ端警官とともに銭形警部が去ってゆくのを確認した筒井はブルカを脱いでほっと息をつき、青脹れした顔の汗を拭った。「見事に追っ払いましたね」店主が感心する。
「まるで土俵の青房方向に送り出したみたいなお手並みでした」
「小説家だと言ったけれど、じつはむかしから俳優をやってましてね」
「そうなんですか」
「ええ。テレビドラマや映画、舞台にいろいろ出演しました」
「これはお見それしました。なにしろエジプトに来て長いものですから。日本のドラマや映画はとんと疎くて」
「まあ道楽みたいなものですよ」
「またまたご謙遜を。警察追っ払い大作戦の成功をお祝いしましょう。ちょうどこれから青柴垣の神事が始まるんです」
「アオフシガキノシンジ?」
「もともと島根県の美保神社で四月七日に行なう神事です。由来は古事記の国譲りの神話だそうで、船のまわりに設けた柴垣を奪い合います。豊漁と航海安全を祈願するんですよ」
「船の祭りか。ここは青ナイルの河口だから場所はうってつけだ。それにしてもエジプトで古事記由来の祭りが見られるとは……」
「日本びいきなんですよ、エジプト人は。天正カルタも大人気」
「天正ガルタなんて今どきの日本人は知らないよ。カードはたしか四種類だね。ハウとイス、オール、それとコップだったかな」
「そうです。ハウは青札です。船には青不動を安置します。京都青蓮院所蔵の不動明王。もちろん本物じゃなくてレプリカですよ。そろそろ始まりますから行きましょう」
店主の青野と筒井はバザールを抜けて河口へ行った。なるほど船が二艘浮かび、勇ましい男たちが芝垣を奪い合っている。なかには船酔いして青反吐をゲロゲロ吐いている者もある。川面に魚がピチピチはねる。求仙というスズキ目の海魚のオスで青倍良と呼ぶそうだ。岸辺に大勢の地元エジプト人が集まってやんやの喝采を送りさんざめく光景は草双紙の一種、青本に描かれる一場面としか思われぬほどだ。筒井の顔のまわりをバッタ目マツムシ科の青松虫が飛び交う。
「青豆いかがっすかー」と売子が見物人に声をかける。江戸時代の京都で夜明けに売り歩いた青豆売そのものだ。青みを帯びた河水はどこまでも透き通って美しい。青み上戸なのだろう、酔いつぶれた見物人が真っ青な顔でぶっ倒れている。波打ち際にはイラクサ科の一年草青みずが川風に揺れる。船は白と紺に塗り分けた青水引のような旗を翻している。青水引は黒水引ともいって凶事に使うのがしきたりだ。筒井は胸騒ぎがした。青ナイルが白ナイルと合流する地点を眺めながら筒井は気を取り直して、「青角髪依網の原に……」と万葉集の歌を口ずさんだ。
合流地点の水は青緑色で、水田に繁茂する水綿を思わせた。「陰暦六月、青水無月には河をさかのぼって泳ぐ水泳大会もあるんですよ」青野が行った。泳ぎを知らない筒井は想像しただけで怖じ気づき顔が青んだが、悟られまいとして仰向きに空を見上げ、「青麦の季節も景色がいいでしょうね」と話題を変えていっそう仰向いた。その姿勢で川岸を歩くと仰向けに寝そべった酔っ払いにけつまずいて尻餅をついた。誰だ、こんなところに仰向けたのは! 邪魔だ! 青虫みたいに踏んづけてやる!――と一瞬思ったが、大人げない気がしてぐっと堪え、収穫したコリヤナギのまだ皮を剥いでいない青芽のような飲んだくれを睨みつけただけで素通りした。
「青豆いかがっすかー」
再び売子がやって来た。顔をよく見るとエジプト人にしては珍しく西洋人のような青眼である。青物を商う行商人なのだろう。あるいは近くに青物市があって青物屋から仕入れるのかも知れない。
「旦那、青豆いかがっすかー」
「豆は要らないよ。ほかに何かないの」
「ありますよ。紅葉の天ぷら」
「え?」
「まだ紅葉してない青紅葉を使ってます」
「驚いたなあ。京都で食べたことはあるけど、エジプトでも食べるの?」
「二三年前から売ってます。日本には青森っていう町があるそうですね」
「うん。町というか都市だけどね。県の名前でもある」
「その青森から来た観光客が教えてくれたんです。天ぷらにするとうまいんだぞって」
「へえ。それはそうと、肩に担いでる木の枝が立派だね」
「これっすか? 青森椴松ですよ。日本ではふつうオオシラビソって呼ぶらしいっすね。マツ科モミ属の常緑樹です」
「エジプトに来たのは初めてだけど、結構日本に似てるんだね」
「日本は行ったことがないのでよくわからないっすけどねー。あ、いま通りかかった人、あれは青屋っすよ」
「アオヤって何?」
「藍染の職人。ここだけの話ですけど、卑しい身分なんですよ。牢屋の掃除とかさせられて」
「被差別民か」
「なんでか知りませんけどね」
筒井は河を眺めた。青やかな波が静かに揺れている。
「あ、魚が跳ねた」
「青矢柄です」
「聞いたことないなあ」
「ヤガラっていう魚の一種ですよ。このあいだも日本人の観光客が、うわあ珍しいって、写真を撮ってました。帰国したらすぐ青焼にするぞって興奮して。意味わかんないっすけど」
「たぶん青写真のことだ」
筒井は眼を閉じた。川風が心地よい。葉の生い茂った青柳の光景がまぶたの裏に浮かんだ。故郷長野の景色だった。思えば遠くへ来たものだ。家の庭の青柳草は枯れていないだろうか。「青柳の葛城山に春風ぞ吹く」。新古今和歌集の歌が口をついて出た。
ドン! 誰かが肩にぶつかり、「なにぼーっと突っ立ってるんだよ!」と怒鳴って去った。
「大丈夫ですか」
「うん。あー、びっくりした」
「青屋大工っすよ」
「青屋って、さっきの?」
「仲間です。牢屋専門の大工。態度悪いんですよ、差別されてるからひねくれてるんです」
「いや、眼をつぶってた僕が悪いんだ。ふるさとの青柳を思い出してた」
「植物っすか?」
「うん。家の裏が草木の茂った青山でね」
「あ、聞いたことありますよ。シブヤの近くでしょ?」
「渋谷の近く? ああ、地名の青山か。よく知ってるね」
「観光客がしゃべってたんです。アオヤマはおしゃれな町だって」
「むかし青山っていう人が住んでいたんだよ。人名が地名になった」
「大学があるとか言ってましたよ」
「そうそう、青山学院大学。それにしてもよく知ってるなあ。君、本当にエジプト人?」
「ちゃきちゃきのエジプト人です」
「その言い回し、江戸っ子としか思えないよ」
2015年12月24日 Part 1
千穐楽
 静岡芸術劇場の『薔薇の花束の秘密』、おかげさまで本日が最終日です。開演は午後二時半。わたくしは稽古を三回見学し本番も三回観ましたが、なんど観ても目頭が熱くなります。「終わってほしくない! このまま永遠に芝居が続けばいいのに」と思うほど。きょうもこれから静岡に向かいます。
静岡芸術劇場の『薔薇の花束の秘密』、おかげさまで本日が最終日です。開演は午後二時半。わたくしは稽古を三回見学し本番も三回観ましたが、なんど観ても目頭が熱くなります。「終わってほしくない! このまま永遠に芝居が続けばいいのに」と思うほど。きょうもこれから静岡に向かいます。
2015年12月23日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十九回
「ツユクサの花を絞った汁で染めた和紙も売ってるんです。青花紙と言いましてね」
「初耳だなあ」
「日本人でも知ってる人は少ないです。水に浸すとすぐ脱色するのが特徴で、友禅の下絵を描くのに使います」
「中庭の入口にかけてある簾も風流だね」
「あれは青葉の簾です。平安時代のもので、陰暦四月一日の更衣の儀の時に内裏の南隅の柳にかけたそうです」
「壁に横笛が飾ってありますね」
「これは青葉の笛。雅楽で使う龍笛の中でも名器として知られる品です」
「売り物ですか」
「いえ、さすがにこれは売りません。客寄せのための看板みたいなものですよ」
中庭から淡い緑色の小さな昆虫が飛んできた。青翅羽衣というカメムシ目の虫だという。簾の下から蛇がにゅっと顔を出し、筒井はぎょっとした。「青波布です。台湾の友人にもらいました。毒蛇ですけど治療は簡単なので、噛まれても大丈夫ですよ」
外にバタバタと人が走る音がする。店主が店先から首を出して様子を窺った。
「警官が五六人、こっちに向かって来ます」
「やばい! 俺を狙ってるんだ」
筒井は血の気が引いて顔が青ばんだ。
「頼む! かくまってくれ!」
「いいですよ。中庭にお隠れなさい。たぶん警官でも下っ端の連中ですよ。中世でいう青葉者ですね。念のため、これをかぶりなさい」
店主は夫人が愛用するブルカを筒井に渡した。筒井はブルカで頭をすっぽり覆い、目だけ出して中庭に逃げた。庭は植物園のような青葉闇で、真っ昼間なのに薄暗い。身を潜めるにはもってこいである。ツチハンミョウ科の甲虫青斑猫が顔のまわりをブンブン飛ぶ。
トレンチコートにソフト帽をかぶった警官が部下らしき男たちを引き連れて店に現れた。ギョロリとした眼に二重顎の警官は身分証を示して店主に言った。
「仕事中に失礼」
「何かご用ですか」
「インターポールの銭形という者だが、ルパンを――いや間違えた、筒井という男を捜しておる。この顔に見覚えはないか」
銭形が人相書きを見せると店主はハッとして息を呑んだ。銭形の眼が鬼火のように輝いた。
「さては見覚えがあるのだな? どこで見た?」
「あ、いえ、存じません……」
「嘘をつくとためにならんぞ。――ん? 奥にいるのは誰だ?」
「え? あ、奥は中庭です。鳥を飼ってるだけです」
「鳥にしては図体が大きいようだが。こいつは怪しい」
銭形は懐から短い竹刀を抜き出して店主の鼻先にちらつかせた。
「誰だ、そこに隠れているのは! 出てこい」
青光りする竹刀を右手でふりかざし、左手で青髯を撫でながら銭形は怒鳴った。騒ぎを聞きつけたバザールの通行人が群がり集まって店先にたちまち青人草ができた。
「わたくしでございますか……?」
アオゲイトウ、別名青莧が生い茂る中庭に身を潜めていた筒井は観念して店に現れ、女のふりをしておずおずと店主の横に立った。世間は筒井康隆といえばただの小説家と思っているが、俺は俳優でもあるのだ。テレビドラマや映画に何度も出たし、むかしは自分の劇団を持っていたくらいだ。蜷川幸雄演出の『かもめ』にも出演した俺様だぞ、女を演じるのは朝飯前だ。――眼と手以外の全身をブルカと衣服で包んだ筒井に銭形は訊ねた。
「失礼ですが、あなたは……」
「妻でございます」
「奥さんでしたか。いや、どうもお騒がせして済みません。筒井という男を捜しておりまして。あそこに停泊している客船をシージャックした容疑者です。こんな顔ですが、見かけませんでしたか」
「上手な人相書きですね……。あらまあ、さっきの人だわ」
「見かけたんですね!」
「ええ、ついさっき。港のほうから猛スピードで走ってきましたよ。なにか大声で叫んでました。『早くしないと国会に間に合わない! 青票を投じなくては!』とかなんとか」
「なんの話です?」
「さあ……。よくは存じませんが、国会で記名投票をする時に反対の意志を表明する青い票のことではないでしょうか。賛成の時は白票を使うと聞いたことがございます」
「しかし……筒井は国会議員でもなんでもないんですよ。シージャックした危険人物です。それだけじゃない。アルプス山麓の町の病院を壊滅させた容疑もあるんです」
銭形は青表紙のノートを取り出し、筒井に関する数々の容疑を読み上げた。ノートは江戸幕府の法度や定書を記した青標紙そっくりだった。
「で、そいつは今どこに?」
「バザールを抜けて西に走っていきましたよ。そういえば何か叫んでました。『やーい、銭形のとっつぁん! 捕まえられるものなら捕まえてみろ! あばよー!』って」
銭形の顔が青瓢箪のように真っ青になり、青びる唇がわなわなと震えた。かと思うと今度は真っ赤になって頭から湯気が昇った。
「間違いない! そいつがルパンだ――いや筒井だ! 西だぞ! 追え!」
警部の鶴の一声で、青服を着た部下たちが一斉に西へ向かって駆け出した。銭形は「ごめん」と挨拶して後を追った。
2015年12月23日 Part 1
あと一日
 静岡芸術劇場の『薔薇の花束の秘密』、あしたが千穐楽です。角替和枝さんと美加理さんの演技バトルをお見逃しなく。
静岡芸術劇場の『薔薇の花束の秘密』、あしたが千穐楽です。角替和枝さんと美加理さんの演技バトルをお見逃しなく。
2015年12月22日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十八回
船は青ナイル河口の港に入った。船長が大勢の乗務員を引き連れてレイチェルの部屋にやって来た。「宮崎に向かう約束じゃないか」筒井が怒鳴ると船長は「あなたをシージャック容疑者としてインターポールに通報しました。もうすぐエジプトの地元警察に引き渡します。神妙にしなさい」と冷酷に告げた。レイチェルがバッグから古銭を出して船長に見せた。「これをあげるから見逃してくれない? 明和五年に鋳造された寛永通宝の青波銭。高く売れるわよ」。所長はかぶりを振った。「この青韋はどう? 藍色に染めた革が美しいでしょう?」。所長は睨んだまま微動だにしない。「じゃあこれをあげる。青二。天明時代のめくりカルタよ。ダメ? 青丹はいかが? 染め物や絵の具に使う岩緑青。とても高価なのよ。お腹はすいてない? 野菜の青みを損なわないように茹でた青煮があるわ。おいしそうでしょう? やっぱりダメ? あ、これは気に入るわよ、青丹打。ほら触ってみて。絹のつやがすばらしい。絹はお嫌い? 麻のほうがよければ青和幣をあげる。青丹衣もあるわよ」
所長は頑として首を縦に振らず、「女性を出しにするとは青二才ですね」と筒井を冷やかした。進退窮まった筒井は窮鼠猫を噛む思いで所長に猛然とタックルをぶちかまし、相手がひるんだ隙に部屋を飛び出て船を駆け下り、右も左もわからないエジプトの港町を盲滅法に走った。
俺はいったい何をしているのだ。日本に帰りたいのにアイルランドからベトナムに連れられ、挙げ句の果てがエジプトである。しかも地元警察に追われる身だ。逃げねば。なんとしても逃げねば――
闇雲に走った先にバザールがあった。通りの両側に小さな商店が櫛比し、買物客や観光客でごった返している。身を隠すにはもってこいだ。筒井は衣料品店の主人が店の奥に気をとられている隙をついて、軒先に吊してあった青鈍色の女性服を奪い、日本を離れて以来着た切り雀だったジャケットを脱いで着替えた。イスラム教徒の女がよく着る、顔と手以外の全身をすっぽり覆う服である。まるで青女房だ。
女に化けた筒井はバザールを歩いた。本屋の店先に日本語で書かれた旅行ガイドのような本があるのが目にとまった。手にとってページをめくる。「青丹よし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり」という和歌が載っている。隣の店は惣菜屋で、魚や野菜を酢味噌で和えた青饅を売っている。その隣は日本でいえば呉服屋だろうか、青く染めた青布子を陳列台に所狭しと並べてある。エジプトなのにどこか宮崎県南西部の青根温泉を思い起こさせる風景だ。本屋をあらためてよく見ると陳列された本はどれも和書で、店先に「AONO」と書いた看板がある。筒井は奥にいる店主に声をかけた。
「ちょっとすみません」
「はい、いらっしゃい」
「あ、やっぱり日本人でしたか」
「ええ。青野と申します」
「わたしは筒井と申す旅の者ですが……じつは困っておりまして」
「どうしました?」
「かくまってほしいのですが」
「何か事情がおありのようですね。立話も何ですから奥へどうぞ」
案内されるまま青暖簾をくぐって店の奥に入った。それまでは人目につかないように伏し目がちだったが、思い切って仰のき店主の目を見つめた。筒井の顔をまじまじと見て男だと気づいた店主は驚いて仰のけざまに足を滑らせて床に倒れ仰のけた。筒井は自分が小説家であること、警察に追われていることをかいつまんで説明した。
「小説家ですか。じつはわたしの祖父は文芸評論家だったんです。青野季吉と言いまして」
「青野季吉? プロレタリア文学の理論家の?」
「おや、ご存じですか」
「文学を志す者なら知らない人はいませんよ」
「祖父の影響でいろんな小説を読みましたよ。とくに菊池寛の『恩讐の彼方に』が好きでして。釈迦に説法ですが、大分県北部に青ノ洞門と呼ばれるトンネルを掘る話です」
「むかし読みました」
「ところでお腹はすいてませんか? おにぎりがありますけど、一つどうです?」
腹ぺこだった筒井は青海苔をまぶした握り飯を食った。見たこともない青羽の鳥が二三羽店先をかすめて飛び去った。店の裏は中庭で青葉が生い茂っている。
「祖父には弟子が三人いたのですが、みんな祖父よりも優秀でしてね。まさに青は藍より出でて藍より青しです。あ、中庭の木には触らないで下さい。小さな虫がいっぱいいるでしょう。青翅蟻形羽隠です。触ると皮膚が赤く腫れますよ」
筒井は店の中にとどまった。右手に持った握り飯に青蝿がたかる。
「青野さんは、ご出身はどちらですか」
「青墓です」
「アオハカ?」
「ご存じないのも無理はありません。岐阜県大垣市の古い宿場町でしてね、平治の乱に敗れて逃れる源義朝が息子の朝長を殺した所です」
「さっきから気になっていたんですが……袴を穿いてますね」
「ああ、これですか。これは襖袴と言いまして、祖父の遺品です。なにしろエジプト人相手の商売ですから、エキゾチックな服装のほうが客受けするんです。エジプト人は日本への関心が高くて、このあいだも仙台を旅行したいから青葉城のガイドブックがほしいというお客さんが来ました」
中庭で鳥が鳴いた。
「青葉梟です。中国人が飼ってたのをもらい受けました。庭には青翅挵りもいますよ。珍しい蝶です。高く売れるんですよ」店主は髭を剃った青肌を撫でて言った。
「しかしいくら日本への関心が高いからといって、和歌の本を買う人がいるんですか」
「いるんですよ、これが。昨日はカイロ大学の学生さんが来て、枕詞の『青旗の』は『木幡』にかかるのはわかるが、なぜ『忍坂の山』と『葛城山』にもかかるのかなんて難しい質問をされて、へどもどしてしまいましたよ」
店主は中庭から青鳩を一羽と、おそらくツユクサであろう青花の束を持ってきた。筒井は青洟を垂らして呆然と見守った。
2015年12月22日 Part 1
ツイートをご紹介
 あさって千穐楽を迎える『薔薇の花束の秘密』。ツイッターでの評判が上々です。いくつかご紹介しましょう。
あさって千穐楽を迎える『薔薇の花束の秘密』。ツイッターでの評判が上々です。いくつかご紹介しましょう。
- 結論から言うとハンカチ持ってって良かった。(^ω^) 泣いてないけどな!(ナカジ@nakajine_s)
- 見てきた! とてもいい舞台でとっても楽しめました♪♪ (Gt.柴田 龍一郎(@Gt_Ryu1130)
- 素直に面白かった。女はこわい。 女優はこわい。 (momoyotateno@momoyotateno)
- 二人芝居。回想シーンでは、別の人物を演じ、その切り換えは素晴らしかったです。話の中にすーっと入り込んで夢中になりました。昔の自分と重なったりと私の心に響く感動の作品でした。静岡芸術劇場の構造はお芝居を観るのに最高でした。(くーたん@renew9393)
- 二人芝居の独特な間と力強さ、雰囲気がガラっと変わる演じ分けが凄い。(ぐれちゃ@greycya03)
- 2人芝居で3時間は凄い…。女たちのキャラクターが立ち過ぎてて、面白かった。エネルギッシュ。(Daisuke Kuraoka@Dachs_P)
- 芸風異なる角替和枝と美加理による二人芝居。主旋律は美加理が合わせ、変奏は同人が主張する印象。異化と他己の塩梅が良い。プイグの戯曲は実に味がある。ラストに掛けて孫への語りはジンときた。(暗愚正傳@ihuppert)
- 帰り道恥ずかしい程むちゃくちゃ死ぬ程ずーっと泣いてしまって目が腫れてしまっとる…。(河村若菜@wakka1228)
- 2時間50分(休憩含)の2人芝居と聞いて身構えたが、少しも退屈しない濃密な時間だった。まずプイグの戯曲がよく出来ているし、小空間向きの作品を大舞台にかけた森新太郎の豪腕も見事。角替和枝も美加理も振幅の大きな内面を見せる。(谷岡健彦@take_hotspur)
いよいよあさってが千穐楽です。
2015年12月21日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十七回
筒井はもう一度青竹を踏みつけた。痛い! 決して広くはない通路を行き交う乗客乗員が「邪魔だなあ」と言いたげに睨む。レイチェルは筒井を自分のキャビンに案内した。部屋の隅に鉢植の木があり、レイチェルが枝を切って水差しに入れると水の色が青く変わった。「あおだもよ。モクセイ科の落葉高木。田んぼの縁に植えて、刈りとった稲をかけて乾かすのに使うの」
筒井は足の裏が痛くてたまらず音を上げた。「情けないわねえ」レイチェルが呆れる。「じゃあ特別ルール。花札で勝負よ。わたしに勝ったら合格」。
二人は花札を始めた。たちまちレイチェルが青短三枚を揃えて勝った。
「話にならないわ」
「頼む、どうか俺をフリーメーソンにしてくれ! お礼に青緂をプレゼントするよ。白と青を交互に配した織物だ」
「持ってるの?」
「いや……でも、必ず手に入れてみせる」
レイチェルは窓を開けた。海風がさっと吹きこみカーテンの煽ちにベッドの枕元から小さな紙切れが吹き飛んで床に落ちた。「本日の清掃は私、青地が担当いたしました」と書いてある。清掃係のメモだった。煽ち風がカーテンをバタバタとはためかす
「手に入れてみせるって、当てはあるの?」
「じつは……ないんだ。むかしから稼いでも稼いでも生活が追いつかない煽ち貧乏でね。毎日飲むお茶も灰汁に一晩つけてから蒸した粗末な青茶さ」
「素寒貧なのね! でも小説家なんでしょう?」
「近頃はさっぱり本が売れなくて。去年の印税は三千円……」
「江戸後期の蘭学者青地林宗が書いた日本初の物理学書『気海観瀾』を長年探してるんだけど、あなたに頼んでも無理ね」
「本なら俺の専門分野だ。古本屋で探してみるよ」
「言っておくけど、ほしいのは原本よ」
「原本は……たぶん国宝級だ」
「だからあなたに頼んでも無駄だって言ったの」
「そんなこと言わないでくれぇぇぇ」
筒井は床に寝そべり手足をたばた煽ち、駄々っ子のようにわめいた。レイチェルは意に介さず、茶碗の上べりに引いてある青い線まで酒を青っ切りについで飲んだ。酒の肴は生の色を失わないように漬けた野菜の青漬である。ほろ酔い気分になったレイチェルはベトナムの植物が好きだと言った。青葛と青葛藤がお気に入りで、葉の色が青々とした青椿の美しさはたとえようがないそうだ。半身を起こした筒井は青っ洟を垂らしている。こんな男をフリーメーソンに勧誘したわたしが馬鹿だった――レイチェルは窓を閉め、クローゼットから紺地に浅葱縞の青手で作ったショールを出して首にまとい、小さな陶器の壺を取りだして筒井に見せた。「青金の粉末を膠に溶いて混ぜた青泥よ。美術工芸品の彩色に使うの。あなたに手が出せる代物ではないわ。貴重品だから価格が青天井なの」
廊下から足音が近づいてドアの向こうでぴたりとやんだ。たぶん石坂だ、あるいは客室係の青木かもしれないと筒井は言った。レイチェルがドアを開けると、青砥というのだろうか、青灰色の砥石を持った男が立っている。
「どなた?」
「突然お邪魔してすみません。青砥と申します。わたしもこの船の客です。本日はすばらしい商品をご紹介しに参りました」
「すばらしい商品って、その砥石のこと?」
「あ、いえ、違います。こちらです」
青砥はもう片方の手を差し出した。青唐辛子だった。
「トウガラシなんかほしくないわ」
「そうですか……わたくしテレビショッピングで売子をやってた者ですが、おまえみたいな青道心じゃ視聴率がとれないってプロデューサーにクビにされてしまいまして……」
「それはお気の毒さま」
「どうか、助けると思って買ってくれませんか。今ならもれなく青蜥蜴を一匹サービスします!」
「要らないわよ、トカゲなんて! あたしがほしいのは、たとえば青土佐よ。土佐名産の和紙。どうせあんたは知らないでしょうけど」
「あいにく存じません」
「青砥稿花紅彩画なら買うわよ。歌舞伎の脚本。鎌倉時代中期の武士青砥藤綱の肖像画も探してるの」
「ふとんクリーナー、レイコップじゃダメですか」
「テレビショッピングには興味がないの! 曲亭馬琴が執筆して葛飾北斎が絵を描いた青砥藤綱模稜案の初版本なら喜んで買ってあげるわよ」
セールスマンはすごすごと引き下がった。レイチェルは茹でた青菜を肴に酒盃をもう一度あけた。
汽笛が鳴り客船がホーチミンの港をゆっくりと離れた。「やったぞ!」筒井は青っ洟をずるっと吸い上げて喜んだ。俺はシージャックに成功した。ついに帰国の途に就いたのだ。ベトナムから日本までは大した距離ではない、一晩眠れば翌朝には宮崎に着くだろう。船は大海原をひたすら進んだ。二日経ち、三日経ち、一週間が過ぎて運河を越えた。あれ? ベトナムから日本に行くのに運河なんてあっただろうか? 運河を抜けると客船は大きな河を遡った。どうも様子がおかしい。筒井はレイチェルの部屋に行き訊ねた。
「まだ日本に着かないのかな」
「日本? なに寝ぼけてるの? ここは青ナイルよ」
「え! 青ナイルって、まさか……」
「ナイル川の支流」
エジプトじゃないか! 俺はてっきり日本に帰れるとばかり思ってたのに。レイチェルは青梨をかじって「早くアイルランドに着かないかなあ」と能天気に呟く。帰国の夢が絶たれた筒井はすっかり気落ちして青菜に塩である。
2015年12月21日
残り二公演
 今月五日に幕を開けた静岡芸術劇場『薔薇の花束の秘密』、残る公演は本日と水曜日の二回です。角替さんと美加理さんの演技はどんどん磨きがかかり、二時間半の芝居はちっとも長さを感じさせません。本日もカーテンコールの拍手が鳴りやみませんでした。さあ、ぜひ静岡へ。あなたの心に薔薇の花束をお届けします。
今月五日に幕を開けた静岡芸術劇場『薔薇の花束の秘密』、残る公演は本日と水曜日の二回です。角替さんと美加理さんの演技はどんどん磨きがかかり、二時間半の芝居はちっとも長さを感じさせません。本日もカーテンコールの拍手が鳴りやみませんでした。さあ、ぜひ静岡へ。あなたの心に薔薇の花束をお届けします。
2015年12月20日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十六回
騒ぎを聞きつけた石坂が船長室に現れた。袷の乱れた襟元から下着の襖子が丸見えで、服さえ着ていれば格好なんてどうでもいいという考えがいかにも青し。両手に抱えた青瓷は床の間から盗んだに違いない。
「筒井さん! 船長を放しなさい」
「うるさい!」
「早まってはいけません。ほら、窓の外には蒿雀が美しい声でさえずっていますよ」
「野鳥には興味がない」
「では青軸を差し上げましょう。梅の栽培品種で、若枝も花軸も緑色なんですよ」
「君は黙っていろ」
「じゃあ青鹿をプレゼントします」
「アオシシ?」
「カモシカです」
「カモシカなんかもらっても飼えるわけないだろ! 俺は日本に帰りたいんだ。そもそも君が乗る船を間違えたからベトナムになんぞ来てしまったんだぞ」
「わかりました。どうにかしますから、とりあえず青紫蘇ドリンクでも飲んで落ちついてください。あ、また青鵐が啼きましたよ」
「アオシトド?」
「アオジですよ」
「だから野鳥には興味がないって言ってるだろ!」
「こうなったら青柴をプレゼントしましょう。葉のついたまま刈った柴です」
「俺は桃太郎の爺さんじゃない!」
「とにかく私が説得します」
筒井は果物ナイフを下ろして船長を放した。石坂は船長に船を日本に向けてくれないかと懇願した。船長は宮崎市南部の青島でよければ寄港してもよいと青縞のシャツの乱れを直しながら答えた。ようやく帰国の青写真が整った筒井はほっとした。副船長たちはシージャックに驚き、繭を作る時期になると体の色が青みを帯びる蚕すなわち青熟のような顔色である。石坂は「あ、またアオジが啼いた」と相変わらず青書生のように暢気で、青白橡すなわち淡い黄緑色のハンカチで額の汗を拭い、テーブルのグラスをつかんで青汁をごくごく飲んだ。時代物の陶器を抱えた石坂の青白い姿はまさに青白きインテリである。
船はなかなか出航しない。「青信号になるのを待ってるんです」船長が説明した。副船長が「まあ、これでもお飲みなさい」と茹でたほうれん草を裏ごしして酢とみりん、砂糖、塩を混ぜた青酢の入ったコップを筒井と石坂に渡した。筒井は酢を飲みながら青々と菅の生えた故郷長野の青菅山の景色を思い出した。コップを握る手をあらためて見ると青筋が浮いている。そういえば最近ろくな物を食ってないからなあ。栄養不足で、このままだと野垂れ死にだ。
「ちょっとあんたたち! 何してるのよ!」
突然黒人の女が船長室に飛びこんできた。胸から腹にかけて大きな青筋鳳蝶をプリントしたシャツを着た女は「いつまで停泊してるつもり? 早くアイルランドに行ってよ」と青筋を立てた。シャツは裾になるほど青色が濃くなる青裾濃で、女は手前の壁にかけてある青簾をつかんで引き下ろし滅茶苦茶に踏んづけて、青墨色の瞳で船長を睨み、「さっさと船を出しなさい!」と怒鳴りつけた。「じつは事情がありましてこれから日本に向かいます」船長が答えると女の顔色が青ずんだ。石坂はいつの間にキャビンに行って戻ってきたのか、床の間にあった青摺の掛軸を小脇に抱えている。陶器と一緒に盗むつもりらしい。筒井は女の顔をまじまじと見て言った。
「レイチェル……?」
「なぜ名前を知ってるの……あら、筒井さん!」
間違いなかった。連載第十回、アルプスの麓の病院が溶岩流に襲われて以来行方不明だったレイチェルだ。
「無事だったのか」
「ええ、おかげさまで」
「今までどこでどうしてたんだ?」
「ホーチミンに来てたの。青摺りの衣を買いに」
「アオズリノコロモ?」
「そうよ。宮廷で祭祀がある時、奉仕の祭官や舞人が着る衣よ。日本人のくせに知らないの?」
「お恥ずかしい。でも君は国際労働機関の職員だろ? なぜそんなものを買うんだ?」
「仕事じゃなくて趣味。今はバカンスなの。ホーチミンには日本の骨董品がたくさんあるのよ。青銭とか。明和五年に作られた真鍮製の寛永通宝よ」
青銭なら知ってますよ、私も探してるんです、と石坂が横から口を挟んだ。筒井は邪魔されたのに腹を立ててグーでパンチし、レイチェルと話を続けた。
「じゃあ、日本の骨董品を海外で安く手に入れているってわけだね」
「そういうこと。カラムシの茎の皮から取り出した青麻という繊維も手に入れたわ。パパへのプレゼントよ。パパ、青底翳なの」
「アオソコヒ?」
「あなた本当に日本人? ものを知らないわねえ。緑内障のことよ」
「そいつは大変だ」
「失明寸前なの。パパはもう青空を拝めない」
レイチェルは船長室の窓からホーチミンの港を見つめた。港の向こうには青田が広がり、農作業で負傷したのか怪我人が一人、長方形の台を竹で吊した箯輿に乗って運ばれてゆく。担ぐ男たちの足下に大きな青大将が鎌首をもたげている。
「あの田んぼ、パパの土地なの」
「え? ベトナムに土地を持ってるのか」
「うん。パパは稲が充分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ青田売りをするの。青田買いする人が必ずいるからいい商売になるのよ」
「お父さんは実業家なのか」
レイチェルは、ここでは話ができないからと筒井の腕をつかみ、船長室を出て通路の薄暗がりに連れ出し小声でそっと囁いた。「誰にも言っちゃダメよ。パパはね……フリーメーソンなの」
フリーメーソン! 世界的規模の秘密結社だ。俺は今まで架空の組織だとばかり思ってたが、実在するとは! レイチェルがさらに囁く。
「パパは余命幾ばくもないから後継者を探してるの。優秀で信頼できる男がいたら青田刈りしたいって。あなた、メンバーにならない?」
筒井はびっくり仰天した。まさかフリーメーソンの勧誘を受けるなんて夢にも思わなかった。
「なれるのか? 俺みたいな男でも?」
「ええ、その気があればね」
「なりたい! いや、なる! 断然なる! で、どうすればいいんだ?」
「じゃあ青竹を踏みなさい」
レイチェルは肩から提げていたバッグから半分に切った短い竹を一本出して床に置いた。
「なんで?」
「しきたりよ。メンバーの候補者はまず青竹踏みをするの。健康かどうかチェックするの」
筒井は片足ずつ交互に青竹を踏んだ。土踏まずがものすごく痛い。思わず悲鳴を上げた。まるで青田差し押えを受けた稲作農家のようなつらさである。
「痛くてとても無理だ。かわりに青畳の上で反復横跳びするから、それで勘弁してくれないか」
「ダメよ! 竹を踏むのがむかしからの決まりなの。しっかりやりなさい!」
筒井はまるで実るべき時期になっても穂が出ない青立ちの稲のようにしゅんとなった。でもどうにかしてフリーメーソンになりたい。青田売買で悠々自適の暮らしを送ってきたらしいレイチェルの父親の後釜になりたい。
2015年12月20日 Part 1
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十五回
二人が船室に戻ると石坂は「中は暑いですね」と扇子で筒井の顔をむやみに煽ぎ立てた。左手に青黄粉の粉を山盛りにしたのを扇ぐものだから筒井の顔は粉まみれになった。「まさに青き宮。皇太子殿下ですね。ははは」石坂が筒井を仰ぎ見て笑う。粉を吸いこんでむせる筒井にお構いなしに「これをご覧なさい」と石坂が壁を指す。客船にしては珍しく小さな床の間があり、年代物らしい壺がある。「江戸後期、京都の陶匠青木木米の青磁です」。目利きの石坂が鑑定する。筒井はきなこの粉が眼に入って見えない。床の間には掛け軸があり、石坂は一読して「浮世草子の作者青木鷺水だ。『青きを踏む』と書いてあるでしょう。萌え出た青草を踏んで野山を歩くことですよ」と蘊蓄を傾ける。掛け軸本体も高価なものだそうで、銀を20パーセントほど含んだ金銀合金の青金をほどこしてあり、石坂は「いい仕事してますねえ」とどこかで聞いたことのあるフレーズを口にして感嘆する。
「どうです? 立派な品でしょう?」しゃがんだ石坂は筒井を仰いで言った。
「どうでもいいけど、きなこを扇ぐのはやめてくれ」
青黄粉だらけになった筒井の顔はまるで青隈を塗った歌舞伎の悪役の公家、青公卿である。石坂は掛け軸に描かれた青草がすばらしい、欲しいなあ、盗んじゃおうかなあ、と青臭いことを言う。
「青草摺という手法ですよ。糊張りの紙に山藍の葉や青色の草で花鳥などの文様を描くんです。絵の具はどこで売ってるんだろう。青草屋かなあ。青朽葉の色づかいがすばらしいなあ」
「いい加減にしろ!」
筒井が怒鳴った。石坂ははっとして青くなった。筒井の顔はおろか部屋中がきなこだらけである。堪忍袋の緒が切れた筒井は石坂の青頸をむんずとつかみ、日本在来種のアヒル、青首鶩のような首根っこを締め上げた。ちょうどその時デッキでは男子十五歳で初めて出漁する者を祝う青首祝が行なわれていたが、部屋で格闘する二人は知る由もない。筒井がぎりぎりと首を絞める。石坂の顔は血の気が引いてまるで青首大根だ。憤怒の塊になった筒井は歌舞伎の悪役や幽霊が塗る隈取、青隈そっくりの顔色である。窓の外には青雲が棚引いている。古事記の一節、「青雲の白肩津に泊てたまひき」はこんな光景を描写したのだろうか。筒井が手を離すと、青黒に染められた袷から突き出た石坂の首に青黒いあざができた。尻餅をついてへたばった石坂は青毛の馬のようにぶるぶる震え、まるで風に揺られる青鶏頭のようだった。
キャビンの外が急に騒々しくなった。筒井がドアを開けて船内の様子を窺うと、乗務員たちが稲を早めに刈りとった青毛取の俵をせっせと運んでいる。窓の外からキョッキョッキョッと小鳥の鳴き声が聞こえる。
「緑啄木鳥だ」石坂が言った。
「アオゲラ? 山にいる鳥じゃないか。もう日本に着いたのかな」
筒井はデッキに出た。海面を見下ろすと全体が緑色の藻、青粉に覆われ、一頭の青駒が犬かき、いや、馬かきしている。青粉をよく見るとそれは青海苔の代用としてよく使う石蓴である。アオサは日本各地の干潮線の岩石に着生する藻だ。ついに日本に帰ってきたのだ! 筒井は小躍りしてデッキの反対側に行った。客船はいつの間にか港に接岸しており、埠頭では大勢の女性がこちらに向かって手を振っている。
「アオザイを着てますね」遅れてデッキに出てきた石坂が言った。
「アオザイ?」
「ええ。ほらご覧なさい。ベトナムの民族衣装ですよ」
本当だ。ここはベトナムじゃないか。船は日本行きのはすだ。石坂はアイルランドを発つ時たしかに「船で日本に帰ります」と言ったぞ。まさかベトナム行きではあるまいな。ベトナムに寄港してから日本に向かうのかな。船長に確かめよう――筒井は船長室に行きドアを開けた。船長はほかの乗務員とテーブルを囲んで青魚を食べている。窓の外を青鷺が一羽ゆうゆうと飛んでゆく。船長は筒井を見て言った。
「やあ、いらっしゃい。どうです、一緒に食事しませんか? ちょうどこれからデザートを食べるところです」
船長は青麦を炒って臼で挽いて糸のようにした青差を載せた皿を見せた。皿の横には銭の穴に紺染めの細い麻縄を通して銭を結び連ねた青緡がある。日本のお土産だろうか。
「お食事中のところ恐縮ですが……この船は日本行きですよね?」筒井は船長に訊ねた。
「青鯖の塩焼もありますよ。召し上がりませんか」
「いえ、結構です。船の目的地を知りたいんです」
「目的地にはもう着きましたよ」
「え!」
筒井は耳を疑った。船長と乗務員たちは顔を見合わせてどっと笑った
「アイルランドとベトナムを結ぶ世界唯一の船ですからね。食事が終わり次第アイルランドに戻りますよ」
冗談じゃない。筒井は逆上してテーブルから果物ナイフを拾い上げ、船長の喉元に突きつけて叫んだ。
「この青侍め! さっさと船を日本に向かわせろ! さもないと青鮫の餌食にしてやるぞ!」
筒井の剣幕に押された船長たちは青ざめた。
2015年12月19日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十四回
日本とヨーロッパを頻繁に往復して亜欧を股にかけて亜鉛や古美術を商う石坂は阿翁すなわち祖父も商売人だったそうで、浮草に似たとても小さな青萍を栽培し、京都府長岡京市にある西山浄土宗の本山粟生光明寺に納入しただけでなく、江戸後期の洋風画家亜欧堂田善の銅版画コレクターとしても有名だったという。祖父の口癖は「視野を広げろ。青海原を越えて世界にはばたけ。青馬に乗って世界を駆け巡れ」だった。
「うちの先祖は白馬の陣に並んだことがあるそうです」
「アオウノウマノジンって何ですか」
「わたしも詳しいことはよく知らないのですが、平安京に建礼門という門があったそうで、その別名らしいです。平安時代には白馬節会という宮中行事があって、正月七日に宮廷の庭に馬を引っぱり出して眺めたんですって。なんでも青い馬を見ると年中の邪気を払うという迷信があったそうです」
「馬が縁起物だとは知らなかった」
「わたしもです。亀のほうがよっぽど縁起がよさそうに思えますけどね。青海亀とか」
石坂は、お一つ召し上がりませんか、と鞄から青梅を取りだした。塩に漬けた青梅漬だ。日本を離れて久しい筒井はアイルランドで梅が食べられるとはありがたいと、遠慮なくむしゃむしゃ食べた。口の中が酸っぱくなって思わず顔をしかめる筒井を見ながら石坂は藍色の青絵が描かれた陶磁器がいかに貴重か、また先ほど述べた葵下坂という名刀は青江下坂とも呼ばれ、備中青江、現在の倉敷で製作された青江物という刀とともにどれほどヨーロッパで人気を集めているかを熱弁した。筒井は梅を食べてしまうと急に食欲が増し、ほかに食べ物はないか訊ねた。「こんなものでよければ」石坂は茹でた青豌豆の入った袋を差し出した。筒井は袋に手を突っこみグリンピースをわしづかみにしてがつがつ食った。豆を頬張りながら「これじゃまるで礼儀を知らない青男だな」と思った。もし女だったら「あの子は年若く世慣れない青女だからね」と、ご愛敬で済むのだが。たらふく食べた筒井は石坂の顔色を窺いながら再び訊ねた。
「じつは日本に帰りたいのだが……あいにく一文無しで、西も東もわからなくて……」
「じゃあご一緒にどうです?」
「ご迷惑ではありませんか」
「いいえ、ちょうどわたしも船で帰国するところです。螺鈿の材料にする青貝を仕入れなくてはならないので」
「それはありがたい!」
「もうすぐ船が出ます。ではそろそろ行きましょうか」
二人は港に向かった。筒井は嬉しさのあまり青蛙のようにピョンピョン跳ねた。思いきり跳ねた拍子に石につまづいて青垣に頭をぶつけた。石坂は鞄の中から折りたたみの青傘を出して広げた。携帯用の日傘だった。古美術商だけあって持物が風流である。
「青貝というのは、どこで獲れるんですか」
「本州から四国、九州にかけて広く分布してますよ。でも一番質の高いのは青ヶ島で獲れるんです。八丈島の南にある火山島です」
「さすがにお詳しいですね」
「むかしは五島列島の青方産が珍重されたんです。でも乱獲されて絶滅してしまいました」
港には大きな客船が停泊していた。船体は青褐色で、かなり古いのだろう、全体に青黴が生えている。大勢の乗客がデッキから青紙と青唐紙のテープを投げ、見送る人に最後の別れを告げる。手すりのそばに青枯らびた鉢植のヤシの木が見える。船員が青刈りの穀物をせっせと船に積んでゆく。おそらく家畜の餌にする青刈り飼料か、あるいは青刈り大豆であろう。青枯れのヤシの木はヘンリー・フォンダとジェームズ・キャグニー、ジャック・レモンが主演した映画『ミスタア・ロバーツ』そっくりだ。依怙地な艦長を演じたキャグニーはヤシの木を後生大事に育てていたっけ。青枯れ色をしているのは青枯れ病のせいだろうか。
筒井は石坂に連れられて二人用の船室に入った。日本人の船員が来て、青菜を茹でてすりまぜた青羹という羊羹を振る舞ってくれた。窓際の隅にミズキ科の常緑低木青木がプランターに植えてある。
「今の男は青木といいましてね。客室係です。よく気が回る人ですよ。この船で働く前は人生に絶望して富士山麓の青木ヶ原で首を吊ったそうです。運よく旅人に発見されて一命をとりとめたと言ってました」
「苦労人なんだな」
「ええ。出身は長野県北部、青木湖の近くだそうです」
「青木という名字を聞いてぱっと思い浮かぶのは青木昆陽だなあ。江戸時代の蘭学者」
「わたしは青木繁です。洋画家の」
「さすがは古美術商だ。もう一人思い出したよ。青木周弼。幕末にオランダの医学を学んだ医者です」
「明治時代の外交官で青木周蔵という人もいましたね。たしか長州藩士だったはず」
ブオオオオと汽笛が鳴って船が出航した。部屋の窓から海を眺めると小舟が数艘、キス科の硬骨魚青鱚を釣っている。筒井と石坂はデッキに出た。頬を撫でる海風は西日本で初秋に吹く青北を思わせた。
2015年12月18日
「一番大事なのは精神的な復興」
「非常時こそ人間らしく行動できる社会、人間であってほしい」。佐々木孝先生のロングインタビュー、本日もリンクを貼っておきます。
2015年12月17日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十三回
「亜鉛のことならおまかせください!」銘仙の袷を着た男が出し抜けに声をかけた。俺の妄想に割りこむとは読心術でも操るのか。「わたくし、こういう者です」と手渡された名刺を見ると肩書は亜鉛研究家、氏名は石坂洋次郎。どこかで聞いたことのある名前だ。「亜鉛のすばらしさを世界中の人に知ってもらいたくて、はるばるアイルランドにやって来ました」石坂は勝手にしゃべりだした。
「亜鉛華をご存じですか」
「知らないよ」
「酸化亜鉛です。白い粉末で、酸にもアルカリにも溶けます。白色顔料や化粧品、医薬品に使います」
「へえ」
「亜鉛華軟膏は亜鉛華とラノリンを混ぜた軟膏で防腐効果があり、皮膚病に効きます」
「ふーん」
「亜鉛鉄板はご存じですよね」
「知らないってば」
「トタンですよ」
「ああ、屋根とかに使う、あれか」
「ええ。亜鉛凸版は写真製版法で作った、亜鉛を版材とする凸版でしてね。亜鉛の板に感光液を塗って、文字や画像のネガを焼きつけて硝酸で腐食させるんです。感光液を塗る板は亜鉛版と言います」
「話の腰を折ってすまないが……私は亜鉛のサプリメントが飲みたいだけなんだ」
石坂の顔が青くなった。よほどばつが悪いのだろう、冷や汗がどっと噴き出て袷の襖にぽたぽた垂れた。顔面はまるで青豆をすってあえた青和えのように青青としている。着物の柄も夏の水辺に茂る青蘆をあしらい、首の後ろにまわした青編笠が青嵐に煽られる姿はまるで白餡にグリンピースの生餡を混ぜた青餡が着物を着て歩いているようだ。石坂は葵を染め抜いた袖で青い額の汗を拭い、芙蓉や銭葵など葵科の草が描かれた袖の中から賀茂祭に用いる髪飾りの葵鬘を取りだし、青息吐息で筒井に恭しく差し出した。なにもそこまで卑下することはないじゃないか。筒井は袖に描かれた葵草と葵座を見ながら石坂に訊ねた。
「石坂洋次郎というお名前は、小説家の……」
「はい。同姓同名です。父が『青い山脈』の大ファンでして」
「そうですか。じつは私も小説家です」
「これはお見それしました。アイルランドへは取材旅行で?」
「いやあ、話せば長くなりますが……和服がお似合いですね」
「ヨーロッパでは着物のほうが目立って商売しやいんです。亜鉛がメインですが、副業として庭石に使う緑色の青石も売ってます。ほかにも秩父青石で作った青石塔婆などを」
「手広く商売をなさってるんですね」
「はい。刀も商ってますよ。越前の刀工康継が制作した葵下坂。慶長年間の作ですから今から五百年以上前のものです。徳川家康のお気に召して葵の紋を切るのを許された品です」
「そんな名品を買う人がアイルランドにいるんですか」
「これがいるんですよ。さすがヨーロッパですね。目利きは大勢います。庭に葵菫を植えたいから苗を売ってくれとか、日本料理に使いたいので青板昆布を仕入れてくれとかいう人もいるくらいで。刀の鍔も葵鍔でなくては買わないとか、結構うるさいんですよ」
「でも商売のし甲斐があるでしょう」
「はい。日本人だろうがアイルランド人だろうがお客様は神様です。お客様の信頼を得るのが商売のコツですね。仰いで天に愧じず、俯して地に愧じず」
「立派な心がけだ」
「このあいだもオランダ人に青糸毛の車はないかって聞かれましてね。むかし皇后や摂政、関白が乗った牛車ですよ。しかも徳川家の葵巴がついた品に限るという難しい注文で」
「物好きだね」
「なんでも芝居に使うんだそうです。『青い鳥』とかいう」
「『青い鳥』はメーテルリンクの童話劇だ。牛車が出てくるとは思えないなあ。ひょっとして能の『葵上』じゃないの?」
「芝居は門外漢なもので……『青い花』だったかも知れません」
「『青い花』はドイツの作家ノヴァーリスの小説ですよ」
「いやはや、お恥ずかしい。舞台の小道具として秋田能代の葵盆も使いたい、京都下鴨神社の葵祭を再現するんだ、とかなんとか言ってました。葵盆は青色だと思ってる人が多いんですが、実際は淡黄色の漆を塗ってあるんです」
「まるで古美術商だ。とても亜鉛の専門家とは思えない」
「自分でも時々何の商売をしてるのかわからなくなることがあります。でも青色申告はちゃんとやってますよ」
2015年12月17日 Part 1
「放射能は実害よりも心理的な害が大きい」
本日もまた十勝毎日新聞の佐々木孝先生ロングインタビューをご紹介します。ぜひご一読を!
2015年12月16日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十二回
「あなたの話は支離滅裂! アウトラインがなってないわ」女が叫んだ。土産物屋の女主人はアイロンがけをやめて再び刺繍にとりかかり、アウトラインステッチをしながら二人の様子を見ている。店の左隣の商店にコンピューターでよく用いるアウトラインフォントでアウトレットストアと書いた大きな看板がある。筒井は大声を張り上げる言語学者を無視して店に入り眼鏡を買った。連載第十二回で眼鏡を壊して以来、ようやく視力を取り戻した筒井が表に出ると言語学者は「このアウトロー!」と言い残して去った。逢うは別れの始めだ。女の捨て台詞が音楽のアウフタクトのように耳に響いた筒井は言語学者との対立をアウフヘーベンしたいと思い、また逢えるかどうか、右足の靴を高く放り投げて占った。表なら逢える、裏なら逢えない――靴はあろうことか横向きに落ちた。合うも不思議合わぬも不思議。納得がゆかない。ならばと筒井は古代の民間占法の一つ、足占に挑戦した。歩きながら一歩ごとに「逢える」「逢えない」と交互に唱え、目標の地点に達した時にどちらを呟くかで吉凶を占うのだ。二歩目で石につまずいて転んでしまった。
再び祭り囃子が聞こえてきた。大勢の男女が円筒形の二本の管を並べた古代ギリシアの笛アウロスを吹き鳴らす。きらめく朝日はローマ神話の曙の女神アウロラが微笑みかけているかのようだ。眼鏡をかけた筒井があらためて港を眺めると一隻の軍艦がある。近づいてよく見るとロシアの巡洋艦アウロラ号ではないか。1917年の十月革命で臨時政府閣僚のたてこもる冬宮を奪取する行動が始まったきっかけを作った軍艦だ。アイルランドで保存されていたとは。ロシア革命によって樹立したソビエト政権は1991年に解体された。何事も始まりがあれば必ず終わりがある。密教でいうなら阿吽だ。ビルマの民族独立運動を指揮した軍人アウンサンも1947年に暗殺された。
筒井が阿吽の二文字を脳裏に描いたその瞬間、まさに阿吽の呼吸で土産物屋の女主人がやって来て「一口召し上がれ」とほうれん草の胡麻和えで饗してくれた。「お言葉に甘えて」と筒井が皿から一口分をつまんで食べようとした時、女主人はなよなよとあえかに体を震わせて突然苦しそうに喘ぎ始めた。何かの発作だろうか。筒井は喘ぐ女を介抱しつつ、三重県上野市にある元国幣中社である敢国神社の祭神、敢国津神に祈りを捧げた。「大丈夫ですか」と声をかけても女は一言もあえしらいしない。あえしらう気力さえ失われたと見える。女は口から真っ赤な血をあえして息絶えた。「誰か来てくれ!」筒井が大声をあげると、女の亭主が店先から取るものも取り敢えず駆けつけ、頓死した妻をかき抱き、死に水の代わりにマグロのぬた和えのような和え作りを口もとに運んでやった。「あなたもお一つどうです」と勧められたが、縁起をかつぐ筒井は敢えて食べなかった。
朝日の透明な光が海に合へ照る。敢え無い最期を遂げた女の死に水を取ってやれないのはつらいが、なにしろ俺はアイルランドの風習に疎いのだ、失礼は承知だが敢へなむ。街路樹の枝に今にもはらはらと落ちてきそうな白い花があえぬがに咲いている。果たして花びらが数枚ひらひらと、糸を通して合へ貫いたかのように連なって落ちた。筒井の眼には死出の旅に出た女の花道に映った。妻の遺骸をかき抱いたままの夫は天を仰いで、ホメロスの叙事詩『イリアス』に登場するトロイアの英雄アエネアスのように慟哭した。長編叙事詩『アエネーイス』を著した古代ローマの詩人ウェルギリウスでさえ、この夫の悲しみを描ききることはできまい。
涙が涸れ果てたのか、夫は妻の亡骸をそっと地面に横たえて筒井に向き直り、アイルランドでは相嘗祭の直後にもう一つ饗の祭という収穫行事があるのですよと教えた。伝説によると石川県奥能登地方の行事だそうで、百年ほど前に饗庭という日本人がアイルランドに渡り、作家饗庭篁村の小説『当世商人気質』を朗読したところ大評判となった。それを記念して毎年祭りが催され、参加者には魚肉に鰹節をまぜ酒や酢にひたした和え交ぜを振る舞うのだという。俺も伝説の男になりたい――筒井は思った。饗庭という男をお手本に、肖者にしたい。大勢の人が和え物で俺をもてなすのだ。アイルランド国民がこぞって俺のために野菜や魚介類に胡麻や酢を和える姿が目に浮かぶ。ご馳走に舌鼓を打つのだ。亜鉛が不足すると味覚が低減するというからサプリメントを飲んでおこう――筒井の妄想はとどまるところを知らない。
2015年12月16日 Part 1
「絆」は切れている
昨日ご紹介した十勝毎日新聞の佐々木孝先生ロングインタビュー、本日もリンクを貼っておきます。
2015年12月15日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十一回
目抜き通りがわいわいがやがやと騒々しくなった。「お祭りだよ」女が言った。「相嘗祭だ。新嘗祭の前に七十一座の神に新米を奉献するのさ」。法被を着た男女が神輿を担いでやって来る。会うのが久しぶりらしい見物人が握手したり肩を叩いたりして再会を喜ぶ。「祭りは人の心と心を合ふ……」女が擬古的な口調で呟いた。「祭りの時はほうれん草と胡麻を和ふのがしきたりだ。かく恋ひば老いづく吾が見けだし敢へむ。ほうれん草の胡麻和えにて汝を饗ふ」。
筒井は法被姿のアイルランド人がわっしょいわっしょいと神輿を担いで通り過ぎるのを呆然と眺めた。なんてアヴァンギャルドな光景だろう! まるで中央アジア出身のイスラム哲学者アヴィセンナがフランス南部ローヌ河口の都市アヴィニョンでサッカーのアウェーゲームに臨むようではないか! いや、もっと正確に譬えるならゾロアスター教の経典アヴェスタを片手にアヴェマリアを唱えてコルドバ出身のイスラム哲学者アヴェロエスを称えつつ、心の底ではイタリアの物理学者アヴォガドロを崇拝して初期キリスト教会最大の思想家アウグスティヌスを罵り、紀元前27年オクタウィアヌスがローマ元老院からアウグストゥスの尊号を受けたのを祝ってドイツ南部バイエルン州の古都アウクスブルクを練り歩くような騒ぎじゃないか。
行き交う群衆のあうさきるさに気をとられた筒井の肩が通りがかりの女にぶつかった。女はあうさわに「アウシュヴィッツへの道はこれですか」と訊ねた。
「アウシュヴィッツ?」
「ええ……あ、間違えました。アウステルリッツです」
「アウステルリッツ……たしかチェコ第二の都市ブルノの近くの町だね」
「はい。学会がありまして、アウストラロピテクスに関する発表を聞きに行く途中なのですが、道に迷ってしまって」
「ほう。ご専門は人類学ですか」
「いえ、言語学です。アウストロアジア語族とアウストロネシア語族の研究をしています」
「道に迷ったとおっしゃるが、ここはアイルランドですよ」
「え!」
言語学者だという女はびっくり仰天した。チェコに行くのにアイルランドで迷子になるとはよっぽどの粗忽者だなと筒井はにやにや笑った。しかし袖すり合うも多生の縁、ここで逢瀬を果たしたのも何かの因縁だろう。立ち話するふたりのそばを、神輿を担いで怪我をしたのか、額から血を流した法被姿の若者が長方形の板を台にして竹で吊した箯輿に横たわって運ばれてゆく。女はアウターのカーディガンを脱ぎ、「自給自足経済を意味するドイツ語のアウタルキーは自足を意味するギリシア語が語源なんです」といきなり言語学の講義を始めた。筒井は気に障って忠告した。
「見ず知らずの人に講釈を垂れるとは失礼だ。野球ならアウトだよ」
「野球? そんなアウトオブデートなスポーツがお好きなの?」
「うん」
「同じスポーツに譬えるならバスケットボールとかバレーボールとかゴルフのアウトオブバウンズだよって言ってほしかったわ」
「野球以外は興味がないんだ。ほら、アウトカウントがあとひとつで試合終了だぞ。君はピッチャー、僕はバッター。アウトコースに投げても無駄だよ。流し打ちが得意なんだ。アウトコーナーはお手の物さ」
「あなたってアウトサイダーなのね。世界の主流はサッカーよ。誰がアウトサイドになんか投げるものですか! アウトドアの人気スポーツはサッカー! だいたい最近の野球場ってどこも室内ドームじゃない。アウトドアライフを楽しめないわ」
なぜか喧嘩に発展してしまった。相手をやりこめる言葉がまるでアウトバーンを疾駆するフォルクスワーゲンのように飛び交う。ふと気がつくと物見高い外野すなわちアウトフィールドの連中が集まってきてふたりを取り囲んでいるようだが、興奮した筒井の眼はアウトフォーカスして群衆の姿はぼんやりとしか見えない。言語学者は脳裏に浮かんだ罵詈雑言を次々に口からアウトプットしながら相手の反応を伺い、筒井も負けじと応戦、喧嘩はアウトボクシングの様相を呈した。売り言葉に買い言葉、まるでアウトライト取引である。
2015年12月15日 Part 1
「ものを考える人間でありたい」
先週11日(金)の十勝毎日新聞に恩師佐々木孝先生のロングインタビューが掲載されました。日本語が読める人全員に読んでいただきたい、充実した長文の取材記事です。先生の許可を得ましたのでPDF版を公開いたします。
佐々木先生は福島第一原発の事故後も南相馬市のご自宅を離れず、いま日本で暮らすわたくしたちにとっていちばん大切なことを「モノディアロゴス」を通じて日夜語り続けていらっしゃいます。ひとりでも多くの皆さまにこの記事を読んでいただければ幸いです。
2015年12月14日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二十回
崩れた山のほうから馬が走って来た。それまで雑談にふけっていた馭者たちが馬上の男を見るや否や、馬車に隠し持っていた槍を一本ずつ手にとり、相槍の戦いに備えて身構えた。やって来た男は馬をとめて大声を発した。
「我こそはエジプトとシリアを領有し十字軍に対抗するアイユーブ朝の始祖、サラディンである!」
全員呆気にとられた。十字軍なんて千年近くむかしの話じゃないか。ぽかんと口を開けたままの筒井たちを見た男は「どうだ、恐れ入ったか」と言わんばかりにふんぞり返って口上を続けた。
「余が愛用する槍を盗んだのは誰だ? 愛欲に溺れるおまえたちの仕業に相違ない。いざ尋常に相撲で勝負せよ! 相四つに組んでも負けるものか。おい、おまえ、相読みになれ。なに? 相読みとは何でございますか、だと? 愚か者め。立会人のことだ。くれぐれも言っておくが相嫁ではないぞ。相嫁は兄弟の妻同士のことだ。向こうで踊っている彼等は何者だ? 余はアイラインを引いてきたぞ。似合うか? 化粧をすると表情が豊かになり喜怒哀楽がはっきりする。誰か鏡を持ってこい! 余の姿は定めし愛らしいであろう。余はこれからリゾート・アイランドへ参る。ギリシア神話の虹の女神アイリスに因んだ地中海の島だ」
なんの話だかチンプンカンプンである。気狂いかな、と筒井は思った。やせ馬にまたがったみすぼらしい男の姿はどう見たってドン・キホーテのパロディーである。すると馬上の男の背景が絞り状に周囲から次第に暗くなり、小さな丸の中に残った男の姿も絞られて闇に消えた。アイリスアウトだ! 黄金時代のハリウッド映画で場面転換に用いたテクニックではないか。筒井は興奮した。数年前アカデミー賞を獲った白黒映画『アーティスト』でもこの技法を使っていたが、よもや現実の世界でお目にかかろうとは――夢かうつつか幻か、筒井は目をこすった。闇の中心に小さな円が現れて周囲が次第に明るくなり馬上の男が再び現れた。
「アイリスインだよ。えへへ」
再登場した男は得意げに言った。言葉にアイリッシュ訛りがある。どこからかアイリッシュハープの調べが聞こえてきた。気狂いのくせにBGMつきで登場するとはこしゃくな奴だ。
馭者たちは槍を置き、さっさと帰り支度を始めた。馬車が次々に街道を去って行く。一台だけ残った馬車に「日本行き」と書いた札が貼ってある。ありがたい! 「乗せてくれないか」と筒井は馭者に言った。
「あいりん行きですけど、構いませんか」
「あいりん?」
「大阪市西成区ですよ」
物騒な街として知られるあいりん地区か。しかし帰国したい一心の筒井は即座に応諾し馬車に乗りこんだ。馭者が馬に鞭を当てると馬車は猛スピードで走り出し、山脈をいくつも越え、大河を渡り、海を越えて島国に着いた。ついに日本に帰ってきたぞ! 筒井は欣喜雀躍した。しかし港町の風景はどうも西洋じみている。行き交う人がみな白人であるのも腑に落ちない。
「ここは日本なのか?」筒井は馭者に訊ねた。
「アイルランドですよ」
「アイルランド?」
「ええ、アイルランド共和国」
「行き先はあいりん地区だと言ったじゃないか」
「言いませんよ。お客さん、耳が遠いね」
往来から聞こえる人々の話し声はたしかにアイルランド語のようだ。筒井は馬車から降りて目抜き通りを歩いた。土産物屋の店先に女主人が揺り椅子に坐って日なたぼっこしながらアイレットワークの刺繍をしている。黒竜江から日本に向かったとばかり思ったのに正反対の地の果てに来てしまった。筒井はがっくりと膝をついた。「どうしたんだい?」女将が哀憐を帯びた口調でやさしく語りかけた。筒井は口を利く元気もない。
「さてはおまえさん、愛恋に破れたんだね。恋人に捨てられた、そうだろう?」
女将は愛憐をこめて慰める。筒井は文色も分かたぬ真の闇に放り出されたも同然だった。
「私は人生の隘路に迷いこんでしまったんです」
筒井の眼から藍蝋を溶かしたような暗い涙がこぼれ落ちた。
「日本を目指してあいろこいろの山越えて辿り着いたのがここだったのです」
「人生にはアイロニーがつきものだよ」
刺繍の手を休めてアイロンがけを始めた女は筒井の哀話に心動かされたのだろう、ふたりはしばらく相和して睦まじく語り合った。女は筒井の眼をまっすぐ見つめて諭すように言った。
「なんでも自分の思いどおりに行くと思ったら大間違いだよ。アインシュタインだってそうだ。アインシュタイン宇宙を知ってるかい? 1917年に一般相対性理論の重力方程式から導いた宇宙モデルだよ。物質の分布が一様で空間曲率が正の閉じた静的宇宙さ。ところが実際の宇宙は動的だから、このモデルとは合致しないんだ。アインシュタインは落ちこんだよ。でも原子番号99、超ウラン元素のひとつが彼の名前に因んでアインスタイニウムと命名されて面目をほどこしたのさ」
二十世紀最高の知性であるユダヤ人物理学者の知られざる苦労話を聞かされた筒井はアインフュールングすなわち感情移入した。
2015年12月14日 Part 1
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十九回
息を吹き返した馭者は「へえ、よござんす」と蚊の鳴くような声で相返答し、息も絶え絶えの仲間たちを見渡すと哀慕と愛慕の念が同時に胸にこみあげた。一命をとりとめた馭者の相棒が絵の具に用いる藍棒をおずおずと筒井に差し出し、今回の勝負は相星というわけにはまいりません、負けを認めますのでどうかお納めくださいと慈悲を乞うた。
突然大地が鳴動した。驚いたヤギの群が悲鳴をあげて逃げ惑う。「地震だ!」馭者が叫ぶ。「1975年から83年までアメリカと日本、フランス、西ドイツ、イギリス、ソ連が参加して行なった国際深海掘削計画をIPODと呼ぶんですが、調査の結果、海洋底が拡大するのが明らかになりプレートテクトニクスが確立したのです!」馭者はまるで百科事典を朗読するみたいに説明した。
アイボリー色の群雲がにわかにたちこめ、街道に放置されていたクレーン車が倒れてクレーン上部のアイボルトが馬車を直撃した。中にいた乗客の男女が直前に運よく飛び降り、九死に一生を得た二人は相惚れの恋人同士なのだろう、ひしと抱き合い、互いに無事であるのを祝って能狂言の相舞を踊り始めた。とはいえなにしろ中国人だ、誰に教わったのか知らないが足の運びや手の所作がどうも曖昧で、能なのか狂言なのか曖昧模糊とするばかりである。女は踊りながら「ねえ、ちょいとお兄さん、あたしたち近くの町で曖昧屋を営んでるんだけど、寄ってかない? いい子いるわよ」と筒井に言った。大地震のさなかでも売春宿の客引きをするとはさすが中国人だと筒井が妙に感心すると女は「あたしたち祖父母が同じ相孫なのよ。仕事の合間小間を見つけては狂言を習ってるの」と一方的にまくしたてる。人生の裏街道を生きる女は下手くそな舞いと貧相な身なりが相俟って哀れを誘う。
大地の揺れがおさまった。筒井は身の上話の合間を縫って馭者たちの様子を窺った。濃淡の藍染め糸二種を用いた藍微塵の縞柄の着物を着た馭者たちは体中の埃をはたき落としながら相身互いに助け合って立ち上がった。山が崩れ街道が寸断された眺めは広島生まれの洋画家でシュールレアリスムと東洋画を折衷した靉光の風景画を思わせた。復旧には莫大な資金が要るだろう。中国政府は今ごろ復興予算の相見積りの最中に違いない。
倒壊した一軒家の裏手、ヤギを放牧していた畑の中央に小さな池があり、藍みどろと呼ばれる揺藻がゆらゆらとうごめいている。池の水は茶と藍を混ぜたような藍海松茶色に濁って地震のすさまじさを物語り、筒井は哀憫の情に打たれた。十数台の馬車から乗客が次々と出てきた。相婿らしき男がふたり手に手をとって無事を喜び、うちひとりが米国ベル・アンド・ハウエル社製の携帯用35ミリ撮影機アイモであたりの惨状を撮影する。曖昧屋の女将は相も変らず怪しげな狂言を踊り、いつの間にか踊りをやめた女衒の男は女と相持ちして使っているらしい弁当箱から塩で処理した干魚の相物を出して食べ始めた。たぶん売春宿の近くに塩魚や干魚を扱う問屋の相物座があるのだろう。孫同士だと言うふたりはお揃いの古びた合紋の羽織を着ており、藍屋で染めてもらったんですよと男が言った。
「あいや、そこの御仁」筒井の背後から男が声をかけた。「うちの店で働いている相役ですよ」と女衒が紹介した。売春宿で雑務をこなすかたわら、農民が栽培する藍に課した税金である藍役の取立ても行なう小役人だと言う。「役人は実入りがいいんですよ。自分と妻の両親ともども、つまり相舅同士でやっぱり小役人をやってましてね。一度やったらやめられません」男は下卑た笑いを浮かべ、近くに旅籠があるので一緒に泊まりませんか、と筒井を誘った。小賢しい木っ端役人と相宿なんて真っ平御免だ、ちょっと気を許せば「一緒に我が家に住みませんか」と相宿りを勧められかねない。女将がおぼつかない足取りで再び踊り、男は「あんよは上手、あいやのほろほろ」と冷やかした。
2015年12月13日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十八回
座席は四人がけで乗客は筒井ひとりだった。空席に本が一冊、表紙に『インドへの道』と書いてある。映画化されたエドワード・モーガン・フォースターの小説だろうか。馭者に訊ねると、仲間と相版で出版したインド旅行ガイドだという。指で寸法をはかると縦が約21センチ、横が約15センチで、週刊誌より一回り小さい合判サイズだ。
前方から一台の馬車が来てすれ違い、馭者同士が片手を上げて挨拶を交わした。「一緒に宿場町で客待ちの相番をする仲間ですよ」馭者が説明した。
「ところで、インドまでの運賃はいくら?」筒井が訊ねた。
「八億四千万ドルです」
「八億四千万ドル? そんな法外な値段があるものか」
「払えないって言うんですか? なら片目をくり抜いてアイバンクに登録しなさい。いやでも金を作ってもらいますぜ」
馭者は馬車を停め、それまで柔和だった表情が鬼のような形相に変わった。相反するふたりが睨み合う。馭者はまだ食事を済ませていなかったのか、ふいに馬車を降り、道路沿いの一軒家から火をもらって煮炊きを始めた。家は忌中らしく鯨幕で覆われている。喪中の家の火を使うのは合火といって昔から禁忌じゃないか。今回の旅は縁起の悪いことばかりだ。筒井はアイビーの絡まる家の門をくぐって扉を叩いた。
「どなた?」主婦らしき女が不機嫌そうに顔を出した。
「藪から棒ですみません。旅の者ですが、この辺で馬車を雇えるところはありませんか」
「馬車? そこにあるじゃないか」
「ええ、今乗ってきたんですが、ちょっと事情がありまして、別の馬車にしたいんです」
「今どき馬車とは珍しいね。いいよ。まあお入りなさい」
筒井が家に入ると居間の壁にノートパソコンがある。
「ネットで予約できるけど、本当に馬車でいいのかい? タクシーとかじゃなくて?」
「ネット?」
「なんだい、おまえさん、ネットも知らないのかい? アメリカ国防総省が開発したインターネット・プロトコル、IPで世界中にパケット交換式でデータを転送できるんだよ。今もちょうどIPRのホームページを見てたところだ。太平洋問題調査会だよ。さっきはIBRD、国際復興開発銀行のサイトをチェックした」
半信半疑で筒井がパソコンを見ると十年くらい前のIBM製 ThinkPad だ。女がキーボードをカタカタ打つとブラウザにアメリカのアイビーカレッジのウェブサイトが表示された。新校舎の建設現場だろうか、アイビースタイルの学生たちが肩にI形鋼、いわゆるアイビームを担いでにこやかに笑っている。合衆国東部の名門私立大学アイビーリーグに所属するだけあって、金には不自由しないと見える。
「妙なことを伺いますが……今は十九世紀ではありませんか?」
「なにを寝ぼけたこと言ってるの? あんた、どこから来たの?」
「じつは二十一世紀の日本から十九世紀の中国にタイムスリップしたんです」
「十九世紀にネットなんてあるわけないじゃないか! 夢でも見たんだね。まあ、そこにお坐り」
筒井が食卓に腰を下ろすとドイツの作家アイヒェンドルフの小説『のらくら者の生活から』から抜け出したような純朴な女は台所から大きな皿を持ってきて、牛肉と豚肉の合挽きで作ったハンバーグのような料理を振る舞ってくれた。女と一緒に舌鼓を打ちながら筒井はまるで愛人と密かに相引しているような錯覚にとらわれた。嘘みたいだが、俺はどうやら二十一世紀の世界に戻ったのだ。いったいいつどこでタイムスリップしたのだろう?
「おまえさん、日本から来たと言ったね」
「ええ」
「じゃあ二葉亭四迷の『あひゞき』を知ってるかい?」
「あいびき?」
「うん。ツルゲーネフの短篇集『猟人日記』の一編を翻訳した小説だよ」
「よくご存じですね」
「中国人を馬鹿にするもんじゃないよ! 今や日本を抜いて世界第二位の経済大国だ」
女は寝室から日本製の鎧を持ち出し、右脇の引合の緒である相引の緒を自慢げに指先でひらひらと回した。中国の寒村でたまたま出会った女と日本の文学や武具について語らううちに筒井は国籍も性別も越えて女と相等しい関係が成立したのを感じた。女は書棚から第二次世界大戦中に行なわれたナチス・ドイツのユダヤ人大量虐殺の責任者アイヒマンの伝記を取りだして食卓に広げ、膝に乗せた愛猫をやさしく撫でながら、犬のように殺された無辜のユダヤ人たちを哀憫した。
話に耳を傾けていた筒井がズボンのポケットに手を入れると紙切れが一枚ある。旅館を出発した時、馭者に荷物を預けた。あの時の合符だ。そういえば外に馬車を待たせたままである。猫を愛撫する女に「ちょっと失礼」と黙礼して席を立った筒井は玄関に向かって歩ぶ。
通りのほうからがやがやと人声がする。玄関から外に出ると門前に馬車がざっと数えて十四五台、それぞれの馭者らしき男たちが何やら鳩首協議中で、ひとりが「あいつだ! 無賃乗車!」と筒井を指さしたのを合図に十数人の男たちはアメリカンフットボールのアイフォーメーションの攻撃体形をとったが早いか門にタックルして木っ端微塵にし、筒井めがけて突進した。筒井は咄嗟の判断で家の周囲をぐるりと回って命からがら裏庭へ逃げながら、無賃乗車だなんて人聞きが悪い、まだ目的地のインドに着いていないじゃないか、痛くもない腹を探られるのは理不尽だ、こっちから合奉行に訴訟を起こしてやるぞと独り言を呟き、春と秋に着る間服の袖をまくりあげてポケットから先刻の合符を出してヒラヒラさせながら「荷物の合札ならちゃんとここにあるぞ」と追っ手のほうを振り向いた。馭者たちは猛牛の群れのように家に体当たりし、安普請の家屋は一瞬で瓦礫の山と化した。女は圧死されたに違いない。必死に逃げる筒井の額から汗が滴り落ちアイブローを濡らす。親切な女とこんな形で哀別することになろうとは、まるで恋人と愛別するかのようなつらさである。裏庭には女が飼っていたのだろう、野生ヤギのアイベックスが群れてのんびり草を食んでいたが、馭者の一団が迫って来たのを見た途端にさっと編隊を組んで構え、弓なりになった長い角を前にぐいと押し出して走り出し、馭者たちに真正面からぶつかって蹴散らした。愛別離苦の悲しみにひたっていた筒井はインド行き直行便の馭者が大の字になって倒れているのを見つけ出し、「思い知ったか! 命は助けてやる。その代わり今すぐ宿を手配しろ。相部屋でも構わん」と怒鳴りつけ、地面に落ちていた裁縫用の合箆を拾い上げて馭者の鼻面にぐいぐいと押しつけた。
2015年12月12日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十七回
「助かった!」筒井は再び小説の世界に戻れたことをドクロベエに感謝し、あたりを眺め渡した。滔々と流れる黒竜江はまるで故郷のように懐かしく目に映る。行き交う人々の前時代的な服装と自動車が一台も見当たらないところから察するに、やはり十九世紀後半の中国に戻ったらしい。こんな鄙びた町に妻と愛の巣を営めたらどんなに幸せだろう。のんびり畑を耕して暮らし、農作業の間の遊びには河川の跡地を水田にした相の田の稲穂を眺めるのだ。畑の向こうに聳える三千メートル級の山は山梨県西端、白根三山の間ノ岳に似ているねと妻に問えば、本当ね、と相の鎚を打ってくれるだろう。
川と山に挟まれた港町は旧東海道の宿場町間の土山に地形が似ており、筒井は思わず有名な馬子唄の一節、「坂は照る照る、鈴鹿は曇る、間の土山雨が降る」を口ずさんだ。「あ、こりゃこりゃ」と背後で間の手を打つ者がいる。振り返ると印半纏を来た腰の低い男が「お泊まりではございませんか」と声をかける。宿の客引きだ。どこかで休憩したいと思っていたところだったので、筒井は案内されるまま小さな旅館に入った。
あてがわれた部屋は畳の大きさが京間と田舎間のちょうど中間にあたる間の間で、座卓には間の物と言うのであろうか、ふつうの酒盃より少し大きめの土器がひとつ置いてある。こんな盃をむかし三重県伊勢市、内宮と外宮のあいだに広がる間の山の骨董屋で見たことがあった。店主はいかにも伊勢の人らしく、三味線を弾きながら間の山節を歌って聴かせてくれたっけ。骨董屋からの帰りはほかの客とタクシーに相乗りしたなあ。どこの誰だか知らないが、旅先では人と人との間柄すなわち合端なんて関係ない。ああ、日本に帰りたい――
筒井は軒先から庭を眺めた。まわりは石垣で、石と石との接合部の合端に苔がむしている。石垣の切れ目に棒杭が立ち、宿の主人の愛馬らしき馬が一頭繋いである。筒井は主人を部屋に呼んで、二十一世紀の日本に帰りたいのだが何かよい知恵はないものかと訊ねた。
「それならアイバクにお願いするのがいいですよ」
「アイバク? 聞いたことがないが」
「クトゥブッディーン・アイバク。ご存じありませんか? インド奴隷王朝の始祖ですよ。奴隷身分出身の武将で、十三世紀の初め頃デリーを都として王朝を立てたんです。タイムスリップしたい人はみんなアイバクに祈りを捧げるんです」
「ぜひタイムスリップしたい! で、どうすればいいんだ?」
「インドにお行きなさい」
「インド?」
「もちろんですよ。アイバクのお墓があるんです。墓前で祈りを捧げればどんな時代のどこへでも行けますよ」
「インドか……遠いなあ」
「遠いったって地続きですから。のんびり旅をなさるがいいですよ」
耳寄りな話である。筒井はインドに向かうことにした。さっそく鹿島立ち、といきたいところだったが、腹が減っては戦はできぬ、長旅の前に腹ごしらえしておこうと宿の食堂に入った。中は宿泊客でごった返し、なんとか空席を見つけて坐り、眼の前の皿の水餃子を箸でつまみ上げるとその皿は隣の人のもので、縁起でもなくうっかり相挟みしてしまった。どうも幸先が悪い。給仕の女が三人おり、うち二人は妊婦だ。一家に二人以上の妊婦がいるのを古来相孕みと呼び、勝ち負けを生ずるといって昔から忌み嫌われる。先が思いやられる。食べ終わると主人がやって来て、「インド行きの馬車が出ますよ」と言う。黒竜江沿岸からインドへ直行する馬車があるとは!
「本当に馬車でインドに行けるのか」
「もちろんですよ」
宿の前に馬車が一台停まっている。主人は間違いなく筒井をインドに送り届ける証文に合判を押して馭者に手渡した。筒井が乗りこむと馭者は「次はインド、インド」と声を張り上げ、馬車はガタゴト走り出した。
2015年12月11日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十六回
「おい、筒井」
どこからか野太い声がする。
「だ、誰だ?」
「わしはドクロベエだべえ」
「ドクロベエ……あ、『ヤッターマン』の……?」
「おまえはヘマをやらかしたべえ」
「ヘマ? なんの話です?」
「おまえは広辞苑小説『言葉におぼれて』の主人公だべえ」
「そうですよ。だから今まで頑張って冒険を続けてきたんです。やるべきことはちゃんとやってきました」
「連載第十三回を思い出せ」
「第十三回?」
「デ=アミーチスの小説『クオレ』のエピソードだべえ」
「ああ、はい、ありましたね」
「邦訳の『愛の学校』は陳腐だ、とおまえは言ったべえ」
「言ったかなあ、どうだったかなあ――あ、思い出した。言いましたよ」
「問題はその次だべえ。『小説なんて能の曲中でほんの座興に見せる間の狂言に過ぎないよ』と、心の中で呟いたべえ」
「ええ、それははっきり覚えてます」
「おまえは広辞苑を持っておるか」
「持ってますよ」
「書籍版か、それとも電子辞書か」
「電子辞書です。カシオの EX-word XD-H7500 に入ってる第五版。便利ですよ」
「ならばもう一度間の狂言を引いてみるがいいべえ」
「……引きましたよ。ちゃんと載ってます」
「次の項目を見ろ」
「えーと……間の楔です」
「そのとおり。ところがおまえは第十三回で間の狂言の次に、愛郷塾という言葉を口にしたのだべえ」
「え? 本当ですか? ぜんぜん気づきませんでした」
「事の次第を説明してやるべえ。カシオの電子辞書版『広辞苑』第五版で間の狂言を引くと、最初の語釈に『→「あいきょうげん」と同じ』と書いてあるべえ」
「あ、はい、書いてありますね」
「作者は矢印を選択してスーパージャンプのボタンを押し、間狂言の語釈を確認したんだべえ」
「意味を調べたわけですね。それがどうかしたんですか」
「意味を調べるのは構わん。だが調べ終わったらスーパージャンプする前の言葉に戻って続きを書かねばならぬべえ。なのに作者はぼんくらで、間の狂言に戻るのを忘れて、ジャンプした先の間狂言から後を続けて書いてしまったのだべえ」
「え! てことは、『あいの』で始まる言葉がまだまだあるのに、突然『あいき』で始まる言葉に繋げちゃったってことか」
「そのとおりだべえ」
「じゃあ、第十三回後半以降の俺の冒険は……?」
「無意味だべえ」
「そんな……。でも俺はただの登場人物に過ぎない。ヘマをやらかしたのは作者だ。文句を言うなら作者に言ってくれ」
「このアカポンタン! 作者が間違えた時は、主人公であるおまえがちゃんと物語を進めるもんだべえ! おまえの存在価値は失われたべえ。この世界から追放するだべえ。おしおきだべえ!」
「ごめんなさい! どうか、どうかお赦しを!」
「ふむ……では特別措置を講じてやるべえ。小説の主人公としての責任をしっかり自覚して、今度こそ間の楔という言葉を使って冒険を続けるのだべえ。そうすれば命だけは助けてやるべえ」
「ありがとうございます!」
黒竜江の波打ち際に筒井の体が打ちあげられた。近隣の人々が集まり、水死体か、それとも気を失っているだけか、ぐったりして動かない体を材木の切れ端で突いて反応を伺う。材木には間の楔が打ってあり、眉間に楔が刺さった筒井は思わず「Ouch!」と大声を出した。
「生きてるぞ! 英語を話した」
「顔つきは東洋人だが、さては西洋人との合の子だな」
人々は土左衛門同然の重たい筒井の体をどっこらしょと持ち上げ、和洋折衷の間の子船に乗せた。意識を取り戻した筒井に、腹が減っただろう、ほれ、食べなさいと白米にチリコンカンを添えた間の子弁当を振る舞うと、筒井は腹をすかせたオオカミのようにむさぼり食い、船は江戸時代に正規の宿駅のあいだに設けられた旅人休息用の間宿のような港町に接岸した。
2015年12月10日
薔薇の花束をあなたに
 12月5日に初日を迎えた静岡芸術劇場の『薔薇の花束の秘密』、すばらしい出来映えです。角替和枝さんと美加理さんの演技は言うまでもなく、演出、美術、衣裳、照明、音響のいずれも非の打ち所がありません。休憩を入れて二時間五十分もある長い二人芝居ですが、ダレ場が一切なく、片時たりとも舞台から目が離せない。とりわけ照明と音響のすばらしさは筆舌に尽くしがたい。
12月5日に初日を迎えた静岡芸術劇場の『薔薇の花束の秘密』、すばらしい出来映えです。角替和枝さんと美加理さんの演技は言うまでもなく、演出、美術、衣裳、照明、音響のいずれも非の打ち所がありません。休憩を入れて二時間五十分もある長い二人芝居ですが、ダレ場が一切なく、片時たりとも舞台から目が離せない。とりわけ照明と音響のすばらしさは筆舌に尽くしがたい。
首都圏を中心に長年日本中の芝居を観まくってはレポートをネットで公開なさる「みけねこ」さんが初日のレポートをさっそく書いてくださいました。終演後に行なわれた中井美穂さんと森新太郎さん(演出家)、宮城聰さん(芸術監督)によるアフタートークの内容も手際よく紹介してくださり、一読すればどれほど見事な舞台であるかが一目瞭然です。
2015年12月8日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十五回
望郷の念にかられた筒井は長野に、いや、せめて日本に帰りたいと強く願った。これが愛国心というものなのか。俺は今まで日本という国を愛したことはない。どちらかといえばコスモポリタンだった。親族には右翼思想にかぶれた叔父がいて、日本初の政党は板垣退助が結成した愛国公党だ、ただし勢力は限定的で、正真正銘日本で最初の全国的な政党といえるものは明治8年の愛国社だぞ、男だけじゃない、女だって義和団事件を契機に明治34年に奥村五百子が愛国婦人会を結成したのだ、おい康隆、人の話はちゃんと聞け、おまえは左翼の連中とつき合っているようだが、正しい日本の歴史を勉強しなくちゃダメだぞと、会うたびに説教されてうんざりしたものだ。
遠くの川岸から、よいしょ、よいしょ、とかけ声をかけて大きな輿を担いだ男たちがやって来た。乗客はふたり、相輿で何やらひそひそと相言を交わしている。「山」。アショーカ王が呟く。「川」。ふたりが答える。合言葉を確認した王は、よろしい、気をつけて行くのじゃぞ、と通行を許可し、ふたりは川岸をそのまま下流へと向かった。
「いまのは誰ですか」
「わしの臣下や。最近は物騒な世の中でアカンわ。あの阿育王山には貴重な仏像があるが、異教の原理主義者が偶像を破壊するんや。西洋の言葉でいえばアイコノクラズムやな」
「見せてもらえませんか」
「アカン。このあいだもズウォルキンとかいう男が来よってな、なんでもロシア生まれのアメリカの電気技術者ちゅう話やったが、撮影させてくれ、世界初の実用的テレビジョン撮像管アイコノスコープの被写体にしたいとか抜かして、気は進まなんだが、まあよろしい、ほな撮影しなさいと許可したら、こいつがまた原理主義者や。仏像を滅茶滅茶にしよった。それ以来、部外者は立入禁止や」
ダメだと言われると余計見たくなる。筒井は何らやましいところがないのを証明するため、説経浄瑠璃の愛護の若の一場面を歌って聞かせ、ご機嫌を窺った。アショーカ王は首を縦に振らない。では将棋をさしましょう、陛下が必ず勝てるように私は間駒を自らに禁じます、いつでも王手できますよ、とおもねっても王は首を横に振る。
「じゃあパソコンの使い方をお教えします、アイコンをクリックしなくてもキーボードを叩くだけでソフトが起動するようにカスタマイズしてさしあげます」
「パソコンは嫌いやねん! スマホしかよう使わん」
けんもほろろである。せっかく19世紀の黒竜江にタイムスリップして眼の前の山には貴重な仏像を退蔵する寺院があるというのに拝めないとは蛇の生殺しだ。川にはカモ目カモ科のアイサが群をなして浮かび、頭を水中にもぐらせて水草を食いながら、まるで筒井をあざ笑うかのように尻をぶるぶる左右に振る。
「あいさ、あいさ」と、またしても神楽の囃子詞のようなかけ声がして、輿に乗った女性がふたり近づいてきた。どことなく芝居がかって、能舞台の橋がかりが後座に接続する部分の奥まった位置にある間座から登場したような風情である。「わしの嫁さんと娘や」。アショーカ王は愛妻と少女を筒井に紹介した。かわいらしい娘は十二三歳くらいの愛盛りで、川に沿って広がる畑の畝と畝のあいだに間作して植えた野菜の育ち具合を母親と一緒に見に来たのだという。「あなたもお乗りなさい」と王妃が輿をポンポンと叩いて筒井を誘う。やんごとなき王妃と相座敷なんて滅相もない。「畏れ多い話でございます」と筒井が遠慮して挨拶すると、「そなたは私に反抗するのですか。挨拶切るつもりならそれで結構。鮫に食われるがいい!」。王妃が叫ぶと同時に黒竜江の水面がざわざわと波立ち、ツノザメ目ツノザメ科アイザメ属の藍鮫が群れをなしてもんどり打って暴れ回り、筒井に向かって巨大な歯を剝きだしにする。逃げ腰になった筒井に王妃が言った。
「そなたは何者だ」
「あ、あの、えーと……会沢という者です」
筒井は咄嗟に嘘をついた。
「あいざわ? するとそなたは昭和10年、陸軍省内で統制派の軍務局長永田鉄山を斬殺した相沢事件の犯人、相沢三郎中佐の末裔であるか」
「いえ、おなじアイザワでも字が違います。アイザワサブロウのアイは『相』、私の名字は『会』です。江戸後期の儒学者会沢正志斎の子孫です」
「原理主義者ではないのだな」
「とんでもない!」
ならばよろしい、と王妃がパンパンと手を打つと川上から近世大阪の淀川筋で使われた間三そっくりの船がするするとやって来て岸辺に着いた。
「誤解が解けたのを御祝して愛餐を催して進ぜよう」
「アイサンと申しますと……ひょっとしてキリスト教の……」
「さよう。初期キリスト教徒の兄弟愛を示す会食です」
「でも陛下は、仏教を庇護したアショーカ王のお后では?」
「仏教は寛大です。キリスト教徒がほかの宗教を信ずることは禁じられていますが、仏教徒は同時にキリスト教徒であっても矛盾しないのです。さあおまえたち、会沢さんを船にご案内しなさい」
王妃に命じられた男たちはそれまで担いでいた輿を下ろし、仕事仲間の相仕である船頭と協力して筒井を船に乗せ、続いて王妃と娘も乗船した。王妃は輿から下りた時に着物の裾に埃がついたのを間紙でそっとはたいた。船は黒竜江を下り始めた。ほどなくして船底がぼろぼろ崩れ、船体がぶくぶくと沈む。泥船だ! 船は見る見るうちに川底に沈み、筒井は水を飲んで気を失った。
2015年12月9日 Part 1
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十四回
作者に毒づいた筒井の視界に何やらぼんやりと白いものが浮かびだした。せせらぎが聞こえる。川か。ひょっとして三途の川ではなかろうか。三途の川を渡るには渡し銭が必要だと聞いたことがある。ズボンのポケットをまさぐると小銭があった。間銀として使うにはこれでじゅうぶんだろう。そうか、俺は死んだのか。思えば長いような短いような人生だった。人間万事塞翁が馬、人間到る処青山あり。
「汚れつちまつた悲しみに
今日も小雪の降りかかる
汚れつちまつた悲しみに
今日も風さへ吹きすぎる」
筒井は万感の思いを託して中原中也の詩を哀吟した。少年時代から愛吟した詩篇だった。
川の流れが眼にはっきり映った。視力を取り戻した筒井の前に白髪の老人がひとり、にこやかにこちらを向いて立っている。
「あの……あなたはどなたですか」
「阿育王じゃ」
筒井は耳を疑った。阿育王といえばたしか紀元前三世紀頃、インドのマガダ国に君臨したマウリヤ王朝第三代アショーカ王だ。インドを統一し仏教を保護したと、高校の歴史の授業で教わったのを思い出した。アショーカ王は「あれが阿育王山じゃ」と、はるか遠くの山を指さして歩き出した途端に「痛い!」と声をあげて倒れた。右足の裏から夥しい血が流れている。両端の尖った間釘を踏んでしまったらしい。どくどくと流れる血におののいて右往左往する筒井にアショーカ王は「なあに、心配には及ばぬ。こういう時に備えて合薬を持っておるのじゃ」と、長い左の袖から木でできた小さな瓶を取りだして油のようなものを傷口に塗ると出血はぴたりと止まった。瓶の容器と蓋は合口で、蓋を閉めると逆さに振っても中身がこぼれない。見事な合口造だ。感心した筒井の足がよろめき、へなへなとその場にうずくまった。
「どうしたのじゃ? 顔面蒼白、まるで歌舞伎の藍隈のようなご面相じゃが」
「だ、大丈夫です。ただの貧血です」
幼い頃から筒井は血を見ると気が遠くなる。小学五年生の時に母方の祖母が亡くなり、同じ日に親友の父が急死した。筒井は友人の葬式に行きたかったが母に「やめなさい」と言われた。「相悔みと言ってね、両方の家でお葬式がある時は縁起が悪いから相手の葬式には出ないのがしきたりなのよ」。説明してくれた母が鼻血を出した。それを見て失神してしまったのだ。何十年も昔のことを思い出しながら、筒井はアショーカ王の顔を見上げてぷっと吹き出した。
「何がおかしいのじゃ?」
「すみません、笑ったりして。あなたの――失礼、陛下の口調があんまりおもしろいので、つい……」
「わしの口調がどうだと言うのじゃ」
「その『じゃ』ですよ。『○○じゃ』の『じゃ』。フィクションではときどき見かけますけど、実際に『○○じゃ』って言う人にお目にかかるのは初めてなので」
「ならば言いかたを変えて進ぜよう――わしがインドを統一したアショーカ王でんがな。ほんまやで! でんがなまんがな!」
アショーカ王はインチキ臭い関西弁でまくしたて、明石家さんまみたいに出っ歯を剝きだしにして笑った。なんて愛くるしい王さまだろう! 筒井はさっきから疑問に思っていたことを訊ねた。
「ところで、この川は三途の川ですか」
「おまえはアホか? ベルトコンベアのある三途の川なんてものがありまっか? よく見てみい」
指さされた川向こうを見ると、なるほど大きなベルトコンベアがガタガタ音を立てて動いている。原動側と従動側のあいだにはちゃんと間車が嵌めてあり、瓦礫のようなものが次々にダンプカーに詰めこまれてゆく。「三途の川にダンプがあったら……往生しまっせ!」。大木こだま・ひびきの真似をしてはゃぐアショーカ王はじつに愛くろしい。
「あの瓦礫は何ですか」
「あれか? あれはな、ほら、1858年に中国黒竜江省北部の愛琿でロシアと清国のあいだに愛琿条約が結ばれたやろ? 黒竜江を両国の国境と決めた条約や。あの時にほったらかしにされた戦争の名残や」
三途の川ではなかった! 黒竜江なのだ! てっきり冥土への旅路かと思ったが、俺はまだ生きている!――筒井はアショーカ王の説明を聞いてほっと胸を撫で下ろした。しかし気になることがある。1858年の戦争の名残? するとここは19世紀のロシアと中国の国境なのか? 俺はタイムスリップしたのか?
アショーカ王の足もとを見ると、愛恵する飼犬とおぼしき子犬が一匹じゃれついている。「ちんちん!」「おすわり!」と王が命ずるたびに犬は愛敬たっぷりに従って嬉しそうに尻尾をブルンブルン振り回す。「ジャンケンポン!」。アショーカ王がグーを出す。犬もグーである。合拳だ。相手は犬だからチョキかパーを出せば勝てるのにグーを出すところを見ると、王と犬のあいだではグーしか使わないという相見が成立しているのだろう。もっと遊ぼうよとせがむ愛犬の様子にアショーカ王は目尻が下がりっぱなしで、その眼は慈悲深い仏の愛眼のようだ。「ジャンケンポン!」。両方ともグー。またしてもあいこである。柔和な王の愛顧を受ける犬は幸せ者だ。犬に囲碁を教えてやれば相碁の腕前にまで上達するのではないかとさえ思われるほどである。アショーカ王は右の袖から魚を一匹取りだして犬にやった。南日本の浅海で獲れる藍子という骨の硬い魚だという。犬を愛護し、動物の飼育を愛好する王のあたたかい心に触れて、筒井は長野の自宅で飼っている文鳥を思い出した。自宅を離れていったいどれくらいの月日が経ったのだろう。今頃は主人の帰りを今や遅しと待っているに違いない。今すぐ家に帰りたい! でもここは19世紀後半の黒竜江、飛んで帰りたくても帰る手立てがない。腹をすかせた文鳥の姿を想像して筒井は哀号した。もう二度と会えないかもしれない――哀哭する筒井の泣き声ははるか遠くの山に届かんばかりであった。
2015年12月8日
とりかえっ語14周年
本日めでたくとりかえっ語が14周年を迎えました。15年目もどんどんとりかえましょう!
2015年12月7日 Part 2
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十三回
歓声と拍手がどっと湧き起こる。ももいろクローバーZのゲリラライブが始まったのだ。眼鏡を壊してしまった筒井は盲同然で観覧する羽目に相成った。こんな時こそ相馴れた妻に手を引いてほしい。愛に愛持つ五人のメンバーはきっと愛らしいパフォーマンスを繰り広げ、相嘗祭のような賑わいに違いないのだ。生憎眼が見えない筒井の耳にアイヌのわらべ唄「ピリカピリカ」が聞こえた。ももいろクローバーZがアイヌ語で歌うとは! 観客がうっとり聞き惚れているのが肌で感じられる。誰のアイデアか知らないが、アイドル・グループにアイヌ民謡を歌わせるとは、アイヌ文化の継承と振興を図り、その伝統についての知識を普及、啓発することを目的とするアイヌ新法の精神にのっとった妙案である。歌の次に聞こえてきたのはホメロスの叙事詩『イリアス』の一節だった。ももクロの五人がトロイアの英雄アイネイアスの数奇な運命を朗読し、観客は水を打ったように静まりかえって聞き入っている。感激のあまり筒井の涙腺が緩み、藍鼠色のジャケットに涙が落ちる。これほど心を揺さぶられたのは仏教その他にまつわる故事を集めた室町中期の書物壒囊鈔の原本を見て以来だ。ああ、ももクロちゃん! 「アイドルなんて茶屋女でもなければ遊女でもない、所詮どっちつかずの間の女だ」。女性アイドルに興味がない人は陰口を叩くものである。そんな奴らにこそ、このゲリラライブを聞かせてやりたい! 庭や路地の間の垣からでもいいからライブを見てほしい! ほら、なま暖かい東風が吹いてきたではないか! 風に誘われて外に出てこい!
視界が真っ暗になった。いくら目を凝らしても闇の中である。とうとう本物の盲になってしまったか……。あれ? 何だかおかしいぞ? 俺はたしか『闇の中』という題名の小説の主人公だったはずだ。なのにどういうわけか題名が『言葉におぼれて』に変更されたような気がする。気のせいかな? それとも作者が気まぐれを起こしたのか? だとしたら許せない。デ=アミーチスの小説『クオレ』のタイトルはイタリア語で「心」という意味だが、それを『愛の学校』などという陳腐きわまりない邦題にした翻訳者にも劣らぬ愚行である。いま俺の心の呟きを文字にして書いている作者がどこの馬の骨だか知らないが、「小説なんて能の曲中でほんの座興に見せる間の狂言に過ぎないよ」とでも思っているなら心得違いもはなはだしい。1931年に橘孝三郎が水戸に創立した私塾愛郷塾にでも通って小説の書きかたを一から勉強し直せと言いたい。文学は料理屋と同じ愛敬商売だ。登場人物を蔑ろにし、読者を楽しませないような小説に存在価値はない。だいたい作家という人種はどいつもこいつも自信過剰だ。阿弥陀如来のように柔和な愛敬相の持主はひとりもいない。お山の大将を気取って通り一遍の愛敬付合いしかしないし、少し魅力が出て愛敬付いてきたかなと思って気を許すと、婚礼の祝いにもらった愛敬の餅を人に投げつけたりする。酒を飲めばすぐ愛敬紅を塗ったような赤ら顔になってくだを巻くし、愛敬黒子がチャーミングですねとお世辞を言えば、これは江戸時代に婚礼の際新婦が襟にかけた愛敬守りのようなものだよとくだらない蘊蓄を傾けて我こそは天下一の愛敬者なりとふんぞり返る。こっちは、まったくですな、ハハハと愛敬笑いするしかないじゃないか。ああ、忌々しい! 小説家なんてくたばっちまえ!
2015年12月7日 Part 1
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十二回
筒井は偽造カードをヒラヒラさせながら「ワタシ、ニホンゴ、ワカラナイアルヨ」と運転手に言った。片言で日本語を話そうとするとなぜかインチキ中国人みたいな口調になってしまうから不思議だ。運転手は「嘘つけ! さっきから流暢に話してたじゃないか」と怒鳴って足下から藍鉄色の金棒を拾い上げ筒井の頭をゴツンと殴った。その拍子にハンドルを切り損ね、バスがぐらりと傾き横倒しになりそうになったが車体はかろうじて転倒を免れた。筒井を相手取ったばっかりに大事故を起こすところだった。どんなもんだ、ベテランの腕前を見たか、と運転手は自慢したかったが、考えてみれば運転中に乗客がみだりに話しかけてくれたからこそ運転技術を披露できたのだ、相手のさする功名ではないかと思い直した。
筒井はバスが傾いたとき足をすべらせて転び、必須アイテムである眼鏡を割ってしまった。どこかで眼鏡を調達せねば。筒井はバスを停めてほしかったが、運転手は無線で会社の人と話し中である。乗客にそっぽを向いて相手向いにするとは不届き千万、もし男に妻かいるなら肝胆相照らすその女と一緒にあの世に送ってやる、ただ殺すだけでは気の毒だから夫婦ともども相殿に祀ってやってもいい、と筒井は殺戮への欲望がむらむらとわき上がり、我が事ながら恐ろしく、アイデンティティーが崩壊しそうになる。見納めにと運転手の顔に視線を向けたが、眼鏡を失ったのでぼんやりとした人影しか見えず、正体をアイデンティファイできない。
車内のラジオからニュースが流れた。都内某所で催された連歌の寄合で相頭をつとめた歌人が心臓発作で急死し、多くの著名人が哀悼の意を表したという。東京か。バスは今どこを走っているか知らないが、たぶんまだ東京は間遠だろうと筒井は思い、暇つぶしに愛読書である小説『処刑台』の続きを読み始めた。遊郭で遊ぶ主人公の男女が相床に寝て、お互いに相年であるのを喜び、明日は隣の神社を参詣しよう、相殿造の乙な神社だよなどと語らう場面だった。『処刑台』の作者はキルギス共和国の作家アイトマートフである。遊郭の男女は相伴って神社を訪ねる。何をするにも常に二人一緒で相取りする、恋人というよりは兄妹のような関係だ。
突然バスがアイドリングストップした。「ももいろクローバーZだ!」と運転手が叫ぶ。そんな馬鹿な話があるか。高速道路の路肩にアイドルが突っ立っているなんてあるまじきこと、源氏物語の登場人物ならあいなと言って怪しむところだ。とはいえ本当にいるならぜひ姿を見たい、メンバー五人は本当に相中なのか、この目で確かめたいと筒井は思ったが、間の悪いことに眼鏡がないので窓の外を眺めても目に映るのはぼんやりとした白い雲のような景色ばかりである。見たい、いや諦めよう、でも見たい――欲望と諦念が相半ばする。しかしいくらあがいたところで無駄である、紫式部ならあいなしと書くだろう。こうなったら裸眼で勝負だ。ももいろクローバーZに握手を求めて近づけばいい。筒井は運転手に、五分でいいから待っていてくれと、あいな頼みしてバスを降りた。
高速道路の路肩だろうと思った筒井がバスを降り、近眼の眼を凝らしてまわりを見渡すと、どうやらサービスエリアだった。店舗があるらしい所に向かう。「お客さん、どうぞ。これ食べてみて」と女の声がして串焼きみたいなものを手渡された。鮎魚女の塩焼である。女の顔に鼻先を近づけて頭のてっぺんから足下まで舐めるように見ると、女は藍韋の革で作った羽織のようなものを着ている。新嘗祭の前に行なう相嘗祭の際に身につける衣裳なのだという。
2015年12月6日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十一回
相対尽くで一緒に川に飛びこんでくれる人はいないか、筒井がキョロキョロあたりを見回す。市民は脱兎の勢いで溶岩流から遠くへ逃げてゆく。ある者は焼け落ちる自宅を眺めながら損害賠償は江戸時代なら相対済し令で解決できるのにと肩を落とす。家が焼けたのはおまえのせいだ、いや、おまえだ、と相対して怒鳴り合う者もあれば、相対相場の相対売買で儲けた金が一瞬で灰になり、叔父甥の間柄で抱き合い涙に暮れる者もある。そうかと思えば溶岩流を眺めながら暢気におやつのドーナツを間食いする女もいて開いた口がふさがらない。
筒井の眼の前に空からだらりと一本の梯子が垂れ下がった。救助隊のヘリコプターだ! まさにあいた口へ餅、藁にもすがる思いでつかまると梯子はスルスルと巻き上げられ、あっという間に筒井はヘリコプターの格納庫に引き入れられた。「お腹がすいたでしょう。これ、どうぞ」と救助隊員が藍茸の天ぷらを差し出す。ひとりで食べるのは申しわけない、誰か共食者はいないかと筒井が立ち上がった拍子に頭を天井にぶつけ、思わず「あ痛しこ」と呟いた。
病院で決闘を迫られたあの剣客は今頃どこでどうしているだろう。あの時はもう少しで相太刀の斬り合いになる勢いだった。筒井はあいだちなく天ぷらをむしゃむしゃ食った。皿には刺身のつまによく使う藍蓼が添えてあり、空腹のあまり迷わず食べ、藍建で染めたハンカチで口もとを拭った。溶岩流で燃え上がるアルプス山麓の町を上空から眺めながら天ぷらを食うなんて無分別、あいだてないではないかとも思ったが、太政官庁の北東隅にあった朝所で会食した当時の参議たちだって同じ立場なら食ったに違いないのだ。集中治療室で手術を受けた相店の大家は無事だろうか。いや、逃げ遅れたに決まっている。俺が大家と医者の間に立ち、二人の間に入って避難誘導しなかったのが悔やまれる。涙に暮れる筒井に「着きましたよ」と隊員が声をかけた。気がつくとヘリコプターは広い滑走路に着地していた。アイダホフォールズ地域空港だった。
溶岩が噴き出たアルプスの麓からヘリコプターで大西洋を越えてアイダホにやって来た筒井は藍玉で染めたタオルで額の汗を拭い、隊員がくれた間物の饅頭を食べた。これがじつに美味だった。なんでも江戸時代の和算家会田安明がこよなく愛した菓子だそうで、会田は契りを交わした女と次に会うまでの間夜を、この饅頭を食べながら過ごしたのだという。「こちらへどうぞ」と滑走路から空港職員の男に声をかけられた。なよなよした、いかにもあいだれた男で、時代が時代なら朝所で会食しながら政務を行なうのが似つかわしい風情である。ヘリコプターを降りた筒井は案内されるまま隣のジェット機に乗った。どっと疲れが出て泥のように眠った筒井が目を覚ますと、そこは愛知国際空港だった。
到着ロビーに行くと、大きな字で「筒井様」と書いた白いプラカードを持った見知らぬ男が待ち構えていた。「長旅お疲れさまでした。大変な目に遭われましたね。あ、申し遅れましたが、こういう者です」と男は筒井に名刺を差し出した。肩書は愛知教育大学文学部の教授、氏名は「唯野仁」である。ん? 唯野仁? どこかで聞いたことがあるぞ。あ! 俺が執筆した小説『文学部唯野教授』の主人公と同じ名前ではないか! 呆気にとられた筒井に唯野教授は愛知大学で非常勤講師も務めていますと自己紹介を続けた。俺の小説の主人公と同じ名前の人間がこの世にいるとは。筒井は只野教授に愛着を感じた。
空港内には哀調を帯びた三味線のバックグラウンド・ミュージックが流れていた。西洋ではなく日本の楽器を愛重するとは今どき珍しい。筒井は長野の自宅で飼っている愛鳥の文鳥を思い出した。今年も五月十日になれば愛鳥週間が始まる。只野教授は駐車場に停めてあった自家用車に筒井を乗せ、知多半島の愛知用水に辿り着くと筒井を降ろし、では失礼、と車をすっ飛ばして去った。知らない土地に置き去りにされた筒井は、彼奴め、今度会ったらただじゃすまないぞ、と天を呪った。すると彼方からバスが来て筒井の横にぴたりと停車した。高速バスで、大きなフロントガラスの上に会津行と書いてある。福島県になんか用はないが、ひょっとすると自宅がある長野の近くを通るかもしれない。途中下車させてもらおうと決めた筒井はバスに乗った。
運転手は会津という名字の男で、筒井がここ数日の出来事を問わず語りに語って聞かせるとたいそう気の毒がって哀痛した。運転手も苦労人なのだろう、どこか俺と相通ずるところがありそうだと思った筒井の気持ちを察したのか、運転手は会津家の履歴を話し始めた。先祖は享保五年に南山地方の幕府蔵入地の農民が起こした会津御蔵入騒動で生き残った首謀者で、今もNHKの歴史番組から取材の申し込みが相次ぐという。運転手は巧みなハンドルさばきで高速道路をぶっ飛ばしながら、召し上がりませんか、と赤身の魚と白身の魚の刺身を並べた相作りの皿を筒井に手渡した。小腹がすいていた筒井はむさぼり食いながら、ところで今日は何月何日ですかと運転手に尋ねると「会津暦で三月十日です」と言う。西暦で教えてほしいのですがと筒井はさらに尋ねたが、運転手の耳には入らなかったようで、会津城はそれはもう立派な城ですよ、弥勒菩薩の異称は阿逸多と言いましてね、お祭りになると鍛冶屋の師と弟子が相槌をトントンと打ち合って盛り上げるんですなどと、どうでもいい話を続ける。筒井はしかたなく、へえへえと相槌を打つ以外にない。「夏祭りでは不祥この私が櫓太鼓の太鼓叩きを相勤めます」。運転手の自慢話が止まらない。バスの車内を見回すと座席のテーブルに会津塗のお椀が一つずつ乗せてある。会津嶺とも呼ばれる磐梯山の麓で制作された漆器だそうで、江戸前期の会津農書にも記述が見られる伝統工芸品だという。
筒井はだんだん腹が立ってきた。幕末と維新期に会津小鉄という剣客が活躍したがあれは京都の人です、会津磐梯山を地元の人は会津富士と呼びます、山を眺める和服姿の女が合褄を気にしながら身をよじる様子は色っぽいですよ、会津身知らずという福島原産の柿は召し上がったことがありますか、え、ないんですか、ぜひお食べなさい、ここだけの話ですけど、品種改良したのは新潟生まれの歌人で書家の会津八一ではありませんよ、柿は会津焼の盆に載せると色が映えます、江戸後期の廻船問屋会津屋八右衛門が会津蠟燭を立てた横に盆を置いたのが後世に広まったんです、ぜひ会津若松にいらっしゃい――運転手は息継ぎもせずにまくしたてる。
筒井は頭痛がした。気分が悪い。妻の妊娠によって夫も悪阻と同じ状態になる相悪阻に似た症状だ。運転手の相手をしていたらこっちの身が持たない。突然アイディアが閃いた。日本語を知らない外国人のふりをすればいいじゃないか! 筒井はアイディアマンなのである。口の悪い友人は、なあに、あいつはただの観念論者、アイディアリストにすぎないよ、と言う。「アイディアリズムのどこが悪い!」と筒井は思う。観念的、理想的、つまりアイディアルであるからこそ人間ではないか。外国人だと偽ることにした筒井はジャケットの内ポケットをまさぐり、スイスの病院で拾った職員のIDカードを取り出して顔写真の上に自分の写真を貼り、ID番号を確かめて、ハンドルを握る相手方に示した。姑息な手段であることは重々承知の上だった。相手変れど主変らずとは言い得て妙で、筒井はいつもその場しのぎで辛くも窮地を脱してばかりいる。相手次第、相手尽では詐欺も厭わない。
2015年12月5日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第十回
相前後してレイチェルと駕籠かきの男二人が到着した。レイチェルは筒井にすがりつく剣客に向かって「放しなさい! 私はアイゼンハワーの孫よ!」と語気を荒げた。アメリカ合衆国第三十四代大統領の孫だったとは! 驚いた筒井も含めて一同「ははあ」とその場にかしこまると、レイチェルは俄然神々しく振る舞い、密教の愛染法というものがいかにありがたい祈りであるかを説き始めた。大阪市天王寺区の勝鬘院で毎年六月末に愛染祭が催され、会場には愛染曼荼羅が飾られるそうだ。愛染法の本尊は愛染明王と呼ばれ、衆生の愛欲煩悩がそのまま悟りであることを表わす明王なのだという。日頃から煩悩の塊であるのを恥じていた筒井はレイチェルが救いの女神に思えた。「どうか俺に祈りの極意を授けてくれ」と哀訴する筒井に、「自分の頭で考えろよ」とレイチェルはなぜか愛想が悪い。卑屈な態度を見て愛想を尽かしたのだろうか。俺を見限ったのか、それともわざと邪険に扱って心をもてあそぶつもりか。レイチェルへの愛憎が相半ばする。
筒井はジャケットの内ポケットから愛蔵の万年筆を抜き出して、これは死んだ親父が愛息である俺に形見として与えてくれたものだが、君にプレゼントしたいと、おずおずと差し出した。受けとったレイチェルが万年筆のキャップを外すとペン先からシュッと紫色の液体がほとばしり、滴が落ちた床の部分に煙が立ちのぼって見る見るうちに床に穴が開く。レイチェルは悲鳴を上げて万年筆を落とした。「アイソザイムだ」と、集中治療室から飛び出てきた執刀医が言った。同じ化学反応を触媒する酵素が二種類以上ある場合の、酵素のそれぞれをそう呼ぶのだという。まるで映画『エイリアン』のワンシーンのようで、全員後ずさりして穴の広がる様子を見つめる。床はどんどん溶けてゆく。執刀医は「地殻は密度のより大きいマントルに浮かんでいる状態にあるという考えをアイソスタシーと呼ぶのですが、この調子だとマントルまで貫通するかもしれない」と恐ろしいことを言う。筒井がふと横を見ると、レイチェルの姿がない。愛想尽かししてどこかに去ってしまったのか。
物凄い地響きがして大地がグラグラ揺れ、眼の前に真っ赤な炎の柱が噴き上がった。穴がマントルまで貫通したのだ。原子番号が同じで質量数が異なる同位体すなわちアイソトープが真っ赤な溶岩となって病院を焼き払う。一同蜘蛛の子を散らすように逃げ惑い、筒井は傍らのテーブルに置いてあったアイソトニック飲料をわしづかみにして逃げた。どこに避難するにせよ水分だけは確保しておかねば。パニックを起こして逃げ惑う人々の姿はアイソポスの寓話『イソップ物語』を思わせる。
レイチェルは無事だろうか。筒井は女と出会った逢い初めの地であるブリュッセルの中心街での出来事が遠い昔のように感じられた。どうか無事でいてくれ、再会できたら先祖代々伝わる藍染の着物をプレゼントしよう、藍染付の布地はきっと似合うはずだ、と筒井は女への想いがつのる。一緒にアイソメトリックスで筋力トレーニングをしよう、トレーニングウェアは馴染みの藍染屋に特注して作らせよう。どうか愛想もこそも尽き果てたなんて言わないでくれ。愛想笑いはこりごりだ。筒井はレイチェルと結婚して子宝を授かり、子どもが愛孫を抱いて訪ねに来てくれる未来を思い描いた。レイチェルと俺の間にはきっと何かの因縁があるに違いないのだ。
筒井は病院を飛び出し、道端の電話ボックスからスイスのアメリカ大使館に電話をかけた。大使館にはたしか会田という日系人の職員が勤めており、レイチェルの居所がつかめるかもしれないと思ったのだ。ところが電話に応じたのはスイス人の職員で、「会田はIターンして郷里の長野にいます」とフランス語で告げた。会田と相対でレイチェルを捜し出したいと思ったのに。受話器を置いて肩を落とし、ふと見上げると、峨々とそびえるアルプスの高峰を取り巻くように白い雲が靉靆している。町の中心を流れる川に浮かぶ小舟の船頭が欸乃すなわち舟歌をうたう。橋の欄干から船を見下ろした筒井は絶望し、誰でもいいから一緒に入水して相対死にしたいと思った。
2015年12月4日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第九回
しびれを切らした剣客が「おい」と廊下のほうに声をかけると、刀を構えた男がもう一人現れた。同じ家に相住みする浪人だそうで、刀と思われた細長い棒はよく見ると絵の具として使う藍墨だ。「二対一とは卑怯者め。これで相済むと思ったら大間違いだぞ」と筒井が怒声を発すると、剣幕に気圧された剣客二人はへなへなとしゃがみこみ、土下座して、アイスランドの広大な土地を譲るからどうかお赦しをと命乞いをする。アイスランド語を知らない筒井は辺鄙な土地をもらっても傍迷惑なのでけんもほろろに一蹴すると、ではケシ科の一年草アイスランドポピーの苗はいかがです、切花として大人気、いい商売になりますよ、ぼろ儲けできます、よかったら私たちと手を組んで相掏りになりませんか、濡れ手に粟ですぜ、と剣客は藍摺の着物の皺を伸ばしながら揉み手して筒井の機嫌を伺う。元手の要らない商売とは願ったりかなったりだ。わざわざアイスリンクでスケートの勝負をする手間も省ける。氷上スポーツを愛する筒井は少し心残りだったが、儲け話に一口乗ることにした。
「ではさっそくですが、娘を嫁にもらって頂きましょう」
剣客が手を叩いたのを合図にドアを開けて入ってきたのは、派手な着物を着崩した二目と見られぬ醜女だった。商売を始める前提条件として、娘の愛婿にならねばならぬと剣客が言う。相席したことさえない初対面の女と結婚しろとは、まるで哀惜の念に堪えない人を嘲ったり、愛惜の品を失った人をからかったりするのと同じくらい失礼な話である。筒井が言下に断ると、剣客は「娘は女相撲の相関、すなわち張出大関になるしか取り柄がなく、幼い時に母親と死に別れたのです」と哀切な話を語り始めた。剣客の相棒も哀絶の涙に暮れている。涙もろい筒井はもらい泣きしそうになったが、ぐっとこらえて言い放った。
「私はアイセル湖」に行かねばならないのです。ではこれで失礼」
口から出任せだが、こんなことでも言わないとその場を逃れられない気がしたのだ。筒井が立ち去ろうとすると剣客はジャケットの裾をつかんで「お名残惜しい。お別れの前に相先でぜひとも囲碁を一局。商売の仲介手数料、間銭は必ず払います」としつこく迫る様子はまるで愛染の虜となって去り行く恋人にすがりつく女のようだ。窓の外は黒い雲が靄然として町を籠める。筒井は傍らにあった登山用具のアイゼンをむんずとつかんで剣客に振り下ろす。ひらりと身をかわす剣客の浮世離れした身のこなしは、1946年に愛善苑と名を変えて再発足した神道系宗教の一派大本教の開祖出口ナオを思わせた。なおもすがりついて放さない剣豪はまるで愛染かつらの高石かつ枝だ。
2015年12月3日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第八回
女は息もつかずにまくし立て、ハンドバッグから iPad mini とスマートフォンを取り出して両方を接続した。二つのデバイスを入出力、すなわちI/O装置として使うのだろう。タブレットの画面にIOC、国際オリンピック委員会のトップページが表示されたが、タップしてもページが変わらず、画面がフリーズした。女はイライラしてもう一服相思草を吸った。どうやら重度のヘビースモーカーらしい。うんともすんとも言わなくなった iPad mini に業を煮やした女は歩道に落ちていた合折釘を拾い上げ、般若のような面持ちでディスプレイにギギギギッとこすりつけた。
突然つむじ風が巻き起こり、女は悲鳴を上げて筒井に抱きついた。ギリシア神話の風の神アイオロスの仕業に違いない。あっという間に二人の体が天高く宙を舞った。女は筒井にしがみついたまま言った。
「このまま死ぬなんてイヤ! 死ぬ前に生まれ故郷のアイオワに行きたい!」
哀音を帯びた女の声はまるで哀歌を謳いあげるかのようだ。筒井は情にほだされ、憐憫と情欲がない交ぜになった奇妙な心もちになった。仏教では愛欲が人を溺れさせるのを河にたとえて愛河と呼ぶそうだが、俺はひょっとするとこの女に惚れたのだろうか。天の彼方に吹き上げられた二人が急降下してバタンと着地すると、そこは雪山だった。体が無事であるのを確かめた女が風景を眺めて言った。
「アイガーだわ」
「アイガーって何だ?」
「スイス中部、西アルプスの高峰よ。標高3970メートル」
そうか、クリント・イーストウッドが監督と主演を務めた映画『アイガー・サンクション』の舞台になった、あの山か。それにしてもよく標高まで記憶しているものだ、まるで百科事典だなと感心する筒井をよそに、女は藍返しのスーツの埃を払い、ハンドバッグから折りたたみ式の将棋盤を取り出して広げた。
「ねえ、一局やりましょうよ」
「将棋? こんな雪山で?」
「いいじゃない、ほかにすることもないし。そのうちきっと救助隊が来てくれるわ」
誘われるがまま筒井は女と将棋を始めた。序盤の陣形は定石通り相懸りだ。何気なくハンドバッグを見ると鍵がかかる仕掛けになっている。鍵をなくしたら使いものにならないだろうと言うと、平気よ、合鍵があるから、と女は将棋盤から目を離さずに答え、「王手」と言った。よもやアメリカ人の女に将棋で負けることはあるまいと高をくくっていた筒井は驚き、さてどうしたものかと思案しつつ麓を眺めると、目と鼻の先に避難小屋とおぼしき小さな建物がある。
「将棋なんか指してる場合じゃないぞ。見ろ、小屋だ」
筒井は女の手を引っぱって山頂から滑り降り、うまい具合に山小屋に辿り着いた。掘っ建て小屋にしては堅牢な造りで、梁と根太の継ぎ手が相欠になっている。ドアに貼紙があり、「避難小屋。駕籠あります」と書いてある。すると麓から、えっほ、えっほ、という男の声が近づき、駕籠を担いだ男が二人現れた。
「どうです、旦那。相駕籠をさしあげましょう」
「あいかご?」
「一つの駕籠に二人を乗せるんですよ」
ありがたい! 筒井は女と駕籠に乗った。男たちは再び、えっほ、えっほ、とかけ声をかけて山を下りる。駕籠の中の二人はまるで相傘だ。
駕籠がピタリと止まる。いつの間にか山麓の宿場町に着いた。どこかに宿はないだろうかと駕籠かきに訊ねると、宿はないが相借家ならすぐそこにありますよという返事だった。案内された家に行くと大家らしき小肥りの女が現れ、筒井と女を見比べて、どういう関係だい、と訊ねた。「私は歌い手です。こいつは三味線の合方です」と筒井は嘘をついた。大家は「商売女にしか見えないよ。どうせ吉原あたりの相方だろう」と、妙につっけんどんである。駕籠かきの一人がもう一人の相肩に「おい、大家の足を見ろ」と言う。大家は間形と呼ばれる江戸時代に流行った女物の小さな下駄を履き、鼻緒は沖縄の藍型で染め抜かれている。借家はI形鋼をがっちり組んだ鉄筋造りだ。部屋を貸してほしいのですがと筒井が来意を告げると、家の奥から大家の亭主らしき翁が現れ、能の間狂言の間語りを始めた。呆気にとられていると、翁は相構へて静々と足を運び、懐から取り出した間紙で涙を拭いながら父母を亡くした哀子の悲しみを厳粛に舞った。天涯孤独となった子の哀史を語る朗々たる声と優雅な舞はまさに動く一篇の哀詩で、生前親が蝶よ花よとかわいがって育てた愛子が、かつて同じ土地を共有していた合地のやくざ者にさらわれ、親は殺され、遺族が哀辞を述べ、愛児のあどけなさを称える、じつに見事な狂言だった。筒井の頬を涙が伝う。すると翁はまるで機械仕掛けのようにピタリと動きをやめた。
「またICがショートしちゃった」
大家が言った。ICは、たしか集積回路だ。さすれば翁は電動仕掛け、人間ではなくロボットだったのか!
「Igが不調なのかもしれないわ」
道連れの黒人女が大家に言った。
「何だい、アイジーって」
「免疫グロブリンです。抗体として働き、B細胞によって産生され、血清のガンマ‐グロブリン分画に含まれるんです」
「何のことだか、チンプンカンプンだよ」
「国際自由労連、通称ICFTUに勤めていた時、教わりました」
「そうかい。あんた詳しそうだね。じゃあ、ちょいと爺さんを直しておくれ」
「いいですよ。ICカードはありますか」
「そんな物がこんな山奥にあるわけないだろ」
「では大至急、国際商業会議所、通称ICCに連絡して下さい!」
「連絡って、うちは電話さえないんだよ。裏庭にICBMならあるけど」
「それって大陸間弾道ミサイルじゃないですか! ミサイルなら必ずICカードがセットされているはずです」
「でも、勝手にいじると国際刑事警察機構、通称ICPOがすっ飛んで来るんだ。ここだけの話だけど、あたしゃ前科者でね。もう二度と警察のお世話にはなりたくないんだ……」
言い終わるや否や、大家は気を失ってばたりと後ろ向きに倒れた。心臓発作だ! 筒井は外で待ちぼうけを食らわされていた駕籠かきの男たちを呼んで老婆を駕籠に乗せ自分も隣に乗りこみ、連れの女にはすぐ戻るから待っていてくれと言い残し、近くの総合病院に向かった。老婆はすぐICU、すなわち集中治療室に運ばれた。担当医は強い日射しを避けるためのアイシェードを目深にかぶり、白衣の代わりに藍下で染めたガウンを着ていた。なるほど窓の外からは冬のありがたい太陽の日射し、つまり愛日が燦々と降り注いでいる。ガラス窓で隔てられた隣室から治療の様子を見守っていた筒井の背後で素っ頓狂な女の声が聞こえた。
「間遮を持ってきたわよ!」
振り返ると、借家に置き去りにしてきたはずの黒人女が将棋盤と駒を持って笑っている。
「大声を出すなよ。病院だぞ。それに何だよ、アイシャって」
「将棋の間駒よ。知らないの? 日本人のくせに」
「どうやって来たんだ? まさか走ってじゃあるまいな」
「ううん、借家にね、大家さんの愛車があったから借りたの。ついでにワインももらってきちゃった。飲もうよ」
女が手回しよく持参したワイングラスに赤ワインをなみなみと注ぐ。二人は相酌して酒をがぶがぶ飲んだ。女の話によると、この葡萄酒は大家が愛惜した年代物だそうで、風味は言うまでもなくラベルのデザインにさえ愛着を覚えて、相借屋の居住者にさえも振る舞ったことはないという。
集中治療室では医師とスタッフが大家の治療にかかりきりだった。少し酔いが回ってきた筒井は、酔い覚ましにと病院の外に出た。正面玄関を外から見るとドアは板張りの合決で、アルプスから吹き下ろす風が当たってガタガタと鳴らす。濃いアイシャドーを塗った看護婦がドアから出てきて、訝しげに筒井の顔をちらりと見る。不審者と思われたに相違ない。ならばいっそのこと不審者になってしまえと腹をくくった筒井は浄瑠璃の相三味線を口真似で演奏してみた。咄嗟の思いつきにしては上出来で、哀愁を帯びた音色に我ながらうっとりし、どういうわけか黒人女への愛執が募った。
ブリュッセルの中心街で出会って以来、俺はまだ黒人女の名前を知らない。アルプスまで旅の道連れにした間柄なのに。筒井は再び病院に戻り、集中治療室の隣の部屋でぐでんぐでんに酔っ払って床に大の字になっている女に訊ねた。
「君の名は?」
「アハハ! 『君の名は』って菊田一夫のラジオドラマかよ!」
「いや、そうじゃなくて……」
「じゃあ佐田啓二と岸恵子の映画?」
「アメリカ人のくせによく知ってるな」
「馬鹿にしないで!」
「違うんだ。名前をね、まだ聞いてなかったなあと思って」
「レイチェルよ」
レイチェル。愛書家の筒井が真っ先に連想したのは『沈黙の春』の著者レイチェル・カーソンだった。次に脳裏に浮かんだのはリドリー・スコット監督の映画『ブレードランナー』でハリソン・フォード扮するデッカード刑事と逃亡する女レプリカントの名前だ。筒井はレイチェルとの相性がよい気がした。理由はわからないが、レイチェルにはどこか哀傷を感じさせる暗い部分がある。独身だろうか。あるいは誰かの愛妾だろうか。愛称は何だろう。
「ニックネームは?」
「レイよ」
「愛唱歌は?」
「レイ・チャールズの『ジョージア・オン・マイ・マインド』」
「愛誦する詩は?」
「質問攻めね。ダンテの『神曲』よ」
「ダンテ? あれを覚えてるの?」
「全部ここに入ってるわ」
レイチェルは茶目っ気たっぷりに人さし指でトントンと頭を叩いた。
「驚いたなあ。あの長編詩を暗唱できるなんて」
「哀情豊かな作品だから暗記しやすいのよ。主人公のダンテがベアトリーチェに捧げる愛情がこの上もなく美しいの」
うっとりした表情で『神曲』の魅力を語るレイチェルの横顔は高貴な家柄の愛嬢としか思われないしとやかさだった。レイチェルが『神曲』の地獄篇を朗読したら、古今東西のどんな哀傷歌も影が薄くなるだろう。できることなら俺も一緒にあいしらいして朗読に加わりたい。
病院に併設されたあひしらひ所、つまり宿泊施設から職員が走ってきた。手術が終わったのだろうか。大家の容態はどうですかと筒井があいしらうと、藍白地の革で染めたガウンを羽織った職員は藍の葉を刻んで木炭と加えて発酵させた藍汁が入った小さなカップを筒井に差し出した。患者の体内から抽出された液体で、フリーメーソンの会員にしか見られない合印だという。職員は濡れた指を江戸時代の奥女中がよく身につけていた間白の小袖で拭き取りながら筒井に訊ねた。
「あの患者とはどういうご関係ですか。母親か祖母か、それとも愛人ですか」
「とんでもない」
「そうですか。患者の戸籍を調べてみたのですが、先祖が愛新覚羅なんですよ」
「アイシンカクラって何ですか」
「中国の清朝帝室に由来する姓です。あなたは東洋人だから、ひょっとして親族ではないかと思いましてね」
筒井は職員に促されて集中治療室の隣室に戻った。患者は患部をアイシングして炎症を抑えている。中身はチョウザメの浮き袋で作ったアイシングラスらしい。枕の上の方の壁に「愛洲」と書かれたプレートがある。これが患者の名字なのだと職員はアイスをペロペロ舐めながら説明してくれた。愛洲は愛すに通じるのではないか。筒井はこの名字が何か重要な合図であるような気がした。
院内に突然非常ベルがけたたましく鳴り響いた。廊下をどやどやと走る音がする。筒井がいる部屋のドアがバタンと開き、古ぼけた袴姿の男がさんばら髪を振り乱し、抜き身の刀を振りかざして怒鳴った。
「ここにおったか! お命頂戴つかまつる!」
「どちら様ですか」
「問われて名乗るもおこがましいが、拙者は愛洲惟孝。室町後期の剣客、愛洲陰流の創始者、名を久忠と申す。いざ勝負!」
勝負と言われても、筒井には何のことだかさっばりわからない。そもそも命を狙われる覚えがないし、戦うにしても武器がない。しかしこの落ち武者らしき剣豪の言動にはどこか魅力的で愛づかはしいものが感じられる。古代ギリシアの雄弁家アイスキネスならきっと修辞を凝らして見事に描写することだろう。「武器ならこれをお使いなさい」と職員がアイスキャンデーを差し出してくれたが、そんなものが武器になるものか。こうなったら素手で戦ってやる。古代ギリシアの三大悲劇詩人の一人、アイスキュロスの三部作『オレステイア』の殺戮シーンを再現してやる。「いくらなんでも素手は無茶ですよ」と職員がアイスクリームを舐めながら口を出す。見ると右手にはバニラのアイスクリーム、左手にはアイスクリームサンデーを持ち、首から提げた二本の水筒にはアイスクリームソーダとアイスコーヒーが入っているのをストローでちゅーちゅー吸っている。こいつはいったいどれほどアイスが好きなのか。「どんだけー」と、ついIKKOの口真似をしてしまった筒井に、集中治療室から出てきた主治医が提案した。
「アイスショーで勝負したらどうです? ご覧の通りここはアルプスの麓、季節は冬。町中の池は凍って、滑り放題ですよ」
名案だった。北海道は札幌で生まれ育った筒井はアイススケートの達人である。チャンバラはとても無理だが氷の上なら水を得た魚、アイスダンスだってお茶の子さいさいだ。筒井は主治医が差し出してくれたアイスティーを一口飲み、「アイスハーケンはありますか」と耳打ちした。登山で氷壁を登り降りする際に氷に打ち込んで使うハーケンである。町中の道路や歩道はカチカチに凍ってアイスバーンになっているからアイスピックがあればなおありがたい。場所によっては氷河の急傾斜地帯、すなわちアイスフォールがあるかもしれない。ハーケンとアイスピックがあれば武器としても使えそうだ。筒井は傍らのテーブルのアイスペールから氷を一個つまんでアイスティーに入れたがすぐ溶けてしまい、もっと氷はないかと壁際のアイスボックスの中を探した。勝負するならアイスダンスなんていう手ぬるい競技ではなく、荒々しいアイスホッケーで雌雄を決するのも一興だと筒井は思い、ひとりほくそ笑んだ。
2015年12月2日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第七回
突然大音響が轟いた。天地がひっくり返ったように家屋がガタガタ揺れる。筒井が窓辺から外を窺うと、つい先ほど通ったばかりの一本道からまたしてもミサイルが発射された。
「ずいぶん物騒なところですね」
筒井が老人に水を向けると、老人はため息をついて呟いた。
「おまえさんがさっき畑で見たミサイルはIRBMじゃったが、今のはINFじゃ。1987年にアメリカとソ連が全廃条約に調印したのじゃが、ご覧のとおり、アメリカは極秘に開発を進めておるのじゃ。そんな話はどうでもいい。おまえさん、コーヒーを飲んだらIFCに行くといい」
「アイエフシーって、何ですか?」
「国際金融公社だ。わかりやすく言えば世界銀行の姉妹機関じゃな。そこに行けば電報の差出人がわかると思うのじゃ」
願ってもない話だ。筒井は熱いコーヒーにふうふう息をかけて冷ましながら一口ずつ啜る。老人は気を利かせて近所のタクシー会社に電話をかけ車を一台雇ってくれた。筒井は丁重に礼を述べて老人と別れ、到着したタクシーの後部座席に坐ると運転手に命じた。
「IFJまでやってくれ。大至急だ」
「アイエフジェー? 本当にアイエフジェーでいいんですか?」
「くどい! つべこべ言わずに、さっさと行ってくれ」
わかりましたよ、行けばいいんでしょう行けば、と運転手は怪訝そうな顔でアクセルを思いきり踏みこみ、猛スピードで北に向かって走り出した。アーリントンからワシントンDC、フィラデルフィアを経由してニューヨークに至り、フェリーで大西洋を超えてイギリスに渡り、船を乗り換えてベルギーに上陸、首都ブリュッセルの中心街にある大きなビルの正面でタクシーは止まった。
「着きましたよ」
「え? ここが国際金融公社なのか?」
「違いますよ。国際ジャーナリスト連盟です。アイエフジェー。ここが本部ですけど」
「でも、俺はアイエフシーに行けと言ったんだ」
「勘弁してくださいよ。アイエフジェーって言ったじゃないですか」
しまった! 言い間違えたのだ!
「運転手さん、申しわけない。私が行き先を間違えてしまった。すまないが国際金融公社に行ってくれないか」
「冗談じゃない! 北半球の裏側まで走ったんですよ! 長いことタクシー稼業やってますけど、大西洋を超えてアメリカからヨーロッパまで走るなんて、そんな馬鹿な客はあんたが初めてだ。とにかく、ここまでのタクシー代、ちゃんと払ってください」
「いくら?」
「五億六千万ドル」
「え?」
「だから、五億六千万ドル」
「そんな……そんな大金、払えるわけないだろ!」
「耳を揃えて払ってもらいますよ。持ち合わせがないならIFTUに交渉したらどうです?」
「何だい、そのアイエフティーユーってのは?」
「国際労働組合連盟に決まってるでしょう! 創立は1913年。第二インターナショナルを支持して赤色組合のプロフィンテルンと対立して黄色組合と呼ばれた、あの組織ですよ。1945年に解消されましたけどね」
「じゃあ交渉のしようがないじゃないか」
「だったらIMFに借りたらどうです」
IMFなら知っている。国際通貨基金だ。本部は……たしかワシントンDCだったはずだ。何てこった。さっき通り過ぎたばかりじゃないか。
「運転手さん……すまないが、もう一度ワシントンDCに戻ってくれないか」
「お断りします! ここまでの分を耳を揃えて払ってもらうまでは一歩も動きません」
筒井はしかたなくタクシーを降りた。どこかに銀行はないかと、オフィス街の広い歩道をキョロキョロしながら歩いていると、突然何かに頭がゴツンとぶつかり、尻餅をついた。
「ちょっとあなた! 痛いわねえ。どこ見て歩いてるのよ!」
頭を撫でながら筒井が見上げると、淡い紫色のスーツを着た黒人の女性が、おでこをさすっていた。「失礼しました」と詫びながら立ち上がった筒井が女の胸元を見ると、ILOと書かれたバッジがついている。
「あの……つかぬ事を伺いますが、あなたは国際労働機関にお勤めですか」
「そうよ。それがどうかした?」
「ILO条約で有名な、あのILOですね」
「だからそうだって言ってるでしょ? 何か用?」
「じつは……金に困っておりまして。まことに不躾なお願いで恐縮ですが、少しばかりお金を貸して頂けませんか」
「本当に不躾ね。信じられない。で、いくら欲しいの?」
「えーと……えーと、五億六千万ドル」
「え?」
「五億六千万ドルです」
それまでつっけんどんだった女が急に哀婉な身振りで筒井に手を差しのべ、体を起こしてやった。
「あなた……本当に五億六千万ドルが必要なの?」
「……はい」
女はいきなり筒井をギュッと抱き締めて、顔中めったやたらにキスした。
「あなたなのね! 私が待ち焦がれた人は、あなただったのね!」
「あの……ちょっと、どういうことですか」
「私ね、先週占いしてもらったの。とてもよく当たる占い師でね、こう言われたの。あなたは十二月一日に、ある男性から五億六千万ドルを無心される。その男性こそ、あなたの運命の人ですよって」
女にきつく抱き締められながら筒井はたじろいだ。占い師に見てもらったという話が本当だとして、金額までピタリ一致するなんてことがあり得るだろうか。狐につままれたような筒井をよそに、女はハンドバッグから煙草を取り出してスパスパ吸い始めた。愛煙家なのだろう。偶然の出会いは小説などでよく見聞きするが、実際に合縁奇縁というものがあるのかもしれない。筒井はふらふらと街路樹に寄りかかった。一本の根から二本の幹が接して生えた相生の樹木だった。女がハキハキと言った。
「さあ、行きましょう!」
「え? どこへ?」
「相生よ。兵庫県南西部、瀬戸内海沿岸の」
「なぜ相生なんですか」
「占い師に言われたの。運命の人とは相生で暮らすんだって。共白髪が生えるまで、仲睦まじく相老いの夫婦として添い遂げるの」
「でも……あまりにも急な話で、ちょっとついて行けないんですけど。私には私の人生がありますし」
「何を言ってるのよ! あなた日本人でしょ? こう見えても私は生け花をやるのよ。相生挿しが得意なの。長唄の相生獅子も歌えるわよ。愛の巣には相生の松を植えましょうね。夫婦が深い契りで結ばれて長生きすることの象徴よ。婚礼には相生盆を飾りましょう。一つの盆に男島と女島を並べるのよ。逃げようとしても無駄よ。小指と小指を赤い糸で相生結びにして結んじゃうから」
2015年12月1日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第六回
日本でも久しくお目にかからない、まるで昔話から飛び出てきたかのような純朴な老人夫婦に見とれていると、二人はやおら狂言の『相合袴』を演じ始めた。老婆は間赤の小袖を着て、老人はゴルフのアイアンを杖に見立てて幽艶に舞う。アメリカのアーリントンで狂言を鑑賞できようとは夢にも思わなかった筒井は感激して老人に訊ねた。
「失礼ですが、あなたはいったい何者ですか」
「いやあ、名乗るほどの者でもないがの」
胡麻塩頭を掻きながら老人は照れくさそうに懐から一枚の紙片を取り出して筒井に手渡した。名刺だ。肩書にIEとある。
「アイイーとおっしゃいますと……」
「インダストリアル・エンジニアリングじゃ」
てっきり農夫だと思ったら経営工学の専門家だという。呆気にとられた筒井の様子を見て老人はさも楽しそうに、驚くのも無理はないと言いたげな微笑を浮かべて問わず語りに話し始めた。
「わしは移民での。日系三世じゃ。アーリントンに来てすぐ父が死んだのじゃが、アーリントンの実業家が親代わりになって愛育してくれた。実業家といっても、商売のことしか頭にないような堅物ではなく、芸事が好きな人じゃった。ヨーロッパの歌劇が好きで、特にヴェルディの『アイーダ』は歌詞をぜんぶ諳んじていたほどじゃった。よくメトロポリタン歌劇場に連れて行ってくれたものじゃ。やれオペラだ、やれコンサートだと、会社をほったらかしにして遊び暮らしていた時期もあってのう、頭の固い専務たちとは相容れない関係じゃった。ついに取締役たちが合印を盗んで会社を第三者に売り渡してしまった。父は――もちろん血の繋がりはないがのう――『アイーダ』のレコードをかけては哀韻を含んだ歌にひとり暗涙を催したものじゃった。音楽だけでは気休めにならなかったようで、カリフォルニアワインを愛飲したものじゃ。酔いが回ると『俺はこんなもんじゃない。俺は騎士道物語アイヴァンホーの生まれ変わりだ。今に見ていろ』と言うのが口癖でのう。唯一残った財産が、ほれ、この畑じゃ。晩春になると藍植うと言って、藍の苗を苗床から移植したものじゃ。畑仕事のかたわら、好きな音楽をよく聴いていた。無調、復調、引用を駆使したアメリカの作曲家アイヴズの作品は殊にお気に入りじゃった。いつじゃったか、ヴェルディとアイヴスのどっちが偉大か、友人と言い争って喧嘩になり、相撃ちになったこともあったよ。まさに肉弾相撃つ、それはもうすさまじい戦いじゃった。幸い九死に一生を得て、畑で採れた藍を使って葛飾北斎風の藍絵を販売したところ、これが大当たりしてな、一挙に巨万の富を得て、のちにIAEAの理事長になった。そうじゃよ、国際原子力機関じゃ」
老人の数奇な半生を知った筒井は、記念写真を撮ってもいいですかと老人に訊ねながら、ポケットから今どき珍しい「写ルンです」を取り出した。
「写真はええが、そのカメラはISOがちと足らんと思うがのう」
「え? 何のことです?」
「ISO感度じゃよ。イソ感度とも言うようじゃが、ほれ、今日はこんな曇り空じゃから、あまりよく写らんと思う。わしの家にデジタルカメラがあるが、よかったら家に寄らんか」
筒井は好意に甘えて老人夫婦の家に行った。『大草原の小さな家』のインガルス家のような木造の二階建てで、インターネットにも接続できると老人が説明してくれたが、回線を調べてみるとISDNで、やはり地平線まで広がるトウモロコシ畑の真ん中にある農家だけあってブロードバンドは普及していないのだなと筒井は納得した。
「何のお構いもできないが、コーヒーを淹れるから、まあゆっくりしていきなさい」
「ありがとうございます」
筒井が礼を述べて木の椅子に腰かけた途端、窓の外にオートバイのエンジン音が聞こえた。
「筒井さーん、電報でーす」
郵便配達夫が大声を上げて玄関に現れ、電報を渡した。電報? ちょっと待て。俺は日本からアメリカ合衆国のアーリントンに吹っ飛ばされて以来、誰にも居場所を知られていないはずだぞ。なぜ電報が届くのだ? 誰がどうやって俺の居所を突きとめたのだ?
不審に思いながら筒井は電報の文面を読んだ。アルファベットと数字の羅列だった。
「ISBN978-4122022874」
小説家である筒井はISBNが国際標準図書番号であることにすぐ気がついた。しかし番号は何の本だかわからない。
「あの、すみませんが、ちょっとインターネットで調べさせてもらえますか」
「いいよ。ほれ、このパソコンを使いなさい」
老人は旧式のIBMデスクトップパソコンを示した。筒井はブラウザを起動させ、グーグルで「ISBN 978-4122022874」を検索した。ヒットした結果を見て驚いた。1995年に発売された筒井康隆の小説『残像に口紅を』中公文庫版ではないか!
どこの誰だか知らないが、ひょんなことからアメリカ合衆国ヴァージニア州アーリントン郡にやって来た俺の居所をつかんだ奴がいる。そいつは俺に電報を送って寄越した。しかもメッセージは俺の小説のISBNだ。いったい誰の仕業だ。俺に何を伝えようとしているのだ。そいつにじかに会って目的を聞きたい。いてもたってもいられない。だが探し出したくてもあてがない。筒井は途方に暮れて哀咽した。
2015年11月30日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第五回
その瞬間、大地が小刻みに振動し、地獄から響くかのような大音響が耳をつんざいた。傍らに大きな看板があり、IRと書いてある。情報検索(information retrieval)の略だろうか、それとも投資家向け広報活動(investors relations)であろうか。しかし、どっちだろうと頭を悩ませる暇さえなく、筒井の後方から道に沿って一発のIRBM、すなわち中距離弾道弾が発射された。畑の一本道はミサイルの発射台だったのだ。トウモロコシの栽培と誘導弾の発射を相合に行なうために道は作られたのであり、沿道にはトウモロコシの葉が藹藹と茂り、ミサイルから噴射された燃焼ガスが靄靄と棚引いている。
弾道弾がはるか彼方に飛び去り、耳を聾せんばかりの轟音が弱まるにつれ、足下からキーキーという鳴き声が聞こえてきた。マダガスカル島にしか棲息しないはずのアイアイが、筒井の足首にじゃれついている。道端には相合井戸があり、柵に相合牛が一頭繋がれ、畑の所有者であるらしい老人と老婆が相合い傘をさして相合煙管をぷかぷか吹かしている様子がいかにも愛愛しい。
2015年11月29日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第四回
アーヘンの夜会に是非参加したいと筒井は思った。しかしここは信州上田である。どうやってドイツに行けばよいのか。沈思黙考すると、ああら不思議、筒井の体がふわりと宙に浮き、猛スピードで空を飛ぶ。悪魔の仕業か、はたまた神のご加護か。いや、きっと1875年にボンベイで創設されたヒンドゥー教改革派のアーリアサマージに伝わる秘術にちがいない。いずれにせよ、このまま空を切って一気にドイツへ到達できればもっけの幸い、ついでにアーリア人になれれば申し分ない。火球となって大空を一直線に飛んでゆきながら筒井は「われをドイツに行かしめよ」とゾロアスター教の悪神アフリマンに祈りを捧げると同時に、三世紀頃の南インドの僧侶アーリヤデーヴァの霊魂にも念仏を唱えた。
ズドン! 俯せに着地した筒井が顔を上げると、眼の前にアーリントンと書かれた看板がある。アメリカ合衆国東部ヴァージニア州の郡だ。ドイツのアーヘンを目指したのに、着いた先はAachenではなくArlingtonだった。アルファベットのアールが恨めしい。あたりは広大なトウモロコシ畑である。面積はいったい何アールあるのだろう。トウモロコシは赤や黄色や青などさまざまな色が塗ってある。日本の田んぼアートにそっくりだ。フランス語人アートではなくアールと呼ぶのだろうが、おそらく地元の画家かイラストレーターがR&Dすなわち研究開発を行なって大がかりな芸術に仕立て上げたのだ。
急にめまいがした。足がふらつく。気が遠くなる。足下にぽたり、ぽたりと血が落ちる。激しく着地したときに頭から出血したらしい。Rh式血液型で言うと筒井はRhマイナスなので、輸血してもらいたくても相手は簡単には見つからない。リボ核酸、通称RNAがどんどん失われてゆくのが実感される。どこかに病院はないものか。遠くを望むと、RC造りの白い五階建てのビルが見えた。気力をふりしぼってビルに向かう。そばから見ると入口はアールデコで、建物全体がアールヌーヴォーだ。駐車場にはRVのワンボックスカーが何台も並び、白衣を着た男女が大勢、建物を出入りしている。
病院にちがいないと思った筒井は血だらけの体を引きずるようにして玄関を入った。正面奥に総合受付らしきカウンターがある。筒井は受付嬢に訊ねた。
「すいません、ここは病院ですか」
「いいえ、アーレント研究所です」
アーレント? ひょっとして『全体主義の起源』や『人間の条件』で名高い政治哲学者ハンナ・アーレントか? ああん! 病院じゃなかったのね!
失意のどん底に落ちた筒井は滅亡したアーンドラ王朝のことを想った。いかに栄華を極めた王朝でもいつかは滅ぶ。今の俺のように、王家の人々も血まみれになって死に絶えたのだろう。しかし自業自得ではないか。おごれる平家久しからず。野球で言えばアーンドラン、つまり自責点なのだ。
血と涙を顔から滴り落としながら筒井はビルの外に出た。濡れた頬を風がなでる。この風はひょっとして日本海沿岸に吹く北東の風、地元の人が言うあいではなかろうか。ヴァージニア州アーリントン郡になぜ日本海の風が吹いているのだろう。
「あいすみません」
突然背後から男の声がした。筒井が振り返ると男が三人、それぞれ一メートルほどの間を隔てて立っている。三人とも平たい笊を持ち、釣ったばかりとおぼしき鮎が山盛になっている。服装は着古した藍色の着物で、乞食かと思われる貧相な姿が哀を誘う。襟から裾まで埃まみれだ。
「一匹でもよござんす。魚を買ってくれませんか」
みすぼらしい男たちを気の毒に思った筒井は、彼らへの愛が芽生えるのを感じた。困ったときはお互い様だ。一匹くらいでよければ買ってやろうと、ポケットをまさぐって小銭を探す。すると男は、こちらへどうぞ、と、駐車場とトウモロコシ畑の間の小道を指さす。見ると、そこだけ妙に細い隘になっている。招かれるまま歩く。足下に残飯だの犬猫の死骸だのがあちこちに放置され、穢の巷だ。まるで羅生門のような陰惨な眺めに夢でも見ているのかと、筒井はアイをしばたたいた。もちろん眼をしばたたいたのだが、なにしろ居場所がヴァージニア州アーリントン郡なので、日本語で眼と言うよりは英語を使うほうがふさわしいと思われたのだ。
細道はアルファベットのIそっくりの一本道で、いつ果てるとも知れない。どこに連れて徃かれるのか、筒井はだんだん心細くなり、つい歩調が衰える。不安を悟ったかのように男が声をかけた。
「心配はご無用です。じきに目的地に到着と相成ります」
ほっとした筒井は無邪気に「あい」と返事した。
2015年11月29日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第三回
ダムには水がほとんどなく、斜面には誰が描いたのか巨大なグラフィティがある。こんなところでアートを鑑賞できようとは夢にも思わなかった筒井は、ポケットの中からくしゃくしゃになったアート紙を引っぱり出して広げ、口もとのアーティチョークを拭った。空腹が満たされて人心地がつくと、さてどうやってこのダムから家に帰ったものか、歩けない距離ではないが、きっと半日はかかるだろうし、かといって誰かに助けを求めたくてもまわりには人っ子一人いない。
「ちくしょう。これが映画だったらなあ」
もし自分が映画の登場人物だったら、きっと窮地を脱せるはずだと筒井は思った。しかし端役や脇役を簡単に殺すマイケル・ベイとかローランド・エメリッヒの作品は願い下げだ。願わくばアートシアター系がいい。スクリーンにはまず制作会社のロゴが現れ、次いで趣向を凝らしたアートタイトルが映し出されるだろう。アートタイプで印刷した細密画の複製のようなデザインであってほしい。アート・ディレクターの腕の見せどころである。
理想の映画作品を夢想しつつ、ダムの欄干から身を乗り出して底を見下ろす筒井の足が滑った。体は欄干を超え、球のように斜面を転がり落ちてゆく。半狂乱になって叫び声を上げ、気を失いそうになった瞬間、筒井は忽然としてアートマンの意味を悟った。自我の本質と霊魂を意味するアートマンと宇宙の根本原理であるブラフマンが同一であることが窮極の真理であり、ウパニシャッド哲学は正しいのだ。釈尊の従弟アーナンダに聞かせてやりたかった。
気がつくと筒井は大きな広間にいた。ダムの底に転落したはずなのに。身を起こしてあたりを見回すと、幅の広い横長のテーブルが三列に分かれて整然と並び、四方の壁は本棚だ。どうやら図書館らしい。窮極の真理を悟った瞬間、時空を超えたのだろうか。ふらつく足取りで本棚を眺める。ラグビー・スクールの校長としてパブリック・スクールの教育を刷新したイギリスの教育家トーマス・アーノルドの伝記がある。隣にはトーマスの長男で批評家のマシュー・アーノルドの『批評論集』があり、その隣はやはりイギリス人の詩人でジャーナリストのエドウィン・アーノルドの詩『アジアの光』だ。広間は自然光をふんだんに取り入れるためだろう、三角形の天井がガラス張りで、アーバニズムを特長とする建築様式のようだ。間接照明もいかにもアーバンで、誰が手がけたか知らないがアーバン・デザインの専門家がアーバン・ライフを利用者に堪能せしめんとしたのだろう。
体のどこにも怪我がないことを確かめた筒井は図書館には用がないので外に出た。すると前庭で草むしりをしていた老人が筒井のほうを向いて出し抜けに言った。
「アーベル関数論をどう思う?」
何の話だかさっぱりわからない。筒井は訊ねた。
「アーベルって、何ですか」
「決まってるだろ。ノルウェーの数学者だ」
「その人が、どうかしたんですか」
「五次以上の代数方程式は一般に代数的に解けないことを立証した男だ。そんなことも知らないのか。けしからん」
いきなり叱られてしまった。数学はチンプンカンプンだ。それより体の節々が痛む。どこかで湯治したい。
「話を変えて恐縮ですが、この近くに温泉はありませんか」
「温泉ならアーヘンに行くといい」
「アーヘンって、どこですか」
「ドイツ西端部の都市だ。世界的な温泉保養地だぞ。ものを知らないにも程がある」
また怒られた。庭師が言うには、アーヘンでは毎晩大勢の人が集まって講演や音楽を聴くアーベントという催しが行なわれ、遠くはインド西部のアーマダバードからも人が訪れるという。参加者は全員アーミー・ルックに身を包むのがしきたりで、アメリカから移住したアーミッシュの信徒がイギリスの彫刻家アーミテージの作品をハンマーで破壊するのがこの集会の目玉だそうだ。彼らはアーミンの毛皮を身にまとい、アームももちろん毛皮に覆われ、彫刻を粉々に砕きながらユゴー作『噫無情』を朗読するのだ。彫刻の破壊にはイギリスの工業家ウィリアム・ジョージ・アームストロングが開発した回転式水力発動機を使うこともあり、その時は必ずルイ・アームストロングのトランペット演奏と歌声を流し、聴衆はみなアームチェアに腰かけ、洋服の袖のアームホールを気にしながらアームレストに肘を乗せる。中にはアームレスリングに興じる者もある。破壊のパフォーマンスが終わると全員でアーメンを唱え、神に感謝しつつアーモンドを食べてお開きとなる。
2015年11月28日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第二回
筒井の恋人はコンピューターのアーキテクチャーを構築するエンジニアだった。留学先のアーカンソー大学から絵葉書を送ってくれたことがある。裏面は広大なキャンパスの写真で、表の文面によればロシア生まれの彫刻家アーキペンコの作品に出会い、とりわけなめらかなアークを特徴とする技法に心を奪われたと書いてあった。それまで藝術になど興味がなかったはずの恋人の胸の内に、さながらアーク灯のアーク放電が火花を散らすがごとく美術品への関心が芽生えたのを知った筒井は当時大学の三年生で、日曜大工が趣味だった。手先が器用だったから犬小屋からちょっとしたロボットまで、大概のものは何でも自分で作った。どんな材料も巧みに扱えたが、どうしてもうまくゆかないのかアーク溶接だった。何度挑戦しても失敗する。
「アークライトの爪の垢を煎じて飲め」
同級生の高橋によく言われたものだ。高橋は筒井と同じく文学青年で、学生の頃から文士と呼ぶにふさわしい風格があった。アークライトの顰みにならいたいのは山々だ。しかし、いかんせん産業革命に大きな影響を及ぼしたイギリスの発明家で、二百年以上前に死んでいる。どうやって爪の垢を煎じて飲めというのだ。高橋の無責任な放言にはうんざりする。いっそアーク炉に突き落として感電死させてやろうか。よし、思い立ったが吉日だ。筒井は悪魔じみたアーケイックな笑顔を浮かべて、高橋をあの世へ送る決心を固めた。
大学の近くにある商店街のアーケードを歩くと、まるで天の配剤かのように高橋の姿があった。少し離れたところから観察すると、古本屋の店先に立ってショーウインドーの中のアーサー王物語の背表紙をじっと見つめている。足下を見ると、今どき珍しくゴム長を履いている。ああした本を読む人間にろくな奴はいない。筒井はああしやごしやとあざ笑った。後ろからそっと近寄って、首根っこを押さえて引きずってやろう。筒井が足音をしのばせて高橋の背後に近づき、手を伸ばして首筋に触れた瞬間、雷に打たれて全身の毛が逆立った。
しばらく気を失った筒井が我に返ったとき、高橋の姿は消えていた。あいつは体内に電気を蓄えていたのだ。人間乾電池である。ゴム長を履いていたのは、アースで漏電するのを防ぐためだったに違いない。俺がうっかり触ってしまったばっかりに感電してしまったのだ。なんて恐ろしい男だ。倒れていた筒井が上半身を起こすと、そこはアースダムのてっぺんだった。感電の衝撃で近くのダムに吹っ飛ばされたらしい。巨大なダムはアーチを描き、まるでアーチェリーの選手がきりきりと絞る弓のようである。筒井はまだ学生だったとはいえ文学を志していたから、ダムの弧が弓に見える。アーチストならではの連想に、我ながら半ば感心し半ば呆れて、アーチダムからの眺望を恣にしながら、「いい眺めだなあ」とアーティキュレーションをはっきりさせて発音し、ポケットからアーティチョークを取り出してもぐもぐ食べ始めた。
2015年11月27日
広辞苑小説『言葉におぼれて』 第一回
筒井が小説を書き始めて半世紀以上になる。書きたいことはすべて書いた、いつ引退しても悔いはない、そう信じて絶筆を宣言したことさえあったが、老い先が短くなるにつれて、俺はこんなもんじゃない、まだ書ける、このまま死んでたまるかと、執筆意欲がむしろ高まってきた。しかし題材が思い浮かばない。
今朝、原節子の訃報に接した。芸能界との交渉を絶ってやはり半世紀以上になる原節子は、きっとすでに人知れず黄泉の客となったであろうと筒井は想像していたので、凶音を聞いても驚かなかった。とはいえ、正真正銘最後の銀幕スタアがこの世を去ったのだと思うと、スクリーンを見つめて胸が轟いた若き日の思い出が蘇る。筒井は文机の抽斗をあけ、昔マルベル堂で買った原節子のブロマイドを引っぱり出して眺めた。するとブロマイドの原節子が言った。
「筒井さん、辞書を使ってみてはいかがかしら」
ぎょっとした。肖像写真が口を開いたのにも驚いたが、小説の題材についてアドバイスをくれようとは思いもよらなかった。
「日本語の語彙をぜんぶ使って小説を書くんです。名案だと思いますわ」
虚を衝かれた。これまで夥しい数の小説を世に問い、小説家としての地位と名声はすっかり確立したと自負するが、指摘されてみると日本語の語彙をすべて用いた小説は書いたことがない。いや、およそ文筆家と呼ばれる者のうち、日本語のボキャブラリーを網羅した作品を創り上げた人など皆無だろう。
「『広辞苑』の項目を『あ』から順番に使うのよ。きっと面白くってよ」
雷に打たれたような衝撃を受けた。辞書に載っている言葉を最初から順番に選んでぜんぶ小説にぶちこむのだ。幸い手もとには『広辞苑』第五版がある。「名案だと思いますわ」と語りかけた原節子の声は神々しかった。永遠の処女と呼ばれただけのことはある。天啓を得た筒井は躍り上がって床を踏みならした。
「うるさい!」
階下から住人の怒号が聞こえた。足の音をしのばせ、玄関を出た筒井は家の裏手に回った。畦に中学生の男の子が三人、それぞれ網を手に、鮒でも釣るのか、それとも蛙の卵が目当てか、水田の脇を流れる小川の水面を、腰をかがめて見つめている。
「アルゼンチンのアは亜細亜の亜だよ」
「嘘つけ」
「マジだって」
「じゃあ、アフリカは?」
「アフリカは違う。阿川とか阿部の阿を使って阿弗利加と書くんだ」
「なんか嘘くさいなあ」
子どものくせに生意気だ、と筒井は独りごちた。外国の地名を漢字で書けと言われたら、俺だって書けない。伊太利亜くらいならまだしも、ハンガリーとかコートジボワールとかパプアニューギニアとかになると、まるで見当もつかない。でも、いいじゃないか。俺は小説を書き始めたのだ。ついに妙なる案を得たのだ。この悦びをどう表現したものか。遠い山に向って思いきり叫びたい気分だが、どういうわけか声が出ない。唖だ。筒井は愕然として膝をつき、外壁の漆喰、すなわち堊をかきむしった。何の前触れもなく声を失うなんて、まさに痾ではないか。
「吾が生涯も、もはやこれまでか……」
涙が頬を伝う。嗚咽をこらえて顔を上げると、山の手前にキラキラと何かが光るのが見える。
「彼は何ぞや」
筒井は目を凝らした。
「あ!」
声にならない声を上げた筒井の視線の先で、輝く物体はさっと宙に浮かび、空に素早く幾何学模様を描いて飛び去った。未確認飛行物体としか思えぬその動きに呆然となった筒井の頭上を、唖唖と啼くカラスの声が響きわたった。
「俺もああいう風に空を飛んでみたい……」
筒井は未確認飛行物体を操縦する自分を脳裏に思い描いて、思わず嗚呼とつぶやいた。あれ? 声が出るぞ。なんだ、失語症になったと思ったけれど杞憂だったか。ああいう怪しい飛行物体には、きっと人知の思い及ばない魔力があるのだ。おかげで俺は声を取り戻したのだ。――いや、待てよ。こんな話をいつかどこかで読んだ覚えがある。ワシントン・アーヴィングの随筆だったろうか。それともジョン・アーヴィングの『ガープの世界』だったろうか。どっちだったか忘れたが、たしかに読んだ記憶がある。急に暑さを感じた筒井はアーガイルチェックのセーターを脱ぎ、アーカンソー州リトルロックに旅立った昔の恋人のことを思い出した。
2015年11月26日
語尾取り14周年
明日23日、語尾取りがめでたく14周年を迎えます。ひたすら語尾を取り続けて14年。かくも長きにわたって続いてきたのはひとえに皆さまのおかげでございます。ご愛顧に感謝! 2006年3月3日以降の作品はほぼすべて保管してあります。
2015年11月22日
あなたに薔薇の花束を
12月3日から23日まで静岡芸術劇場で拙訳によるマヌエル・プイグ作『薔薇の花束の秘密』が上演されます。舞台は豪華な私立病院の病室。意地悪な入院患者と柔順な付添婦が繰り広げる、女ふたりだけのドラマ。患者を演じるのは角替和枝さん。テレビドラマでおなじみですね。付添婦を演じるのは美加理さん。ク・ナウカ時代から現在のSPACに至るまで看板女優として大活躍中。
二人芝居なのに舞台には五人の女性が登場します。どの人物も生き生きと描かれて、翻訳したわたくしは五人ともいとおしくて抱き締めたいほど。きのう稽古を見学したのですが、角替さんも美加理さんも膨大なセリフと格闘中で、ピンとはりつめた緊張感がひしひしと伝わってきました。稽古の様子はSPACの公式ブログで随時公開中です。ぜひ静岡芸術劇場に足をお運び下さいませ。
2015年11月19日
若者は離れる
二三日前にネットで見かけたニュースによると東京モーターショーとやらいう大きなイベントが閉幕し、入場者数が昨年に較べて一割減少したそうで、記事の見だしに「やはり車離れか…」の文言がありました。若者の大半は家計が苦しいので、維持費がかさばる自家用車を所有したがらないのが一因ではないかと記事の結びにありました。一読してわたくしは思いました。
「若者は離れるのだな」
いつ頃からか思い出せないのですが、「若者の活字離れ」というフレーズを見聞きするようになって久しい。ここでいう「活字」とはおそらく「文字が印刷された書物」のことでしょう。というのは、現在世の中に流通する書物のうち、活版印刷による本はほぼ皆無だからです。嘘だと思ったら最寄りの本屋さんに行ってごらんなさい。どの本も電算写植、つまりコンピューター組版で印刷されたものばかり。本物の「活字」を使った本は絶滅寸前、入手はきわめて困難で、ごく一部の愛書家が秘蔵するコレクターズ・アイテム、今や稀覯本と称してよいほどです。ですから、例のフレーズは「若者の書物離れ」と言い換えるべきでしょう。
本題に戻ると、若者はどうやらさまざまなものから離れたがる。ざっと思いついたものを挙げてみると――
「若者のテレビ離れ」
「若者のタバコ離れ」
「若者の雑誌離れ」
「若者の新聞離れ」
「若者の恋愛離れ」
「若者のセックス離れ」
ほかにもまだまだあるに違いなく、ネットで調べてみると案の定、「若者の○○離れ」を列挙したサイトがあるではありませんか。末尾に五十音順のリストがあります。「IT業界離れ」に始まって「アカデミー賞離れ」「インターネット離れ」「腕時計離れ」があり、「トマト離れ」「納豆離れ」を経由して、最後には「人生離れ」「人間離れ」まである。
若者は離れる。離れてこその若者だと断言したくなるほどです。しかし「人生離れ」とはいったいどんな状況をさすのか。人生から離れてしまえば死の世界が待ち受けるだけですから、どうやら自殺のことらしい。
では「人間離れ」はどうなんだ。人間離れといえば、ふつうは凡人の思いつかない技能やアイデアの持主をさす表現です。でも、きっと違う意味なのでしょう。文字どおり人間から離れるのだ。人跡未踏の地で、植物や動物に囲まれて、仙人のように暮らす若者だ。「そんな若者見たことないよ」と反論するのは無理である。なにしろその若者は人跡未踏の地にいるのだから。仙人のように暮らす若者は限りなく神に近い。あらゆるものから離れた最近の若者は神になる。東京モーターショーの入場者数が減るのも当然です。
2015年11月10日
賞を受けとらない
毎年十月になるとノーベル賞が発表され、今年の文学賞はベラルーシのスベトラーナ・アレクシエービッチさんに贈られることが決まりました。十年前から日本の有名作家が候補に挙がっては受賞を逃し、今年こそ、今年こそ、と期待に胸を膨らませる熱烈なファンはまたしてもお預けを食わされました。
ノーベル賞受賞の知らせを受けた人はたいてい満面に喜色をたたえてマスコミの取材を受けます。しかし中には受賞を辞退する人がいる。文学賞では1964年にジャン=ポール・サルトルが受賞を拒みました。その理由をサルトルはふたつ挙げました。ひとつは「賞を授ける組織あるいは制度に自分がコミットすることになるのがいやだから」という個人的な理由で、もうひとつは「西側諸国と東側諸国の対立は解消されるべきだが、私は東側諸国すなわち社会主義が主導的役割を果たすべきと考えており、ノーベル賞は西側諸国が贈呈するものだから私の主義に反する」という客観的な理由でした。サルトルは1945年にフランスの最高勲章であるレジオン・ドヌールも辞退し、公的な賞はことごとく「要りません」と突っぱねた人でした。
大江健三郎さんが文化勲章を辞退したのも記憶に新しい。民主主義を信奉する大江さんは天皇陛下が下さる勲章をもらうわけにはいかない。自分の主義に相反するからです。
このように、政治的な主義主張に反するという理由で受賞を拒む人がいますが、まったくちがう理由で賞を受けとらない人もいる。たとえば小説家の古井由吉さんです。
古井由吉さんは1971年に『杳子』で芥川賞を受賞したのち、1983年に『槿』で谷崎潤一郎賞、1990年に『仮往生伝試文』で読売文学賞を受賞し、1986年から2005年までの二十年間は芥川賞の選考委員をつとめました。ところが1997年に『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞してからは一切の賞を拒み、2005年を最後に芥川賞の選考委員も退任しました。「文学賞をさしあげますよ」と言われても「いいえ、結構です」と断り続ける。なぜかというと「小説を書く仕事に集中したいから」です。
大きな賞をもらうと、まずマスコミが大騒ぎします。取材が殺到する。友人知己や親類もお祝いする。祝電が届き、手紙やメールが山のように押し寄せる。「受賞の喜びについてエッセイを書いてくれませんか」とか「講演をしてくれませんか」といった依頼が次々と舞いこむ。あれやこれやの雑事が増えるばかりで、肝腎の仕事に手がつかなくなる。ご高齢の古井由吉さんは、小説を心ゆくまで書ける時間が残り少ないことを切実に感じており、生活が雑事に乱されるのが耐えられない。静かにじっくりと小説を書く暮らしを邪魔されたくない。だから「賞はいらない」のです。
2004年に発表なさった『野川』に深く心を打たれたわたくしは、どうか静かにじっくりと、心ゆくまで小説を書いて下さいと願わずにはいられません。
2015年10月9日
15周年
たった今思い当たったのですが、当サイトを開設したのが2000年10月6日なので、きのうめでたく15周年を迎えたのでした。これもひとえに皆さまのおかげでございます。記念日を忘れたのはひとえに粗忽者のわたくしのおかげでございます。ありがたや、ありがたや。
2015年10月7日
Happy Birthday, Mr. President
ついこのあいだお雑煮を食べたばかりだったはずなのに、暦を見ると早くも十月一日でございます。きょうが誕生日の人、いるかしら。もちろんいますよね。一年三百六十五日、毎日誰かがどこかで生まれたのですから。
愛用のデスクトップパソコンのモニターに常時日めくりGadgetというソフトを表示させておりまして、今も眺めながらキーボードをカタカタと叩いておりますが、この日めくりソフトには毎日、その日誕生日を迎えた有名人二人の氏名が載っています。本日は浜田光夫とジミー・カーター。
浜田光夫と聞いて、まあ懐かしい、と思わず声を上げるファンがきっといるはず。吉永小百合と共演した日活の純愛青春映画で人気を博した俳優さん。いちばん有名なのは『キューポラのある街』。ジミー・カーターは説明不要ですね。第39代アメリカ大統領。南部ジョージア州のピーナッツ農場から出世した議員で、演説すると南部訛りがひどくて、大統領になってからも訛りが抜けず、そのせいでからかわれたり、逆に親しみをもたれたりした人でした。
で、ここからが本題。誕生日に歌うお祝いの唄があるでしょう。言わずと知れた「ハッピー・バースデー」です。あの唄には作者がいるのをご存じですか。わたくしは不覚にも知らなかった。一ヶ月ほど前、スペインの新聞「ABC」の記事を読んで、初めて知りました。
記事によると、今年の8月末、アメリカのルイヴィル大学図書館の司書ジェームズ・プロセルさんが書庫で「ハッピー・バースデー」の楽譜を発見。プロセルさんは1950年代の音楽に関する資料を整理する作業中に、たまたま百年以上前の楽譜が三十枚入ったファイルを見つけ、調べてみるとその中に「ハッピー・バースデー」の楽譜があった。採譜されたのは1893年だそうです。ついでに申せば1893年は明治26年。
この有名な唄に作者がいることは、じつは周知の事実だそうで、わたくしは不明を恥じねばなりません。作者はミルドレッド・ヒル(1859年~1916年)という女性で、彼女は妹(姉?)と一緒に1893年に作詞作曲しました。ただし、当初は今とは歌詞が違い、「グッド・モーニング・トゥ・オール(Good morning to all)」だった。ところが原曲のオリジナル楽譜が今までどこにも見つからなかった。今回ようやくヒル姉妹が作曲した楽譜のオリジナル原稿が発見されたのでした。
誰もが口ずさんだことのある「ハッピー・バースデー」ですが、なんとワーナー・ミュージックが著作権を保有しているんですって。初耳だよ。おかげでワーナーは毎年200万ドル(約2億4千万円)を稼ぐというから、まったく油断も隙もあったものではありません。
最後にひとこと。わたくしがもっとも心を打たれた「ハッピー・バースデー」は、マリリン・モンローがジョン・F・ケネディ大統領に歌ったバージョンです。1962年5月19日、45歳の誕生日を迎えたケネディにマリリンは妖艶な歌声を捧げました。これが YouTube で手軽に聴けるのですから、便利な世の中です。
2015年10月1日
薔薇の花束の秘密
アルゼンチンの作家マヌエル・プイグ作、わたくしの翻訳による芝居『薔薇の花束の秘密』が本年12月3日から23日まで静岡芸術劇場で上演されます。チラシ(PDF)はこちら。
病室で出会ったわがままな女性患者と腰の低い付添婦の対話劇。出演は角替和枝さんと美加理さん。演出は近年さまざまな賞を受賞して大活躍中の森新太郎さんです。女の二人芝居ですが、男のわたくしも二十数年前からすっかり心を奪われた作品です。静岡県舞台芸術センター芸術総監督の宮城聰さんも絶賛する女のドラマ。ぜひ静岡に足をお運び下さい。
2015年8月24日
油断大敵
中国の天津で化学薬品が大爆発を引き起こし、桜島は大噴火の予兆を示しつつあり、あいかわらず物騒な世の中ではございますが、耳目を驚かすニュースに気をとられているそこのあなた! 大切なことを忘れてはいませんか?
「どんなときも、うっかりする」
粗忽の道を歩む者は、いかなるときにもうっかりしなくてはいけません。油断は禁物。千里の道も一歩から。残暑に負けず、気を引きしめて、うっかりしましょう。
2015年8月16日
電子書籍第二弾
またまたKindle版の電子書籍を出版しました。『ビジネス敬語は音読で身につけろ!!78の文例で、あなたの言葉遣いが劇的に改善する』。今度は5分で読めるシリーズです。代金は同じく299円。コピー&ペーストですぐ使える文例を集めました。
余談ですが、「身につけろ!」と吠えたり「劇的に」と大袈裟に形容したりするタイトルがいかにもビジネス書ですね。編集者のアイデアでございまして、ビジネス関係はちんぷんかんぷんなわたくしにはとても新鮮です。
2015年8月5日
電子書籍を出版したよ
なんとKindle版の電子書籍を出版しました。タイトルは『敬語が劇的に上達する7日間プロジェクト』。たった10分で読み終わるハウツー本です。気になるお値段は、わずか299円。
Kindleなんて見たことも触ったこともないのに原稿書いちゃったけど、いいんでしょうか? しかもビジネスマン向けの実用書。ビジネス書やハウツー本とは無縁の世界に生きてきたので、執筆依頼を受けたときはびっくり仰天しました。「書いて下さい! あなたなら書けます!」と編集者におだてられ、ついその気になって書いてしまいましたとさ。
著者名の「永井雄吉」はわたくしが勝手にこしらえたペンネームです。敬愛する永井荷風先生の本名に自分の実名の一字を加えてでっち上げました。
2015年7月28日
障碍者とともに生きる
映画館でぜひ観たいと思いながら気がついたときには公開が終了され、遅ればせながら先日ブルーレイで『アナと雪の女王』を観ました。姉妹の愛を描いた大ヒット作ですが、障碍者を描いた作品としても出色のできばえです。
エルサは生まれながらにして感情が昂ぶると身のまわりのものをすべて凍らせてしまう体質の持主で、心ならずも他人に迷惑をかけてしまう先天性の障碍者として描かれます。暴力の発動は自分の意志ではどうすることもできず、周囲の人に迷惑をかけたくないあまり引きこもりになる。妹のアナは姉がなぜ自室にこもり心を閉ざしてしまうのか、その理由が理解できない。で、紆余曲折をへた末にアナはエルサを理解し、「ありのままに」姉を受け入れます。
自分が障碍者であることに悩み、他人に迷惑をかけたくない気持ちが高じて引きこもりになる心理は、精神障碍者であるわたくしの心にまっすぐ響いてきました。外界との接触を断ち、部屋にこもって「ありのままに」独居を楽しみたい。しかし独居の楽しみはどこまでも非生産的で、心の健康には益することがない。だから障碍者は「ありのままに」社会に受け入れてもらうことを望むのです。
『アナと雪の女王』の主題は「いかにして障碍者と共生するか」です。ビリー・ワイルダー監督の傑作コメディー『お熱いのがお好き』幕切れの名高いセリフを引用するまでもなく、「完璧な人間なんていない(Nobody is perfect)」のです。その点において障碍者は健常者と変わりません。喜怒哀楽はもちろんのこと、日常的な悩みのレベルにおいてさえも障碍者はじつは健常者と変わらない。嘘だと思ったらEテレのバリアフリー・バラエティー「バリバラ」をご覧あれ。大勢の「エルサたち」が生き生きと悩みを吐露し笑い合うさまを見ると、人間っていいなあと思いますよ。
2015年7月26日
類語辞典を出版しました
皆さん類語辞典をお持ちですか? あると便利ですよ。たとえば「手紙を受け取りました」と言いたいとき、「ご書状拝受しました」「貴簡落手しました」「尊翰落掌しました」という具合に、同じ意味の言い換えができて、ボキャブラリーがどんどん増えます。
というわけで、『用例でわかる類語辞典 第2版』を出版しました。片手で扱えるコンパクトサイズ。最大の特長はすべての項目に例文があることと、使ってはいけない誤用例があることです。辞書は大好きなので、いろんな項目を張り切って書きました。お求め下されば嬉し涙がちょちょ切れます。
2015年7月1日
タモリとNHK
2009年秋に試験的に始まったNHK総合「ブラタモリ」が今春からゴールデンタイムに進出し、毎回見るのが楽しみです。
試験放送のときのナレーターは加賀美幸子アナウンサーでした。土曜のゴールデンタイム進出後はSMAPの草彅剛にバトンタッチ。草薙さんも悪くはないのですが、できれば加賀美幸子さんのままにしてほしかった。なぜならタモリさんがNHKで初めてレギュラー番組に出演したのが1979年~1981年放送の「テレビファソラシド」であり、メインの出演者が加賀美さんと頼近美津子さん、永六輔さんだったからです。
タモリさんのゆるい魅力と、端正でかつあたたかみのある加賀美さんの日本語はベストマッチ。お二人が初共演した「テレビファソラシド」の歴史をNHKはもっと大切にしてほしいと思うのであります。
2015年6月21日
「こんにちは」の苦悩
少子化に歯止めがかからない昨今ではありますが、我が町は住民の平均年齢が37.7歳で、全国でいちばん若いのでございます。家のまわりは朝から晩まで小さな子どもたちが元気よく遊ぶ声がひっきりなしに聞こえ、ああ、平和でいいなあ、と思います。なにしろ日本一若い町ですから、家から一歩外に出ると大勢の子どもたちに会います。すると、何人かに必ず挨拶されます。
「おはようございます」
「こんにちは」
挨拶を交わすのは気持ちがよいので、わたくしは喜んで「おはよう」「こんにちは」と応じます。ああ、気分がいいなあ……と思うのも束の間、心の中の悪魔が囁きます。
「おまえは不審者扱いされてるぞ」
道行く人に声をかけるのは防犯効果があるからだと、どこかで聞きかじったことがあるからです。
サラリーマンではないわたくしは真っ昼間でも町内をよく歩くので、もしかすると子どもたちにとっては「五十がらみの職業不詳の男」なのかもしれない。真っ昼間から町をぶらつく「五十がらみの職業不詳の男」は危険人物の可能性があるから、積極的に挨拶のことばをかけることによって「わたしたちはあなたを監視しているよ」というメッセージを相手に伝えて、犯罪を予防するべきである。
なんて世知辛い世の中でしょう! 子どもたちが元気に挨拶してくれるのは本当に「防犯」のためなのでしょうか? 一説によると「本当に怪しい人物には声をかけたりしない」し、小学校でも「怪しい人に声をかけようなどとは教えない」そうで、この説が本当であれば、子どもたちの元気な「おはよう」の挨拶は純粋に善意によるものだということになります。しかしながら「五十がらみの職業不詳の男」であるわたくしは、不審者とみなされても一向におかしくない生活ぶりなので、子どもたちの善意の裏に悪意がひそんでいるのではないかと疑ってしまう。「こんにちは」の苦悩はきょうも続きます。
2015年6月6日
安全運転のおまじない
自動車を運転中にイライラさせられることはよくあると思います。ウインカーも出さずに突然割りこまれたり、信号が青になったのに先頭車がスマホかケータイに夢中で発進しなかったり、交叉点で出会い頭に衝突しそうになったり―――。つい頭にかーっと血がのぼる。そんなときにわたくしはにっこり微笑んで呪文を唱えます。
「アンゼンウンテン、アンゼンウンテン♪」
するとどうでしょう! 不思議なことに、ささくれだった気分が嘘のようになごむのです。頭を左右に傾けると効果は倍増。「アンゼン」で頭を左に、「ウンテン」で右にと、振り子のように動かしながら呪文を呟いてごらんなさい。心が落ちつきますよ。殺気立つまわりのドライバーに対してさえ「どうぞお先に」と、あたたかい気持ちになれます。ぜひお試しあれ!
2015年6月3日
デジタルの弱点を克服しました!
皆さんはスマホやタブレットに不満を感じることはありませんか?
- 少し使っただけですぐ電池が切れる
- 通信料が高い
- スマホ依存症から抜け出せない
- 落とすと壊れる
- うっかりデータを消去してしまった
きっと思い当たる節があるのではないでしょうか。そんなあなたに朗報です! この度弊社は独自のイノベーションにより、デジタル・デバイスの短所を克服するまったく新しいアナログなガジェットの開発に成功しました。その名は「紙」です。
開発にあたって注目したのはパピルス。紀元前二千年ごろ、古代エジプト人はナイル川下流域に繁茂したカミガヤツリの茎の繊維を編んで筆写の材料を作りました。弊社はパピルスを現在に蘇らせる方法を二十年にわたって研究。その結果、植物の繊維に苛性ソーダまたは石灰を加えて煮沸し、水中に懸濁させ、すき網で濾してから乾燥させることにより、現代版パピルスを生み出しました。それが「紙」です。
アナログなデバイスである「紙」には次のような利点があります。
- 電気が不要なので電池切れの心配がない
- A4サイズの単価はわずか50銭(=0.5円)
- 鉛筆やボールペン、万年筆などの筆記用具が一本あればあらゆる文字情報を書きこめる
- きわめて薄いため、落としても壊れない
- デジタル・デバイスの寿命がせいぜい数年であるのに対し、百年以上の耐用性がある
- 折りたたんだり切り刻んだりすることでどんな形にも変えることができる
- 少額の切手を貼ることにより全世界のあらゆる場所にスムーズかつ確実にメッセージを送信可能
- 交通が不便な場所との通信には伝書鳩が大活躍
長所はまだまだたくさんあり、とても書き切れません。まさに二十一世紀にふさわしいツールです。皆さんも「紙」の威力を体感してみませんか? お近くの文房具店・ドラッグストア・スーパーマーケットなどで気軽にお求めになれます。「紙」と筆記用具をもって、あなたも最先端のアーバンライフをエンジョイしましょう!
2015年5月15日
スペインを通して考える日本
わたくしの恩師である佐々木孝先生がこのたび『スペイン文化入門』という本を上梓なさいました。これ一冊あればスペインの文化を広い視野で俯瞰できる好個の入門書です。しかも単なるスペイン文化の案内書ではなく、スペインを通して日本を考えさせられるのでございます。帯の惹句をご紹介しましょう。
ヨーロッパ近代から放り出されたスペインと世界に躍り出た日本。原発禍の中で浮かび上がる対照的かつ相互補完的な関係!
ついでと申しては失礼ですが、目次もお目にかけましょう。
- 原発禍の中でスペイン文化を読む―――「まえがき」に代えて
- 第1章 われわれにとってスペインとは何か
- 第2章 新しいスペイン像の模索
- スペイン文化の二つの頂点
- スペインについて書くことは泣くことである
- 自由教育学院
- スペイン科学論争
- 内面への道
- 夢想から現実へ
- 第3章 スペイン、その重層性の魅力
- 第4章 スペイン的「生」の思想
- スペイン的生の思想―――現代から黄金時代を読む前提として
- 葛藤の時代―――三つの宗教・文化の融合と葛藤
- 人文主義と神秘思想―――黄金時代の華
- 新世界発見―――その思想的意味
- 第5章 スペイン文化論を補完する二つの作業仮説
- 周辺の周辺は中央である
- 内面に向かっての沈潜
- 第6章 ドン・キホーテとスペイン精神
- 第7章 セルバンテス『ドン・キホーテ』
- 第8章 フランコ以後の新しい日々
- 第9章 民族とその風土
- 第10章 パロスの港 もう一つの地中海への出口
- 第11章 ゴヤまたは楽園のアダム
いかがでしょうか。青い文字で強調しておきましたが、「スペインについて書くことは泣くことである」「周辺の周辺は中央である」とは、いったいどういう意味でしょう? 興味をそそられたそこのあなた! 是非とも本書をお求め下さい。ソフトカバーなので片手で持ちやすく、文体はとてもわかりやすくて内容は奥深いこと請け合います。
2015年5月11日
伝統の技、守ります
ネットの世界はツイッターやフェイスブックなどのいわゆるソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、あるいはLINEなどのスマホアプリが隆盛を極め、昔ながらの個人によるウェブサイトはすっかり下火になった感があります。眞鍋かをりさんがブログの女王として人気を集め、ニフティが新聞の全面広告に巨大な顔写真を載せて宣伝したのが2005年3月でした。ブログの全盛時代です。ところが眞鍋さんは2010年にブログを閉鎖。ブログの人気が衰えてから早くも五年の歳月が経ちました。入れ替わるようにSNSが台頭し、スマートフォンが世の中を席巻。
当サイトのように個人がデザインも運営もひとりで手がけるウェブサイトは今や絶滅危惧種と言ってよいでしょう。ネットは日進月歩。革新的であることが「正しい」、そして時代遅れなのは「間違っている」というのが「常識」とされます。だからこそ、あまのじゃくであるわたくしは、あえて「時代遅れ」を続けてゆこうと思います。エディターの画面を開いて、HTMLのタグをこつこつ手で書く。その作業そのものが楽しいから。「古いやつだとお思いでしょうが」(© 鶴田浩二)、スマホ全盛時代になっても伝統の技を守ってゆく所存です。
2015年4月30日
世界一どうでもいい知識
世界でいちばん長いオーディオCDのタイトルは1999年に発売された Fiona Apple のセカンドアルバムで、ギネスブックに登録されました。そのタイトルは―――
「When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He’ll Win the Whole Thing ’Fore He Enters the Ring There’s No Body to Batter When Your Mind Is Your Might So When You Go Solo, You Hold Your Own Hand and Remember That Depth Is the Greatest of Heights and if You Know Where You Stand, Then You Know Where to Land and if You Fall It Won’t Matter, Cuz You’ll Know That You’re Right.」
単語数101。邦題は『真実』で、わずか二文字。
ところが2008年に発売されたイギリスのバンド Chumbawamba のアルバムタイトルはさらに長く―――
「The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether from Lack of Ideas or From Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother's Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don't Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature as Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to 'Guard' Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It's Over, Then It's Done, and the Boy Bands Have Won.」
単語数156。おそらくこれが現在もっとも長いCDタイトル。出典は日本レコード協会の雑誌『The Record』第634号(2012年9月)。まったくもってどうでもいい知識です。
2015年4月22日
日本一どうでもいい知識
知らなくても人生困らないし、知ったからといって人生が豊かにもならない知識というものがありまして、きのうのデイリースポーツによると、日本テレビ系「笑点」で山田君が運ぶ座布団一枚の重さは3キロだそうです。三十一年前に山田君が座布団運び役に任命されたとき、座布団があまりにも重いので腕力を鍛えるためトレーニングを始め、体力作りに夢中になった挙げ句、プロボクシングのC級ライセンスを取得。さらに同日の別のデイリ ースポーツの記事によると、山田君は不動産収入が潤沢で、その額は「笑点」のギャラの十倍に及び、横浜市内の〈座布団御殿〉で悠々自適の生活を営んでいらっしゃる。ほんとうにどうでもいい知識です。
2015年4月20日
モバイル・フレンドリーほぼ完了
当サイトのほぼすべてのページをスマートフォン向けに最適化させました。ただし「語尾取り」「とりかえっ語」「意味なし掲示板」などの投稿型CGIプログラムはデザインの性質上小さな画面に凝縮するのは無理なので従前どおりのままです。ですから、あくまでも「ほぼ」すべてです。作業に一ヶ月を要しました。くたびれたー。
2015年4月6日
旬の山菜
今月の壁紙はご覧のとおり竹。春といえば筍。今夜は筍を食べませんか?
2015年4月1日
意識低い系
噂によると世の中には意識高い系と称される男たちがいて、大手をふって闊歩するらしい。もともとはネットスラングらしいのですが、NHKのBSプレミアムで「その男、意識高い系。」というドラマになるくらいですから、流行語なのでしょう。
ひょっとしたら自分にもあてはまるのではないかと、思いつくまま自己診断してみました。
- 就職活動をしたことがない
- ツイッターやフェイスブックなどのSNSでは一切発言しない
- スマホやタブレットなどのモバイル端末を持っていない
- 「アジェンダ」「スキーム」「インフルエンサー」「アントレプレナー」といった言葉はちんぷんかんぷん
- やることなすこと自信がない
- 鬱病が治らない
- 自分なんか存在しないほうが世の中のためになると思う
はなはだ残念な結果になってしまいました。これからは意識低い系として頑張っていきたいと思います。
2015年3月27日
「あなたの予定」復活
「みんなで遊ぼう」のラインアップをちょっと模様替え。「漢字検索試験」の代わりに「あなたの予定」を復活させました。スマートフォンの画面でも文字が大きく表示されるように調整したよ。遊んでね。
2015年3月10日
スマホ向けにナビゲーションを改良
画面左側のナビゲーションメニューをリニューアルしました。スマートフォンの小さな画面でも場所をとらないデザインです。
2015年3月7日
Mobile Friendly
Google によると、スマホやタブレットに適したウェブデザインのことをモバイルフレンドリーと呼ぶそうです。当サイトもおとといからモバイルフレンドリーへの道を歩み始めました。きょうは「更新履歴」と「抑鬱亭日乘」「芸人列伝」「舞台通信」「四字熟語」「今日の一句」をそれぞれスマホ向けにアレンジ。進捗状況については更新履歴をご覧下さい。
2015年3月3日
トップページのデザイン変更
パソコンでご覧の方は「え? 何も変わってないよ?」とお思いでしょう。そのとおり。今までと変わりません。しかしスマートフォンでアクセスすると、あら不思議。画面いっぱいに文字が表示されるではありませんか。
デバイスの解像度に合わせてスタイルシート(CSS)を使い分けることにより、パソコンやスマホ、タブレットでそれぞれ最適に表示されるようになりました。スマホもケータイも持ってないのにデザインを変更できた、その労を多として頂きたい! 今後はほかのページも順次モバイル環境にふさわしいデザインに変えてゆきます。
2015年3月2日
スマートフォン向けのデザイン
Google が四月下旬に検索アルゴリズムを変更するというニュースが飛びこんできて、頭を抱えております。報道によれば昨今のネットはモバイル環境での利用が急増中で、今後はスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に適さないデザインのウェブサイトは検索結果の順位が大幅に下がるとのこと。
当サイトへのアクセスも昨今はスマートフォンからのアクセスが増える一方で、たとえば先月は Android と iOS でのアクセスが全体の三分の一を占めます。しかしサイトのデザインは十年一日のごとくパソコンのディスプレイに最適化して構築しております。理由はただひとつ。わたくしはスマートフォンも携帯電話も所有しないから、です。
とはいえ時勢には逆らえません。スマートフォンでも閲覧しやすいようにデザインを整えるべき時期が到来したのでしょう。今ご覧の「ごあいさつ」ページにスマートフォンでアクセスすると、壁紙が大きく表示されて、中央のメッセージ欄がとても小さく見えるはず。そこでスマートフォン向けトップページを作ってみました。スマホの画面全体に文字が大きく表示されるはずです。ただし難点は左のメニューが文字にかぶさってしまうこと。まだまだ改良の余地があります。
いずれ当サイトのデザインをパソコンでもスマートフォンでもタブレットでも読みやすくなるよう全面的に変更するかもしれません。方法は何通りかあるのですが、いざ作業を始めるとなると、これがじつに面倒! 世に悩みに種は尽きまじ。嗚呼。
2015年3月1日
七つの大罪
人は無意識のうちに罪を犯してしまうものです。キリスト教には七つの大罪がある―――「虚栄」「貪欲」「色欲」「暴食」「憤怒」「嫉妬」「怠惰」。デヴィッド・フィンチャー監督、ブラッド・ピットとモーガン・フリーマン主演の映画『セブン』で有名になりました。これらの罪を犯すと地獄に落ちる。地獄行きだけはごめんです! だからこそ現代人の我々は次に挙げる罪を犯さぬよう、日ごろから気をつけようではありませんか。
- 午後の紅茶を午前に飲む
- ランチパックを夕食にする
- キットカットを割らずに食べる
- かっぱえびせんを途中でやめる
- ごはんですよをパンに塗る
- 食べるラー油を食べない
- ウィダー in ゼリーを飲むのに10秒以上かける
2015年2月18日
グラフに大笑い
折れ線グラフに棒グラフ、円グラフ……。いろんなグラフがあるけれど、こんなに笑えるグラフは初めてです。特にフランスのグラフには爆笑。考えた人えらい!
2015年2月12日
ウルトラマンと『広辞苑』
つい先ほど『広辞苑』第六版で調べものをしたらウルトラマンの項目を発見。びっくりしました。古い版にもあったのかしらと第五版をひもとくと見当たらないので、どうやら第六版で新たに採用されたらしい。ためしに最新版の『大辞林』を引いてみると、こちらにも項目があるではありませんか。なるほどウルトラマンは日本人の常識的な語彙として定着したのですね。しかしながら『広辞苑』第六版の語義には首を傾げざるを得ません。
- 広辞苑 第六版
- 1966年(昭和41)から放送された円谷プロ製作のテレビ番組の主人公。銀色の体をした巨人に変身して、怪獣などから地球を守る。
まるでふつうの人間が特殊能力を使って巨人に変身するかのような説明ですが、皆さんもご存じのとおり、事実とは違いますね。言うまでもなくウルトラマンはM78星雲から地球にやって来た異星人であり、ふだん人間として生活するのはあくまでも世を忍ぶ仮の姿。その点、『大辞林』の語釈は正鵠を射たものです。
- スーパー大辞林3.0
- 1966年(昭和41)から放映された特撮テレビ番組「ウルトラマン」の主人公。宇宙から来て、地球を守るためにさまざまな怪獣たちとたたかう。
ついでに『デジタル大辞泉』の語釈も挙げておきましょう。
- デジタル大辞泉
- 昭和41年(1966)から放送された特撮テレビ番組、およびその作品に登場するヒーロー。銀河系の外からやってきた巨大な宇宙人が、さまざまな怪獣から地球を守る。
どちらもウルトラマンが異星人であることを正しく記述しており、ほっと胸を撫で下ろしました。『広辞苑』の執筆者がどなたかは知る由もありませんが、もう少し頑張って勉強していただきたいの!(by 綾小路きみまろ)
2015年2月6日
ついに日本一!
本日「四字熟語」の登録数が5601項目に達し、三省堂の『新明解 四字熟語辞典』を抜いて日本一になりました。5601番目の項目はS先生の奥様の「童謡答案」。爆笑しました。
四字熟語のページを開設したのは2001年10月23日。当時の名称は「森羅万象」でした。十四年の歳月をかけて日本一の座を獲得。千里の道も一歩から。継続は力なり。
今後は前人未踏の領域を突き進むことになります。記録を伸ばせるところまで伸ばそうではありませんか。これからもご愛顧をよろしく!
2015年1月28日
あと四つで日本一
本日10時17分現在、「四字熟語」の登録数が5597項目に達しました。あと四つで三省堂の『新明解 四字熟語辞典』の収録数を超えて日本一になります。さあ皆さん、張り切ってどうぞ!
2015年1月27日
粗忽センター試験 解答
「粗忽第二共和制」でS先生の奥様が見事に全問正解して下さいました。念のため正答を記しておきます。
- いかりや長介……ベース
- 荒井注……キーボード
- 加藤茶……ドラム
- 仲本工事……ギター
- 高木ブー……ギター
選択肢のうちのウクレレは引っかけ問題でした。でも高木ブーさんは我が国屈指のウクレレ奏者なので、ウクレレも正解に含めます。
2015年1月25日
粗忽センター試験
【問題】 ザ・ドリフターズはコントが有名ですが、もともとはバンドで、ザ・ビートルズの武道館ライブで前座をつとめました。それぞれのメンバーの担当楽器を選びなさい。
- いかりや長介
- 荒井注
- 加藤茶
- 仲本工事
- 高木ブー
- ギター
- ベース
- ドラム
- キーボード
- ウクレレ
2015年1月18日
予告編批評家
世の中に「映画評論家」を自認する人は大勢いますね。少なく見積もっても数百人、ひょっとすると千人以上いるかもしれません。ところが予告編を批評する人がいないのはどういうわけでしょう。予告編だって立派な映像作品なのだから批評の対象にするべきだよ。
ためしに「予告編評論家」で検索してみると一人だけ見つかりました。ツイッターで予告編をコメントつきで紹介するサブラルさん。ツイートにざっと目を通してみましたが、中身は評論というよりは紹介で、批評性に乏しい。ならば僭越ながらわたくしが「予告編批評家」第一号を名乗ってしまおう。
で、個々の予告編を批評するのは別の機会に譲るとして、本日はアメリカ映画の予告編に頻出する常套手段に苦言を呈するぞ。
- 低音ドーンやめろ
ショットの終わりをフェードアウトさせて画面が暗くなると必ずドーンと低音が鳴る。「またかよ!」と心の中で呟かざるを得ない。芸がなさすぎます。 - 安易な細切れ
本のページをパラパラめくるように短いショットをたたみかけて見せる手法はサスペンスを盛り上げるのが狙いらしいが、全然ワクワクしません。「とりあえずたくさん映像を見せておけば客は満足するだろう」という予告編作家の安易な考えが透けて見えるだけ。 - 長すぎる!
かつて予告編は二分間でした。ところが最近は二分三十秒。増えた三十秒が余計。予告編はインパクトが命。短くまとめるのが芸の見せ所。本編を見て「予告編だけでじゅうぶんだった」と失望することが多いよ。
2015年1月12日
ようかんと羊
 我が家のおせち料理にはようかんが欠かせません。子どもの頃は母が作りましたが、近年はわたくしがつくります。
我が家のおせち料理にはようかんが欠かせません。子どもの頃は母が作りましたが、近年はわたくしがつくります。
正月にようかんを食べる由来を先日母に教わりました。かつて東北や北海道では大晦日におせち料理を食べる習慣があり、おせちとは別に口取りというものを用意した。口取りは栗きんとんや玉子焼き、ようかんなどの甘味で、子どもは本膳のおせち料理よりも甘くておいしい口取りが楽しみだった。元日はシンプルな雑煮を食べるだけだったとのこと。
ようかんといえば、もうひとつ長年の疑問があります。漢字で書くとなぜ「羊」が出てくるのか。さっそく調べてみよう。まず『百科事典マイペディア』。
もとは中国から伝わった羊肉の羹であったが、材料をアズキに代え、甘味を加えて菓子に発展させたもの。
もともとは羊の肉だったのですね。「あつもの」とは肉や野菜を煮こんだ熱いスープのこと。「羮に懲りて膾を吹く」の、あの「あつもの」です。ついでに『世界大百科事典』も調べてみましょう。
もともとは中国で古くからつくられていた羊肉の羹、つまり汁であった。日本で初めて〈羊羹〉の語が見られるのは南北朝~室町初期に成立した《庭訓往来》などの往来物においてであり、このときすでに汁でなくなっていた。
やはり中国では羊肉のシチューのような料理だったようです。これが日本に伝わって小豆と砂糖の甘味になってしまったのですから、所変われば品変わるにも程があるじゃないか。
2015年1月4日
待てば海路の日和あり
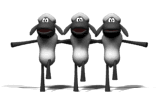 今朝NHK総合「ブラタモリ」の三田・麻布完全版を堪能しました。来週火曜は京都編。いいお正月だなあ。しかも四月から三年ぶりにレギュラー番組として復帰するというではありませんか。あんまり嬉しくて羊たちも欣喜雀躍。
今朝NHK総合「ブラタモリ」の三田・麻布完全版を堪能しました。来週火曜は京都編。いいお正月だなあ。しかも四月から三年ぶりにレギュラー番組として復帰するというではありませんか。あんまり嬉しくて羊たちも欣喜雀躍。
2015年1月3日
風街ろまん
 十二月三十日に放送されたBSプレミアム「名盤ドキュメント はっぴいえんど『風街ろまん』」で松本隆さんが証言したところによると、風街とは東京オリンピックによって消滅してしまった、記憶の中にある東京のことだそうです。
十二月三十日に放送されたBSプレミアム「名盤ドキュメント はっぴいえんど『風街ろまん』」で松本隆さんが証言したところによると、風街とは東京オリンピックによって消滅してしまった、記憶の中にある東京のことだそうです。
東京は一九四五年三月十日の大空襲によって下町が破壊され、一九六四年のオリンピックで大々的な「町殺し」が行われ、性懲りもなく八十年代にはバブルでさらに破壊が進んだとは小林信彦さんが常々述懐するところ。
二〇二〇年のオリンピックで東京の街はまた消滅するでしょう。きらきら光り輝く廃墟の中、ノスタルジックなかつての少年は「風をあつめて」散歩するのです。
2015年1月2日
謹賀新年
 サイトを開設して十五回目の正月です。これからも張り切って運営するぞ。皆の衆もこぞって遊んで下さいませ。
サイトを開設して十五回目の正月です。これからも張り切って運営するぞ。皆の衆もこぞって遊んで下さいませ。
2015年1月1日