今年の10大ニュース
2010年の「世界10大ニュース」が決まりました。当サイトは2001年から毎年の10大ニュースを読者の皆さんの投票を無視して選んできました。今年も国内外から3万604通の応募があり、全てを無視して集計した結果、下記の通りとなりました。
10位 ドイツの警官、若者に雪玉投げられ唐辛子スプレーで反撃 [ロイター]
乱闘騒ぎを捜査中だった警官を襲った雪玉兵器。怪我人が出なかったのが不幸中の幸いでした。
9位 17匹の子犬を産んだ母犬、避妊手術へ [AP]
純血腫のローデシアン・リッジバックが26時間かけて17匹の子犬を生んだベルリンの事件には世界中の人々が凍りつきました。「子犬たちの面倒をみるのがフルタイムの仕事になってしまった」と慨嘆する飼主のラモーナ・ヴェルゲマンさんに人々の同情が集まりました。
8位 ディランのスタッフを詐称、ピザ178枚を注文した男、弁償へ [AP]
ボブ・ディランのバックステージパスを付けた男がピザパーラー「アントニオズ」でピザ178枚を注文し姿を消した事件。犯人はニュージャージー在住で氏名などは明らかにされておらず、弁償額も不明。午前5時半まで残業してピザを焼き上げた「アントニオズ」の従業員の胸中は察するに余りあります。
7位 30年前に盗まれたハンマーの代金が送られてきた [AP]
ペンシルバニアの工具販売会社に何者かが45ドルの小切手を送りつけた事件。「30年ほど前に盗んだハンマーの代金と利子です。盗んでごめんなさい。その後改心しました」と書かれた手紙は世界中の人々の心に残りました。
6位 世界最大のヘビの娘の名前、「ハンナ」に決まる [AP]
米オハイオ州のコロンバス動物園で世界最長のアメニシキヘビ(7m30cm)が死に、その娘(5m40cm)の名前をつけるアンケートで「ハンナ」に決まったニュース。自分と同じ名前をつけられた飼育係ジャック・ハンナが言い放ったジョーク「絞め殺されそうな気分だ」は世界中の人々の心を癒しました。
5位 89歳の男性、76年前に借りた本を図書館に返す [AP]
13歳の時に借りた『フランダースの犬』を76年ぶりにマウントクレメンス公立図書館(米ミシガン州)に返却したマーク・マッキーさん(89歳)。延滞金数千ドルは請求されず、同図書館はマッキーさんに新しい『フランダースの犬』を送る予定ですが、次回の返却は何十年後になるのでしょうか。
4位 中国の地下鉄駅に「生きたカニ」の自動販売機 [ロイター]
中国江蘇省南京の地下鉄駅に設置された「生きたカニの自動販売機」。出てきたカニが死んでいた場合はあらためて生きたカニを三匹もらえるシステムは、「カニの南京大虐殺ではないか」との批判を浴びました。
3位 車で銀行まで送り迎えしてあげた女性、実は銀行強盗犯だった [AP]
男性(26歳)が善意から車で銀行へ送り迎えしていた知人女性(70歳)が強盗だった事件。何を信じればよいのかわからない時代の暗部を鋭くえぐり出したニュースでした。
2位 「元気のない女性を笑わせたかっただけ」全裸になった郵便配達員を逮捕 [AP]
配達地区の女性が「ストレスがたまっているように見えた」ので全裸で郵便を配達し逮捕された米ウィスコンシン州の郵便局員(52歳)。「笑顔だけをまとって」郵便を配ったのは「愚かなことだった」と反省しているそうです。
1位 理髪店に車が突っ込む事故、それでも店主はすぐに客の散髪を再開 [AP]
米アラスカ州アンカレッジの理髪店にSUV車が突っ込んだものの、店主ヘン・ソン氏は事故に動じず、直後に客二人の散髪をきちんと終えたニュース。防犯カメラには事故直後の破壊された店内でこともなげに散髪を再開するソン氏の姿がはっきり映っていました。事故車のドライバーも店の顧客。危機一髪、間一髪と、まさに「髪」のスペシャリストとしてソン氏の名前は後世に語り継がれることでしょう。
〔編集部: これらのニュースが全てエキサイト世界びっくりニュースで今月報道されたものであることには何の作為もありません〕
2010年12月28日
ルドルフ
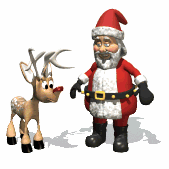 「おつかれさま、ルドルフ。来年も頼むよ」
「おつかれさま、ルドルフ。来年も頼むよ」「はい」
2010年12月25日
「まえがき」
本書は、筆者が四十年にわたって考察してきたクリスマス=盆踊り同系説を説くものである。筆者にとって自著を出版するのは永年の夢であった。その夢が現実となったことを素直に喜びたい。
自著を出版するにあたって何よりも楽しみだったのは『まえがき』を書くことであった。古今東西の書物を繙くたび、著者は真っ先に『まえがき』を読んだ。『まえがき』ほど興味をそそるものはなかった。正直に告白すると、『まえがき』以外読んだことがない。自著を世に問う機会を与えられた筆者は、とるものもとりあえず『まえがき』を書き始めた。読者諸賢が今ご覧になっているこの文章である。
しかし問題が発生した。何を書けばいいのか分からないのである。そこで著者は田口秀雄博士に教えを乞うた。五百冊以上もの著書を有する田口博士に訊けば疑問は氷解するであろうと思ってのことである。しかるに田口博士はこう言われた。『まえがき』は本文を手短にまとめ、何をどう論ずるかを前もって読者に簡潔に伝えるのが役目であり、従って本文を書き終えたのち、最後に書くものである、と。
そんな莫迦な話があるものか、と著者は思った。『まえがき』は書物の開巻劈頭を飾るものである。それを最後に書けとは驚いた。本文の前に書くからこそ『まえがき』である。事の順序を間違えてはいけない。念のため手もとの辞書を引いてみたところ、『本文に入る前に簡単に書き添えること。また、その文章。序文。端書き。序。』とある。やはり本文の前に書くのが『まえがき』である。斯界の権威であらせられる田口博士も寄る年波で耄碌されたのであろうか。
著者は本書の本文をまだ執筆していない。理由は上に縷々陳べたとおりである。本書はクリスマス=盆踊り同系説を論じるが、どのような経緯によって筆者がこの問題に逢着したか、また具体的に何を考察の対象とするか、そしてどのような手順で論を進めるかについては、本文を執筆していない以上、著者にも全く見当がつかない。しかしながら『まえがき』だけは辛うじて世間に出して恥ずかしくないものを書けたのではないかと自負する。とはいえ、なにしろ初めての書物であり、行き届かぬ点が多々あろうと思う。読者諸賢のご叱責をこいねがう次第である。
2010年12月24日
地図
東浩紀が編集長をつとめる雑誌『思想地図β』が今月創刊された。現物を手にしておらず、特設サイトで目次を眺めただけだが、「地図だな、やっぱり地図なんだな」と思った。
「これからは地図で行くよ」と高らかに宣言したのは野田秀樹だった。ロンドンでの研究を終えて帰国した野田が新たな企画集団「NODA・MAP」を設立したのが1993年の秋。同じ年、宮沢章夫が地図を手がかりに書いた『ヒネミ』で岸田國士戯曲賞を受賞した。大瀧詠一が地図を手に三年かけて築地月島の街路を隈なく歩き、成瀬巳喜男の『銀座化粧』と『秋立ちぬ』の全ロケ地を特定し、川本三郎を驚嘆させたのが2008年。そしてNHK「ブラタモリ」ではタモリが古地図を手に東京を歩く。
地図は時間と空間の織物だ。何かを始める。ゼロからスタートする。そのゼロ地点は時間と空間のどこにあるのか。自分が立っているこの場所は時空間のどこに位置するのか。いつ、どうして、そこがゼロ地点になったのか。考える人はたいてい地図を見る。そして地図を作り直す。その作業こそが「考える」ことなのだろう。
2010年12月23日
エルチェの神秘劇
本日午後3時15分からNHK総合「世界遺産への招待状」でエルチェの神秘劇が紹介されます。放送されるのは今年三度目くらいかしら。放送されるたびに当サイトのアクセスが急増します。教会のスペクタクル劇、ぜひご覧下さい。
2010年12月21日
「英王子ら」
今朝の共同通信の見出しに驚いた。
「英王子らの公式婚約写真発表 史上最もくだけた雰囲気」
ウィリアム王子とケイト・ミドルトンの婚約写真が公式に発表され、写真を見るとたしかにくだけたポーズで一般市民と見紛うばかりだ。だからといって「王子ら」はひどい。
「ら」で呼べるのは対等の関係もしくは格下の相手だ。念のため『明鏡国語辞典』をひくと、
人を表す語に付く場合はしばしば謙譲または蔑視の気持ちを含む。目上の相手については使わない。
とあり、『大辞林』も、
人を表す名詞や代名詞に付いて、複数であることを表す。謙譲・親愛・蔑視の気持ちを含んで、それと同類のものを漠然とさす。目上の人を表す語には付かない。
と、きっぱり釘を刺している。
父チャールズ皇太子に次ぐ王位継承者らしからぬ「くだけぶり」に記者の筆がすべったか。だけど本当に我が目を疑ったよ。一瞬、海老蔵を半殺しにした張本人はウィリアム王子かと思った。
2010年12月13日
「写真はイメージです」
チラシや広告でよくお目にかかるフレーズだが、いつ見ても奇異な印象を受ける。言いたいことはわかる。「この写真は実物とは限りません。あくまでも雰囲気というか、こんな感じってことで、ご了解下さい」ということだ。しかし写真は映像(イメージ)だから同語反復ではないのかと思ってしまうのだ。
「音声はイメージです」
いやいや、サウンドだろ音声はと、つい突っ込みたくなる。だからといって「音声はサウンドです」では何のことかわからない。「これはアリコのCMです」
調子に乗りすぎた例である。いつかきっと「これはテロップです」というテロップが出る。
2010年12月7日
マール・ポッカートニー
名字と名前の最初の文字を入れ替えると……イメージががらりと変わるから不思議。
2010年12月4日
蠟月
近所の銀杏並木が息を呑むような美しさ。そしてもう十二月。冗談だよと誰か言って欲しい。
2010年12月1日
ホリデーインタビュー
粗忽主義貧民共和国BBSで古いひとさんが告知して下さいましたが、明後日23日(火)午前6時30分、NHK総合「ホリデーインタビュー」に小島章司さんが登場します。取材は故郷の徳島で行いました。テレビでは滅多に見られない小島さんの姿、ぜひご覧下さい。
2010年11月21日
schola
坂本龍一の音楽講座「スコラ」の特別講座が始まりました。教育テレビ。昨夜はバッハ、7日(日)は山下洋輔とジャズ、14日(日)はYMOによるドラムズ&ベース。夏に見逃した方は是非。
2010年11月1日
2355
日本一アバンギャルドなテレビ局、教育テレビ。なにしろ2004年の「ロシア語講座」がすごかった。舞台はなぜか寿司屋。板前なのか下働きなのか、ダニエル・カールがねじり鉢巻きをして山形弁を話し、カウンターの向こうには職業不明のロシア人女性。生徒役はダニエル・カールとさとう珠緒。「山形弁を話す板前(?)のアメリカ人が寿司屋のカウンターで素性の知れないロシア人女性にロシア語を習う」――どうすればこんなシチュエーションが思いつくのか。「ビット・ワールド」など、すぐれて実験的な番組も数多い中、あの「ロシア語講座」は実験しすぎ。ぶったまげたものです。
そんな教育テレビにしかできない番組のひとつが「2355」。毎晩23時55分から五分間だけ放送されます。不思議な番組ですよ。
2010年10月21日
チ・チ・チ、レ・レ・レ!
¡Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le, los mineros de Chile!(チ・チ・チ、レ・レ・レ! ロス・ミネロス・デ・チレ!)2010年10月14日
サイト十周年 粗忽天皇のおことば
本日、テアトゥルム・ムンディ十周年の記念式典が行われるに当たり、粗忽者の皆さんと一堂に会することは、私の深く喜びとするところであります。
当サイトが設立された十年前、平成十二年十月六日、我が国はしっかり者が横行闊歩し、慎重主義は国民病とも呼ばれていました。その猛威から人々を救うことを使命としてこのサイトは設立されました。
一時閉鎖された時期がありました。半年以上管理できなかった時期もありました。幾多の困難を乗り越えながら、皆さんが手を携え、粗忽者の安寧と繁栄のために貢献してこられたことを、心からねぎらいたく思います。
どうか、体を大切にし、励まし合って、今後とも元気にうっかり過ごされるよう願っております。
2010年10月6日
模様替え
今月6日にサイト開設十周年を迎えるにあたって、ちょいと模様替えしました。変更したのは画面の上の方、各ページのタイトルが表示される部分だけです。トップページは十年前に似たデザインに戻しました。IE 以外のいわゆるモダンブラウザ(Firefox, Chrome, Safari, Opera)推奨です。
2010年10月1日
知ったかぶり
社団法人出版梓会が発行する「出版ダイジェスト」を読むのが楽しみだ。四ページのタブロイド紙で、年に四回届く。「みすず書房の本」と「白水社の本棚」がお気に入りで、何が楽しいかといえば、知ったかぶりができる、この一点に尽きる。きのう届いた「白水社の本棚」でも知ったかぶりができた。
- 現在の〈桃太郎〉話の標準型は明治20年(1887)に初めて教科書に掲載され全国に広まった。
- 昭和16年(1941)の大東亜戦争二周年記念ポスター「征け桃太郎、米英を撃て」には、宝船に乗った桃太郎が、赤鬼と化したルーズベルトが住む鬼ヶ島を目指す絵が描かれている。
- 日露戦争開戦の明治37年(1904)に発行された『征露再生桃太郎』ではおじいさんの名がエイゾー、おばあさんがオアメで、英米の国旗柄の洋服を着た西洋人。桃太郎は軍服姿で、きび団子の代わりに爆弾を携え、おシナちゃん(=支那)、おチョーさん(=朝鮮)をいじめるロスケ(=露西亜)を征伐する。
- イランは世界第三位の産油国だが、適切な精油施設がないため、国内で消費するガソリンの半分を輸入に頼っている。
- スポーツバイクの世界では一日100kmがひとつの「壁」とみなされるが、米津一成は400~600km走り、その超人ぶりを「距離感が壊れている」と称す。
- サンスクリット研究の本場はヴァラナシ(ベナレス)。
- モーツァルトには彼だけの特別な技法というものがなかった。
知ったかぶりである。
2010年9月17日
「積もる話に花を咲かせるでしょう」
今朝のYahoo!ニュースによると、今学期から中国の小学校の国語教科書に台湾関連の記述が増えたという。台湾の人たちは歓迎しているらしい。喜ばしい。たいへん喜ばしいが、一年生の教科書に掲載された文章が一部紹介されているのを読んでびっくりした。こんな文章だ。
船よ、白い帆をあげて台湾に向かっておくれ。台湾のお友達を乗せたら、私たちの学校に連れてきておくれ。そして、私たちは両手をしっかりと握りしめ、積もる話に花を咲かせるでしょう。
すばらしい内容である。しかし、これ、一年生向けにしてはかなり難しくないか。前半はいい。日本の教科書に載せてもいいくらいだ。日本の一年生が習う漢字はごく僅かだから、実際はこんな感じになるだろう。
ふねよ、しろいほをあげて、たいわんにむかっておくれ。たいわんのおともだちをのせたら、わたしたちのがっこうに、つれてきておくれ。
問題は最後の一文だ。「積もる話に花を咲かせるでしょう」。高度だよ。なんて高度なんだ。このままでは日本の教科書には採用されないだろう。ではどう言い換えたらよいか。
そして、わたしたちはりょう手をしっかりにぎりしめ、そんなじだいもあったねと、いつかはなせる 日がきたよ。
中島みゆきになってしまった。
2010年9月11日
文字中毒
文字が書いてあればなんでも読む。ところ構わず読む。いつも必ず眼で文字を追っていることに、ふと気づきました。
歯を磨きながらチューブの裏の説明書きを読み、ティッシュで洟をかみながらボックスに書かれた怪しげな英文もどきを読む。しかも毎日。何度読んだって内容はわかりきってるのに、眼は勝手に文字を追う。
きょうは飛行機のなかで『翼の王国』を斜め読み。表紙絵は友人の堀越千秋さん。絵描きで陶芸家、カンテ・フラメンコを歌わせれば玄人はだし、筆も立つ。天はときとして二物も三物も与えるものです。不定期連載の随筆が読めて我輩にんまり。堀越さんのサンティアゴ巡礼記と鹿島茂の稀書探訪「ヴュ・パピエの小冊子『パリのダンス・ホール』」と福岡伸一のベルリン報告「溶かされた界面 自然と不自然のあいだ フェルメールの旅――ドイツ編・中編」が読めて、お腹いっぱい。なのにA320の機内説明書を読んじゃった。デザートかしら。
2010年9月9日
首を洗って
日本最北端の県庁所在地に来て三日目。今朝起きたらスペインから待望のメール。年が明けてからこの日をずっとずっと待ち望んでいたのだ。さあ、いよいよだ。スペインよ、首を洗って待っていろ。とてつもないものを見せてやるぞ。
2010年9月7日
流行語大賞
鳩山由紀夫の「ボクはなんだったんでしょう」で決まり。
2010年9月1日
大粗忽まつり
無料レンタル掲示板の老舗といえば、たこ焼き村の掲示板でおなじみの teacup、そして我が粗忽主義貧民共和国の OTD。二大BBSと呼んで差し支えないでしょう。
どちらも十数年の歴史を誇りますが、ネットの世界も栄枯盛衰激しく、teacup は運営会社が GMO に変わって存続、OTD はアルチェからライブドアに移ったものの、ついに来年6月30日をもってサービス終了の仕儀に至りました。
そこで、残り十ヶ月を思う存分楽しむべく、大粗忽まつりを開催する運びとなりました。概要は下記の通りです。
- 名称
- 大粗忽まつり
- 期間
- 2010年9月1日(水)~2011年6月30日(木)
- 書込み内容
- 不問
以上をまとめますと、「今までどおり書き込んでね」ということであります。悔いの残らないよう、むやみやたらにうっかりして下さい。
2010年8月27日
夢声戦争日記
戦後65年、韓国併合百周年、アメリカ海兵隊の沖縄残留をめぐる〈2010年安保〉など、いつにもまして戦争を考える夏です。徳川夢声の『夢声戦争日記』(全七巻、中公文庫)を読んでいます。昭和16年12月8日、真珠湾攻撃の当日から敗戦に至るまでの日々を綴ったもの。
勝っているときの戦争ほどワクワクするものはないようで、太平洋戦争開戦翌年に夢声は「げにや、この元旦!」「この元旦こそ未曾有の元旦である。新聞の見出しだけ読んでも、胸がふくらむ」と、無邪気な興奮を隠しません。
夢声は昭和20年8月10日(!)に〈日本の無条件降伏申入れ〉のニュースを入手します。そして15日の玉音放送を聞いて、こう書き記します。
とにかく唯物科学の最高兵器により、唯物崇拝の徒の日本は全敗した。それだからこそ日本はめでたい。もしも日本が原子爆弾を有していたなら、平然として軍人どもはこれを使用し、世界制覇をしていたかもしれない。が、それは日本の精神的自殺である。現在日本にいる大部分のバカ軍人、バカ政治家どもは、愈々大得意になって世界を地獄にしていたであろう。
これで好かったのである。日本民族は近世において、勝つことしか知らなかった。近代兵器による戦争で、日本人は初めてハッキリ敗けたということを覚らされた。勝つこともある。敗けることもある。両方を知らない民族はまだ青い青い。やっと一人前になったと考えよう。
ふつうの〈愛国者〉が幻滅を味わうに至る心の軌跡をつぶさにみてとれる好個の記録です。
2010年8月22日
「ただ何となく」67% 宇宙人世論調査
【銀河系=ゆう記者】 銀河系統計局(GSO)の調査によると、宇宙人が地球を征服しない理由は「ただ何となく」であることがわかった。
GSOが13日、調査結果を伝えた。
5837穣4822秭8234垓2278京3556兆人の宇宙人を対象にした調査によると、「ただ何となく」地球を征服しない割合は回答者のほぼ3分の2を占め、前回調査の59%から上昇した。
地球の存在さえ知らない宇宙人の割合は79%。
「他の惑星に関心がない」と答えた割合は76%で過去最多。理由として「家にいるだけで宇宙のことがわかるから」「三次元には興味がない。俺の嫁は二次元」「外にでるとキモヲタ扱いされるから」など、宇宙人のあいだでも“引きこもり”が増えていることが窺える。
なお調査方法については、「そもそも“宇宙人”という呼び方自体が人間中心主義。断固容認できない」(ゴメラ星・27歳)など、手厳しい意見もある。
地球防衛軍・本多猪四郎元帥の話 「宇宙人はこれまで秘密裏に大勢捕獲されてきたが、高度な文明を持ちながらなぜ地球を征服しないのかが謎だった。地球には征服するほどの魅力がないのだろう。これからは“町おこし”ではなく“地球おこし”が必要」
2010年8月13日
J-POPの元祖
オールディーズというとチャック・ベリーやサム・クック、ビーチボーイズ、フォー・シーズンズなんかをイメージすると思います。手許に資料がないのでうろ覚えですが、ニューヨークに最初のオールディーズ・レコード専門店 "Oldies but Goodies" が登場したのがたしか1961年で、同じ年にやはり "Oldies but Goodies" というコンピレーション・アルバムが発売されました。その時点で人々がイメージした〈オールディーズ〉は主として1950年代前半のロックン・ロール黎明期。ザ・コーズ、ザ・コースターズ、ザ・ドリフターズなどのドゥー・ワップや、ファッツ・ドミノ、サム・クックなど、わずか五年から十年くらい前の楽曲が〈古き良き音楽〉だったわけです。
そう考えると、今から三十年前の1980年はもう〈大昔〉と言っていいでしょう。J-POPという言葉が誕生する前の時代。〈ニュー・ミュージック〉全盛期です。しかし当時の傑作アルバムを聴くと音の良さに腰が抜けそうになります。
本日発売の『レコード・コレクターズ』九月号、特集は80年代の〈日本のロック・アルバム・ベスト100〉。一位は日本ポップス史の金字塔、大滝詠一『ロング・バケイション』。これはもう誰にも異存がないでしょう。四位がYMO『BGM』、六位が山下達郎『Melodies』。山下達郎は十三位にも『FOR YOU』がランクイン。
『Melodies』に関して、評者の高浪昇は「完璧と言えるサウンドプロダクション」と正しく指摘。『FOR YOU』については渡辺亨が「日本のポップスでもっとも音の抜けがいいレコードの一つだろう」「この音の抜けの良さは、本家のブラコン[ブラック・コンテンポラリー]を凌ぐ」と、これまた正しく指摘しています。
音の良さを実現したのは誰か――雑誌では触れられていませんが、吉田保です。『ロング・バケイション』も『Melodies』も『FOR YOU』も、吉田保がレコーディング・エンジニアとミキシングを担当。ちゃんと聴いたことがない人、ぜひお聴きなさい。わたくしこのところ毎日『FOR YOU』を聴き直しているのですが、音の良さに溜息が出るばかり。来年三月には『ロング・バケイション』三十周年記念盤がリリースされますよ。
2010年8月12日
池下彰の学べないニュース
- 池下
- 最近はニュースをわかりやすく解説するバラエティ番組が大人気ですよね。なかでも引く手あまたなのが池上彰さん。
- 土田
- 池下さん、名前、似てますよね。
- 池下
- よく言われます。
- 里田
- 兄弟……?
- ひとり
- 名字がちがうでしょ!
- 土田
- 里田、今途中で気づいて言葉飲み込みましたね。
- 池下
- 語り口がとても親しみやすくてわかりやすい池上さんですが、ところで皆さん、池上彰さんってどういう人か、ご存じですか?
- ひとり
- 元NHKのアナウンサーですよね。
- 池下
- はい。「ニュースセンター845」とか「イブニングネットワーク」のキャスターを務めた人です。でも、池上さんが有名になったのは何と言っても「週間こどもニュース」ですね。
- 里田
- わたし見てました!
- 土田
- あれって土曜の夕方6時だよね、放送時間。お前、土曜日うちにいるの?
- 里田
- 収録なかったから……。
- 土田
- 収録なかったからって……ウソでもいいから別の理由を考えようよ。テレビ的にさ。夢を売ろうよ。芸能人だし。
- 池下
- 2010年からは日曜の朝に移動したんですが、去年までは土曜の夕方6時10から放送していました。池上彰さんは「お父さん」の役で、お母さんと三人の子供たちに最新ニュースを説明するという構成でした。ところで「週間こどもニュース」のタイトル文字、覚えてますか?
- ひとり
- あー、なんか手書きの文字だったような気がします。
- 池下
- そうなんです。ミミズののたくったような字、というと語弊がありますが、味のある手書きの字でした。あの字、実はきんさんぎんさんが書いたんです。
- 土田
- え? そんな昔から放送してたっけ?
- 池下
- 放送開始は1994年なんです。ただし、きんさんぎんさんが書いたタイトルが使われたのは1994年から2004年までで、2005年から2009年までは松井秀喜さんの字なんです。
- 一同
- へぇ~!
- 池下
- 「週間こどもニュース」は人気がぐんぐん上がりました。その証拠に、日本PTA全国協議会という組織があるんですが、この組織が2006年に行った調査で、「親が子供に見せたい番組」の7位にランクインしたんです。
- ひとり
- わかるなあ。
- 土田
- 「ロンドンハーツ」とは大違いだ。
- ひとり
- 比較するほうがおかしい。
- 池下
- あの番組は大人のファンも多かったんです。そんな池上さんですが、2005年3月にNHKを退職します。そして同じ年の8月6日に日本テレビ系の「世界一受けたい授業」に出演。これが民放初出演なんです。
- ひとり
- ちょうど五年前ですね。
- 池下
- 8月6日って、おとといですが、日本にとっては特別な日ですよね。
- 里田
- 終戦記念日?
- 池下
- 惜しい! 終戦記念日は8月15日。8月6日は広島に原爆が投下された日です。おととい広島で行われた記念式典には国連事務総長が初めて出席しましたね。ほかにもアメリカのルース駐日大使や、核保有国であるイギリスやフランスの政府代表も初めて参列しました。原爆といえば、もうひとつ大事な日がありますね。
- ひとり
- 8月9日。長崎。
- 池下
- そうです。あしたですね。実は8月9日は池上彰さんの誕生日なんです。
- 土田
- うわあ。民放初出演が広島で誕生日が長崎って、〈歩く激動の昭和史〉みたいな人なんだ。
- 池下
- まあ単なる偶然だと思いますが。
- 里田
- 池上さんって何歳なんですか?
- 池下
- いい質問ですねえ。おいくつだと思います?
- 土田
- 若いよね。若く見える。
- ひとり
- 55歳?
- 池下
- 明日で60歳、還暦なんです。
- 里田
- 全然みえない!
- 池下
- さて、民放に出演するようになってからの活躍は皆さんご存じのとおりです。
- 土田
- NHKのアナウンサーって民放で荒稼ぎしますよね。草野仁さんとか。
- 里田
- え? 草野さんってNHKだったの?
- 池下
- 草野さんも元NHKアナウンサーです。
- 里田
- 黒柳徹子さんの旦那さんだと思ってた。
- 土田
- 「世界ふしぎ発見」かよ! お前が世界ふしぎ発見だよ。
- 池下
- 土田さん、今、不思議って言いましたね。
- 土田
- ええ。言いましたけど。
- 池下
- 実は土田さんと池上彰さんとは不思議な繋がりがあるんです。
- 土田
- 繋がり? 何だろう?
- 池下
- 池上彰さんの初恋の人が、なんと土田晃之さんのお母さんの妹さんなんです。
- 里田
- えぇー!
- ひとり
- マジ?
- 池下
- これが事実です。
- 里田
- じゃあ、もし妹さんと結婚してたら、土田さんは生まれなかったってことですよね?
- 池下
- そういうことになりますね。
- 里田
- よかったですね、土田さん、生まれてきて。おめでとうございます。
- 土田
- いやいや、別に今さら祝福されても。
- ひとり
- 土田が「学べるニュース」にレギュラー出演してるのは叔母さんのコネだったんですね。
- 土田
- それちがうから! 何の関係もないから!
2010年8月8日
空を自由に飛びたいな♪
「わがまま言うんじゃありません!」
2010年8月6日
自分でつくる
「便利だが紙の百科事典に較べると信用性は低い」「玉石混淆」「頭から鵜呑みにするのは危険」――賛否両論のウィキペディアだが、誰に頼まれたわけでもなくウィキペディアの編集を始めたのは去年の年の暮れだった。日本語版のとある項目が目にとまり、内容があまりにも貧弱なのを看過できなかった。
「欲しいものがなければ自分でつくる」
心の師匠、大瀧詠一の教えである。
ソニーのウォークマン発売よりはるかに先んじて自作の携帯カセット再生機を持ち歩いていた大瀧詠一。ウォークマンの登場は1979年。二年後の1981年3月、師匠は傑作アルバム『A LONG VACATION』をリリースした。録音バランスが絶妙だったこのアルバムは、オーディオ機器メーカーが新製品を開発する際に参照する標準レコードになり、世界で初めて発売されたCD数十タイトルのうちの一枚になった。以後ソニーは新製品の試作品を師匠に送っては意見を乞うた。
閑話休題。ウィキペディアである。
問題の項目がお粗末なので一念発起し、全面的に書き直した。ついでにスペイン語版と英語版のページもつくった。きょうの時点で検索すると、Google 日本語版が3位、スペイン語版5位、英語版5位、Yahoo! Japan は2位。
編集作業に携わってわかったのは、英語版スタッフがチェックの目を厳しく光らせていることだ。「この項目には信頼に足る参照リンクが少ないか、または皆無です。関連する記事へのリンクを貼って下さい」と、黄色いラベルの注意書きが表れた。イエローカードである。人生初のイエローカード。日本語版とスペイン語版は黙認だ。三つのバージョンすべてにリンク記事を多少増やし、様子を見守っている。
「消費者になってはいけない。生産するものになりなさい」
iPad の発売とその熱狂ぶりについてコメントを求められた宮崎駿が語った言葉である。生産だ。へんてこなものができるかもしれない。まちがいをしでかすかもしれない。だからといってひるんではだめだ。まちがいはきっと誰かが直してくれるはずだ。
2010年8月1日
「茹で玉子になります」
オムライスがおいしいと評判の洋食屋が近所にオープンした。散歩のついでに店の前を通ると入口に人の背丈ほどの立看板があり、モーニングサービスのメニューが大きな写真で紹介されている。トーストとスクランブルドエッグ、サラダ、飲み物。話の種に、日を改めて食べに行った。
店内はガラガラだった。客はほかに一組しかいない。何となく厭な予感がする。モーニングを注文した。十分ほどしてメニューを載せたトレイが運ばれてきた。トースト、ゆで玉子、サラダ、コーヒー。玉子はスクランブルドエッグではなくゆで玉子だった。
食事を終えて店を出て、もう一度看板を見た。大きな写真のスクランブルドエッグの中央に、ものすごく細い白いテープが貼ってあり、ワープロ書きの黒い文字が印刷されていた。顔を近づけないと判読できない小さな文字だ。
「玉子は茹で玉子になります」
オムライスで有名な店だ。しかもオープンしたばかりである。写真にはスクランブルドエッグ。しかし、顔を近づけると「玉子はゆで玉子になります」の文字である。すごくダメな感じだ。
開店早々のこのダメっぷりに、詐欺ではないかと怒りを覚えてもよかったし、呆れてもよかったが、わたくしは別の感情にとらわれた。
「ここにもまた『なります』がある」
もう十数年経つと思うが、世の中のあちこちで「○○になります」のフレーズを見聞きするようになった。飲食店でコーヒーを頼めば「こちらコーヒーになります」だ。たぶん全国的な現象だと思う。
この店が板橋区成増に出店したとしよう。〈成増店〉だ。最寄り駅は東武東上線の成増駅か、あるいは地下鉄有楽町線の成増駅にちがいないと誰もが思う。しかしどういうわけか、いちばん近い駅はひとつ南の東武東上線下赤塚駅、もしくは有楽町線の赤塚駅なのだった。〈成増店〉に行こうと成増駅で降りてあたりをキョロキョロ見回すが、どこにも〈成増店〉がない。駅に戻ってみると、傍らに小さな看板がある。
「成増店の最寄り駅は下赤塚になります」
腹立たしい。腹立たしいが、ここまで来て引き下がるのもくやしい。下赤塚に行く。ようやく店に辿り着く。入口に看板がある。スクランブルドエッグの写真だ。店に入りモーニングを注文する。トレイが運ばれてくる。トースト、サラダ、コーヒー、そして和菓子。東京銘菓だか福岡銘菓だか知らないが、有名な和菓子である。そんな馬鹿なと驚きつつもおいしくいただき、店の外に出てあらためて看板を見る。
「玉子はひよ子になります」
2010年7月27日
「昔の人」は実在の人物か 奈良の遺跡で発掘
【奈良=ゆう記者】 奈良文化財徹底研究所は21日、奈良県明日香村で発掘調査中の遺跡から「ムカシノヒト」という人物が実在した証拠と考えられる土器を発見したと発表した。
調査チームは2008年6月から明日香村の胡乱遺跡で発掘調査を行ってきた。先月末に大量の土器を発見、そのうちの一つに「牟加志乃人」と墨書きされたものがあり、他の土器にはこの人物が遺したとされる数々の文句が刻まれている。
文字は万葉仮名で、現代表記に直せば「昔の人」だが、研究チーム主任の永森茂氏によると、これは特定の個人名である可能性が高いという。「同じ遺跡から大量の文句が出てきたのが証拠。『昔の人はうまいことを言ったものだ』という言い方があるが、おそらくムカシノヒトという名の人物が存在し、その人が当意即妙の言葉を数多く生んだのではないか」と永森主任は推測する。
発掘された言葉の中には「三人寄れば文殊の知恵」「秋茄子は嫁に食わすな」「インパクトの瞬間ヘッドは回転する」など、夥しい数のうまいことが書かれている。調査チームは他にも土器が出土するとみて調査を続行している。
小泉謙一・東京大学教授(免疫学)の話 「胡乱遺跡からは小野妹子が座頭市に宛てたとされる手紙の断片も発見されており、遺跡そのものが捏造の産物である可能性がある。今後の調査を見守りたい」
2010年7月22日
ルピー
インドの通貨ルピーを表す記号はこれまで「Rs」でした。これを「$」「€」「¥」みたいな独自の記号に変えようとデザインを公募、きのう採用が決定したのがこちらの記号。写真の男性はデザインを手がけたインド工科大学のウダヤ・クマール研究員。採用が決まったデザインを誇らしげに掲げています。
アルファベットの「R」の左の縦棒を削り、その代わりに右上に横棒を二本加えたのだそうです。しかしこの記号、ひらがなの「き」にそっくりではありませんか。いちばん上の部分に出っ張りを加えれば完全に「き」です。
この記号を世界に流通させるには、まずユニコードへの登録が必要で、それが済めばパソコンのフォントに組み込まれて、ディスプレイに表示したり印刷したりできるようになるわけですが、日本に限って、当面は「き」でいいんじゃないかと思いたくなります。10万ルピーは「き100,000」。どうでしょう?
2010年7月16日
MVP
南アフリカ大会のMVP(Most Valuable Pulpo)はパウル君に決定。タコはスペイン語でプルポ。
2010年7月12日
23+1名
ヨーロッパ・チャンピオンのスペインがドイツを下してサッカーW杯決勝に初挑戦。7月11日の決勝まで当サイトはスペインを応援するぞ。歴史的な快挙を成し遂げつつあるメンバーは下記の通り(大文字は名字です)。
●GK- カシーリャス
- Iker CASILLAS FERNÁNDEZ
- バルデス
- Víctor VALDÉS ARRIBAS
- レイナ
- José Manuel REINA
- アルビオル
- Raúl ALBIOL TORTAJADA
- ピケー
- Gerard PIQUÉ BERNABÉU
- マルチェナ
- Carlos MARCHENA LÓPEZ
- プジョル
- Carles PUYOL SAFORCADA
- カプデビラ
- Joan CAPDEVILA MÉNDEZ
- セルヒオ・ラモス
- Sergio RAMOS GARCÍA
- アルベロア
- Álvaro ARBELOA COCA
- イニエスタ
- Andrés INIESTA LUJÁN
- シャビ
- Xavier HERNÁNDEZ CREUS
- セスク
- Francesc FÁBREGAS SOLER
- シャビ・アロンソ
- Xabier ALONSO OLANO
- セルヒオ・ブスケッツ
- Sergio BUSQUETS BURGOS
- ハビ・マルティネス
- Javier MARTÍNEZ AGUINAGA
- シルバ
- David JIMÉNEZ SILVA
- ビリャ(ビジャ)
- David VILLA SÁNCHEZ
- フェルナンド・トーレス
- Fernando José TORRES SANZ
- マタ
- Juan Manuel MATA GARCÍA
- ペドロ
- Pedro RODRÍGUEZ LEDESMA
- フェルナンド・ジョレンテ
- Fernando LLORENTE TORRES
- ヘスス・ナバス
- Jesús NAVAS GONZÁLEZ
- デル・ボスケ
- Vicente DEL BOSQUE GONZÁLEZ
2010年7月8日
ユア党
参院選が近づいて気になるのは国外のマスコミが新党の名称をどう伝えているかだ。
「みんなの党」は英語でどう呼ぶのだろう。Everyone's Party だろうか。もしかしたら公式サイトに英語表記があるかも知れないと思いアクセスしてみたら、英語表記はなかったものの、ドメイン名が your-party.jp だ。「みなさんの党」だと言いたいらしい。
スペイン語圏ではどう伝えているのか。キューバの外務省のサイトでは El Partido de Todos と紹介されており、これはまさしく「みんな(=全員)の党」である。一方同じスペイン語圏のパナマでは Tu Partido で、英語と同様「あなたの(=みなさんの)党」だ。驚いたのはメキシコの経済紙エル・フィナンシエロの記事で、El Partido Your とある。一瞬目を疑った。英語の形容詞 Your を固有名詞と勘違いしたらしい。これでは「ユア党」だ。ものすごくうさんくさい党名になってしまった。
「たちあがれ日本」の英語表記が The Sunrise Party of Japan なのにも驚く。「日の出党」だ。「たちあがれ」と「日の出」ではイメージが全然ちがう。「旅館日の出」とか「日の出荘」とか、安宿や安アパートをどうしても連想してしまう。昭和の香り、オヤジ臭紛々たる党名だ。
ユア党と日の出党。腰が砕けます。これぞ拍子抜けまつり。
2010年7月1日
上島竜兵からのメッセージ
あのー日本がデンマークに勝ちましたけど、なんで勝てたかっていうと、誰も期待してなかったからです、ハッキリ言っちゃいますけど。でしょ? 絶対負けると思ってたでしょ? よくて同点でしょ? だから伸び伸びプレーできたんですよ選手は。だから今度のパラグアイ戦、期待しちゃダメです。期待したら負けます。派手に応援とかしたらプレッシャーでつぶれます。応援したくなる気持ちはわかります。わかる。だけど、ここはぐっとこらえてスルーだから。いい? にわかファンになって応援とかしちゃダメだから。今度の火曜日! 29日! 応援するなよ! 絶対応援するなよ! 絶対だぞ! 絶対だからな!
2010年6月25日
拍子抜けまつり
いよいよ夏も本番。今年も「拍子抜けまつり」の季節がやってきました。
「意を決して抗争相手の事務所に乗り込んだら用心棒が子ども店長」
拍子抜けです。
「刺青がキティちゃん」
張り合いがありません。
「我が町に初めて芸能人が来ると聞いて楽しみにしていたら、やって来たのが春一番」
期待は失望の母というフレーズが脳裡を横切ります。
さあ、ふるって落胆しましょう!
2010年6月19日
きょうのヘッドライン
・近畿、東海、中四国で反対のドアが開く
・谷垣総裁、7年ぶりの地球へ
・戻ってきたマラドーナ=豪州砂漠に落下
・日中首脳、2度目離婚
・改革派、警官隊と1次リーグ突破へ
・公安委員長が山菜盗 防犯カメラ設置を批判
・抹茶味のヘッドホン カネボウ化粧品
・AKB大島、インド洋で日本の魅力訴え
2010年6月13日
アメリカさんよ
空を見上げりゃ 爆撃機
ミサイル降る日にゃ 傘になり
お前もいつかは 同盟軍の
傘になれよと 教えてくれた
あなたの あなたの真実
忘れはしない
海を見つめりゃ 原油流出
魚のいのちは 尊いが
油まみれで 虫の息
油田を掘れと 教えてくれた
あなたの あなたの真実
忘れはしない
山を見上げりゃ 山にある
死の灰降る日は 核シェルター
お前もいつかは 世の中に
核を増やせと 教えてくれた
あなたの あなたの真実
忘れはしない
作曲 是俣堂章
唄 森進二
2010年5月30日
連載小説 「氷の炎」 第三回
あれからどのくらい時間が経ったのだろう。武藤の声は聞こえなくなった。聞こえないのは声だけではない。物音ひとつしない。無音の世界。いや、ちょっとちがう。音というものが最初から存在しない世界、そんな感じだ。うまく説明できないけれど。
初めにことばありき――「ヨハネの福音書」冒頭のフレーズを思い出した。世界のはじまりにはことばが、ロゴスがあった。すべてはことばからスタートした。でも、俺が今いるここは奇妙なんだ。ことばなんていうものがない、光もなければ影もない、そんな場所。ああ、イライラする。ここがどこかを言い当てようとすればするほど、ことばが核心から逸れてゆく。
珍しいキノコがどうのこうのと言っていたな、武藤のやつ。「珍しいキノコ舞踊団」のことだろうか。八十年代に大活躍した舞踊団。でも確か「生えている」と言っていた。俺はキノコを探すことにした。
(Book 1 完結。続編 Book 2 近刊予定)
2010年5月28日
コーテーエキ
もし自分が畜産農家だったら目の前が真っ暗になるのは間違いなく、本当に恐ろしい疫病ですが、ラジオやテレビでコーテーエキということばを耳にするたび、真っ先に脳裡に浮かぶのは佐藤製薬のユンケル黄帝液で、あの金色のパッケージに続いてタモリ、そしてイチローの姿がちらつき、意識から遠ざけようといくらもがいても為す術がなく、コマーシャルに洗脳されてしまった事実を痛感して愕然とし、口蹄疫も怖いけれどコマーシャルもそれに劣らず怖いものだと肌身で感じる昨今です。
2010年5月25日
連載小説 「氷の炎」 第二回
硬い板みたいなものに「正」の字がぼんやりと浮び上がった。死んで五日目。あと二日で一週間か。早いものだ。しかし何かが変だ。昨日から一日経ったわけだが、眠ったっけ、俺? 眠ってなんかいないぞ。目が覚めたわけでもない。なのに一日が過ぎたことはまちがいない。証明しろと言われても困るが、一夜明けたのは確実だ。一夜? 夜になったっけ? 太陽も月も見えないのに? それどころか、俺の周りには何にもない。何にもない。せめて真っ暗闇だったら、ああ、どこかに閉じ込められてるんだなとか、宇宙空間に放り出されたのかもとか、想像力を働かせられるのに。真っ白だったら、精神科の病棟とか、『マトリックス』でネオがモーフィアスと出会う仮想現実空間とか。でも、これだけ何にもないとお手上げだ。ちくしょう、どうなってるんだ。
「珍しいキノコが生えてる」
武藤だ。あれ? 気のせいかな? 声が小さい。
「おい、だいじょうぶか? 聞こえるか? どこか具合でも悪くなったのか?」
え? 別に? 別にって言ったのか? 沢尻エリカかお前は。
2010年5月22日
連載小説 「氷の炎」 第一回
死んで四日になる。硬い板みたいなものがあってよかった。指で触れるとその部分がぼんやり滲む。正の字を書けばいい。「止」が逆さになっている。あした棒を一本足せば「正」だ。指で触れるといっても、俺に指は見えない。板みたいなものも。ただ感触があるだけだ。
「死後の世界があるなんて嘘だったな」
武藤が呟く。
「天国とか地獄とかさ。楽しみにしてたのに。煉獄さえないとは」
拍子抜けしたのは俺も同じだ。
子どもの頃から死ぬのが怖かった。大人になって考えが変わった。怖いのは死そのものではなく、死ぬという観念だ。生きている限りこの観念は頭から拭い去れない。死んでしまえば解放される。以来、死後の世界を楽しみに暮らしてきた。そして俺は死んだ。武藤と一緒に。まさかこいつが道連れになるとは。腐れ縁とはよく言ったものだ。
「死んだだろ。ついさっきだぞ、葬式」
「でも死んだ気がしない。現にこうやって喋ってるし」
「喋ってるって、だいたいお前、どこにいるんだ」
「どこって、ここだよ」
「ここって、どこ」
「ここはここだよ。お前こそどこなんだよ」
「ここ」
こう答えるほかなかった。俺は「ここ」にいる。ほかにどんな言い方があるっていうんだ。
「なにそれ」
「だって、見えないし。お互いがさ」
俺もさっきから妙だと思っていた。何も見えない。何も聞こえない。自分の姿も声も。なのに武藤と喋っている。武藤は確かに「ここ」にいる。だってそうじゃないか。「ここ」にいなかったら、一体どこにいるんだ。
2010年5月21日
広域善行団川口組、ふたたび
「ヘイ!」
2010年5月1日
普天間基地移設
アメリカは沖縄の海兵隊をすべてグアムに移転させる計画を進めているはずなのに、一向に報道されないのは♪なんでだろ~、なんでだろ~、な・な・な・なんでだろ~♪(by テツandトモ)
2010年4月23日
もったいなくない
USBメモリーを挿すだけでウインドウズが高速化できる、イーブースター(eBoostr)というソフトがあるそうで、公式サイトにアクセスしてみた。
「余ってるメインメモリをキャッシュ領域として活用!」
なるほど。パソコンに4GBとかの大容量メモリを積んでいる人は結構いる。でも今のウィンドウズは32bitだから、どんなに積んでも3GBしか認識できない仕組になっている。そこでこの eBoostr を使えば、余ったメモリを有効に使えるらしいのだが、説明文を読んで「むむ?」と首を傾げた。
「パソコンに搭載しすぎて余っているメインメモリ、勿体無くないと思いませんか?」
なんか変だ。「もったいないと思いませんか?」でいいのに、「もったいなくないと思いませんか?」だ。もったいないに「ない」をつけると否定の否定でプラスになってしまう。
おそらく「もったいないんじゃない?」というフレーズが頭にあったのだろう。相手の同意を期待して「○○じゃない?」という言い方だ。若者風の言葉遣いをするなら「○○じゃね?」だ。「もったいなくね?」。これだけで充分なのに、「と思いませんか?」と繋げてしまった。「もったいないんじゃない?と思いませんか?」。くどい。ルー大柴の顔のようにくどい。斉木しげるの芝居のようにくどい。
このソフトを使えばウインドウズがサクサク動くようになるかもしれないが、オフィシャルサイトのトップページでいちばん目立つところに書く文章としては、ちょっとみっともなくないと思いませんか?
2010年4月22日
好物
「めぐみちゃんの好きな食べものはなあに?」「キリンさんが好きです。でもゾウさんのほうがもっと好きです!」
2010年4月17日
お大事にして下さい
買ったばかりの音楽CDをパソコンに取り込んだ。曲のタイトルはアルファベットが多く、それがすべて全角で、アルファベットは半角じゃないとどうも気持ちが落ちつかないたちなので半角に直した。全角のコロン(:)もあり、これも半角のコロン(:)に変えようとしたら、変更ができない。何度試してもダメである。どうしてだろう、ファイル名に半角コロンは使えないのかなとネットで検索したらマイクロソフトの解説ページに辿り着いた。
「ファイル名の文字変換を有効にする方法」
ざっと斜め読みしてわかったのは、ウインドウズではファイル名に半角コロンは使えない、でも、ある操作を行えば使えるようになる、ということだ。しかし驚いたのはその説明の仕方だ。
まず「概要」が示される。
「ここでは Windows および UNIX オペレーティング システムに対するファイル名の文字変換を有効にする方法について説明します。」
次が「詳細」で、こう書かれている。
「警告 : 深刻な問題として、オペレーティング システムの再インストールする必要がありますが生じるレジストリ エディターを誤って使用する場合。」
いきなり何を言い出すんだ。文章が脱臼している。続きを読む。
「マイクロソフトではあることができます解決を保証レジストリ エディターを誤って使用起因する問題。 レジストリ エディターは、自己の責任においてご使用してください。」
いったい何事だろう、この口ぶりは。しどろもどろだ。まるで高熱に冒され床に伏せっている病人みたいだ。あなた大丈夫ですかと、つい声をかけたくなる。言いたいことがわかるようでわからない。隔靴掻痒の感である。うっかりレジストリエディターをいじって問題が発生した場合、問題解決をマイクロソフトは保証してくれるのかどうか。いきなり「警告」を発して人を驚かせておきながら、肝腎なことがわからない。
続く説明にも驚かされる。
「UNIX ファイル名は、たとえば、コロンを使用できます (:) が Windows ファイル名をコロン (:) を使用できません。」
「を」が二回続けて出てきた。
「UNIX ユーザー ファイル UNIX ネットワーク ファイル システム (NFS) 共有に対する Windows サービスは、[Windows の不正な文字を作成しようとしましたとすると、試行が失敗し UNIX クライアント コンピューターの入出力エラーが返さ。」
途中で息が切れてしまっているよ。
「この問題を回避する、するのにには有効でない文字を置換するのにファイル名の文字のマッピングを使用します。」
うわごとだ。マイクロソフトさんはまちがいなく重病である。
ページを下にスクロールしてようやく謎が解けた。
「重要: このサポート技術情報 (以下「KB」) は、翻訳者による翻訳の代わりに、マイクロソフト機械翻訳システムによって翻訳されたものです。」
機械翻訳だったのだ。オリジナル原稿は英文である(原文へのリンクがある)。そしていちばん下にはアンケート欄があり、「この情報でお客様の問題は解決しましたか ?」「この情報は役に立ちましたか ?」とある。回答は「はい」「いいえ」「わからない」の三種、そして具体的な意見を書く欄がある。
建設的な意見を言いたくてウズウズする。しかし、アンケート欄に入力したわたしの文章が何かの間違いで勝手に英語に機械翻訳されやしないかと心配になった。なぜか英語に翻訳され、インド人のオペレーターが読み、中国人の技術者に回され、ベトナム人が処理する――こんな状況を想像すると、回答はなるべくシンプルな方がよさそうだ。そこで思いついたメッセージはこうだ。
「お大事にして下さい」
どうか、くれぐれもお大事にしてほしい。
2010年4月16日
平家物語
「その家は平屋であった。」
(藤子・F・不二雄の遺稿/NHK教育「こだわり人物伝 藤子・F・不二雄 ふしぎ大百科 第3回▽パパの四次元ポケット」4月14日より)
2010年4月15日
テンネンダイ
六十年代、七十年代、八十年代、九十年代。ここまではよかった。問題は2000年から2009年までをどう呼ぶかで、提唱されたのが〈ゼロ年代〉だ。
ところがもうひとつ難問が現われた。2010年以降の十年間をどう呼ぶのか。ふつうに考えれば〈十年代〉だ。でも一九一〇年代ととられかねないし、昭和十年代と思われる可能性もあってまぎらわしい。そこでサブカルチャー系の人が〈テン年代〉と名づけた。テンは英語の ten ですね。だけどこの語呂はどうだろう。
「天然鯛」
どうしても天然物の鯛を思い浮かべてしまう。あるいは芸能人だ。天然ボケを売りにする芸能人が胸を張り、高らかに宣言する。
「天然だい!」
テレビ番組や雑誌のキャッチコピーにきっと使われる。「テン年代は天然だい!」。日テレは感嘆符を多用するから「テン年代は天然だい!!!」だ。うるさくてかなわない。
2010年4月3日
TOICA
携帯電話を持たないので〈おサイフケータイ〉に縁はないが、一枚だけ電子マネーを持っている。Suicaだ。正しくは〈ICカード乗車券〉と呼ぶらしい。電車や地下鉄、タクシーで使え、コンビニやキヨスクで買い物もできる。
切符を買わずに改札をスイスイ通れるカード、それがスイカだ。名称の由来を調べたら "Super Urban Intelligent Card" の略称だとあるが、絶対こじつけだ。スイスイに決まってる。
JR各社の電子マネーは Suica のほかにJR西日本が ICOCA(イコカ)、JR九州は SUGOCA(スゴカ)、JR北海道は Kitaca(キタカ)で、どれも名称がわかりやすい。ICOCA は関西弁の「行こか?」だし、SUGOCA は博多弁の「凄か」にちがいなく、Kitaca は「北」だ。日本のどの地方のカードなのかが容易にイメージできる。これらに較べてピンとこないのがJR東海のIC乗車券だ。
「TOICA」
地元なので名古屋駅に行くことが多く、構内で TOICA のポスターをよく目にする。見るたび、頭のなかに、ある文字列が浮かぶ。
「遠いか?」
なんだってこんな名前にしたのか。他社のIC乗車券は利便さや地方の場所を簡単にイメージさせる名称なのに、TOICA は人を一瞬考え込ませる。
「遠いか?」
"Tokai IC Card" の略なのだそうだ。東海(Tokai)とトイカ(TOICA)はアルファベットの並びがよく似ている。なのに、目で見ても耳で聞いても〈東海〉がパッと頭に浮かばない。
「遠いか?」
この〝上から目線〟な感じの問いが怖い。
2010年4月2日
早春の風
大きい風には銀の鈴
けふ一日また金の風
卓の前には腰を掛け
かびろき窓にむかひます
大きい風には銀の鈴
けふ一日また金の風
煙は空に身をすさび
日影たのしく身を嫋ぶ
物干竿は空に往き
登る坂道なごめども
岡に梢のとげとげし
今日一日また金の風……
(中原中也「早春の風」『中原中也全詩歌集(下)』講談社文芸文庫、p.22-23)
2010年4月1日
王女メデイア
四月にコロンビアのボゴタを旅行する予定の方へ。宮城聰氏主宰のク・ナウカ・カンパニーの代表作、ギリシャ悲劇『王女メデイア』が第12回イベロアメリカ演劇祭に参加します。十年来世界各地で大評判をとった芝居。舞台設定は明治時代の小料理屋。客の役人が座興として店の女に『王女メデイア』を演じさせます。
スペイン語圏での上演は今回が初めて。セリフはもちろん日本語、現地の人はチンプンカンプン――というわけで、不肖粗忽天皇、スペイン語字幕制作を担当しました。4月1日から5日まで、ボゴタのコルスブシディオ劇場(Teatro Colsubsidio)です。
「は? コロンビア? 遠くて行けるわけないじゃん」
ご安心下さい。6月に静岡で上演されます。〈SHIZUOKA春の芸術祭〉、日時は6月19日(土)19時30分、26日(土)19時30分の二回。場所は静岡県舞台芸術公園の野外劇場「有度」。必見ですぞ。
2010年3月22日
タッチパネル
映画館に行き、事前にネット予約しておいたチケットを発行してもらうために自動発券機に向かった。予約番号を画面で入力して発券される仕組だ。最初の数字を入力しようと人差し指で押す。反応がない。故障かと思い、もう一度トライ。無反応。少し強く押す。やっぱりダメ。もっと強く押す。やっと入力できた。次の数字も最初はダメで、二度三度と強めに押したらできた。そうやって五桁の予約番号を入力し、無事発券されたチケットを握りしめて劇場に向かいながら、数年前ロサンゼルス空港に行ったときのことを思いだしたのだった。
例のテロ事件以来、アメリカは入国管理が厳しい。入国審査では指紋をとられる。カウンターの登録パネルに左の人差し指を当てた。審査官が首を横に振り、もう一度やれという。再度挑戦。また首を振る。認識されないらしい。どうすればいいのか、目で訊ねると、「右の指で上から強く押せ」という。やってみる。また首を振る。そして審査官は言ったのだ。
「お前の指はクリーンすぎる。おでこの脂をつけて押せ」
言われたとおりにやってみると、あっさり認識された。そのとき初めて、わたしの指は脂分が極端に少なく、ぱさぱさであることを知らされたのだった。
世の中はタッチパネル全盛だ。電車に乗ると女の子が iPhone の画面を指で撫でて、すいすいスクロールさせている。iPad の発売も間近だ。昔ながらのパソコンはタッチパネルに取って代わられようとしている。そんな時代に出現する悲しい人たちがいる。
「タッチパネルを前に、なす術もない人」
センサーが感知できないほど指がぱさぱさな人だ。彼らはタッチパネルに存在を否定される。目の前にいるのに「いない」とされるのだ。こんな悲しいことがあるだろうか。悲しみを喜びに変えるには、指先を脂ギトギトにしなしくてはならない。その方法としてわたしが知っているのはたった一つだけだ。
「オリーブオイルをぐいぐい飲む」
ある俳優が、コントで全身をテカテカにする必要があり、毎日オリーブオイルをがぶがぶ飲んだのだ。「おでこ、テカテカになりますよ」と、その俳優は誇り高く役作りの秘密を語っていた。
わたしは iPhone に触ったことがない。買う予定もないが、なにしろタッチパネルの時代である。自分が、いま、ここに、紛れもなく存在することを証拠立てるために、オリーブオイルを飲まなくてはならない。しかもがぶがぶだ。オリーブオイルをがぶがぶ。本当にいやだ。
2010年3月17日
舞台通信
アドレスを変更しました。新しいURLはこちらです。
http://www.theatrum-mundi.net/butai/
お気に入りに登録して下さっている方は、お手数ですが登録し直して下さい。旧ページからは自動的にジャンプします。
2010年3月12日
あれから五年
Firefox 1.0 がリリースされたのが2004年。今ではヨーロッパでのシェアが28%、日本は25%、当サイトも10%の人が Firefox です。
2005年8月19日ニューヨークタイムズに Firefox 1.0 の全面広告が掲載されました。わたくしの名前も載っています。30ドル寄付して載せてもらいました。名前を見つけた人にはステキなプレゼントが当たる(かも)!
2010年3月8日
チリ大地震
ご友人やお知り合いに被害はありませんか。心からお見舞い申し上げます。
2010年3月1日
展覧会のお知らせ
親の顔が見たい――誰もが一度はそう願ったことがあるでしょう。本展覧会は日本を含む世界各地の秘蔵コレクションから「親の顔」を集めた、芸術史上初の試みです。
- 展覧会名
- 誰もが見たい親の顔
- 会期
- 2010年2月20日(土)~2月28日(日)
- 会場
- 国立親美術館
- 開館時間
- 午前10時~午後6時
- 観覧料
- 親 4,500円 子 無料
2010年2月20日
苦節七年
ウェブでルビをどう書けばよいのか。どのブラウザでも行間がズレないよう表示させるにはどうしたらよいのか。試行錯誤を続けて七年、ようやく簡素なスタイルシートで実現にこぎつけました(ただし IE6 と IE 7 は未確認)。
確認したブラウザは次の通りです
Firefox 3.6
Safari 4.0.4
Opera 10.10
Chrome 4.0
「表示がおかしいよ~」「行間が妙に広いよ~」という方、ぜひBBSにご報告下さい。
2010年2月14日
居酒屋風景
「いやあダメだったね、サントリーとキリン」
「面子があるんだろうな、どっちも」
「さてと。何にする?」
「とりあえずビール」
「あ、この店サントリーとキリン両方あるぞ」
「両方頼むか」
「半分ずつチャンポンしてか」
「グラスの中で合併ってか」
「そのグラスを持ってるオレたちはグラス・ホールディングス」
「がはは」
「がはははは」
……こんなオヤジが全国に少なくとも五百人はいると確信するものであります。
2010年2月13日
あぶり出し
子供の頃よく遊びましたよ。年賀状にみかんの汁で文字を書いたり。その点ウェブは簡単。文字の色を背景色と同じにすればOK。ご覧のトップページでも七前からあぶり出しを使っています。
2010年2月12日
草葉の陰のシェイクスピア
どいつもこいつも俺の研究ばかりしやがって。他にいねえのかよ他に!
2010年2月1日
抑鬱亭日乘リニューアル
6年ぶりにデザインを変更しました。気分転換です。新しいアドレスは下記の通りです。
http://www.theatrum-mundi.net/nichijo/
ブックマークやお気に入りに登録していらっしゃる方は、お手数ですが新しいアドレスで登録して下さいませ。
2010年1月30日
平面
3D映画『アバター』を観た。いろいろ感じたことはあるが、立体駐車場が登場して「平面駐車場」が生まれたように、『アバター』によって「平面映画」が誕生したのではないだろうか。
映画のプログラムをパラパラめくったら「立体映画研究家」という肩書きの人が解説を書いている。こんな職業があるとは知らなかったよ。誰が最初に「平面映画研究家」を名乗るか、興味津々である。
2010年1月18日
絵師
ちょっと外に出れば必ず目に入るのに誰がそれをデザインしたのかわからないモノが結構ある。誰が作るのだろう、誰がデザインするのだろうと、いつも不思議に思う。
「看板の人物イラスト」
たとえば「飛び出し注意」だ。たいてい男の子や女の子のイラストが描かれる。あの絵は誰が描くのだろう。専門のイラストレーターがいるのだろうか。
気になる理由は、あのなんとも形容しがたい味わいだ。いびつというか、突拍子もないというか、とにかく独特としか言いようがない味がある。「何を参考にすればこういう絵になるのか」がさっぱりわからない場合が多く、興味は尽きない。
人気商品などでは絶対にお目にかかれない美意識に貫かれた絵。あれらを描く絵師はなんという職業なのだろう。「イラストレーター」ではないと思う。たぶん。どういう手順を踏めば絵師になれるのだろう。正月早々謎が解けない。そして寒い。
2010年1月10日
謹賀新年
ロイ・シャイダー主演の『2010年』を劇場で観たとき、〈2010年〉は遠い遠い未来でした。生きてその年を迎えることがどうしても想像できなかった。その年が本当にやってくるなんて。木星が第二の太陽になることもなく、有人探査船ディスカバリー号が木星に達することもなく。あの頃の未来は輝いていたなあ。こんなはずではなかったんですよ、〈21世紀〉は。だから『クレヨンしんちゃん/嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲』が製作されたわけです。
去年は人に喜ばれる仕事ができるしあわせを噛みしめた一年でした。今年も粗忽を極めるべく精進して参ります。
2010年1月1日